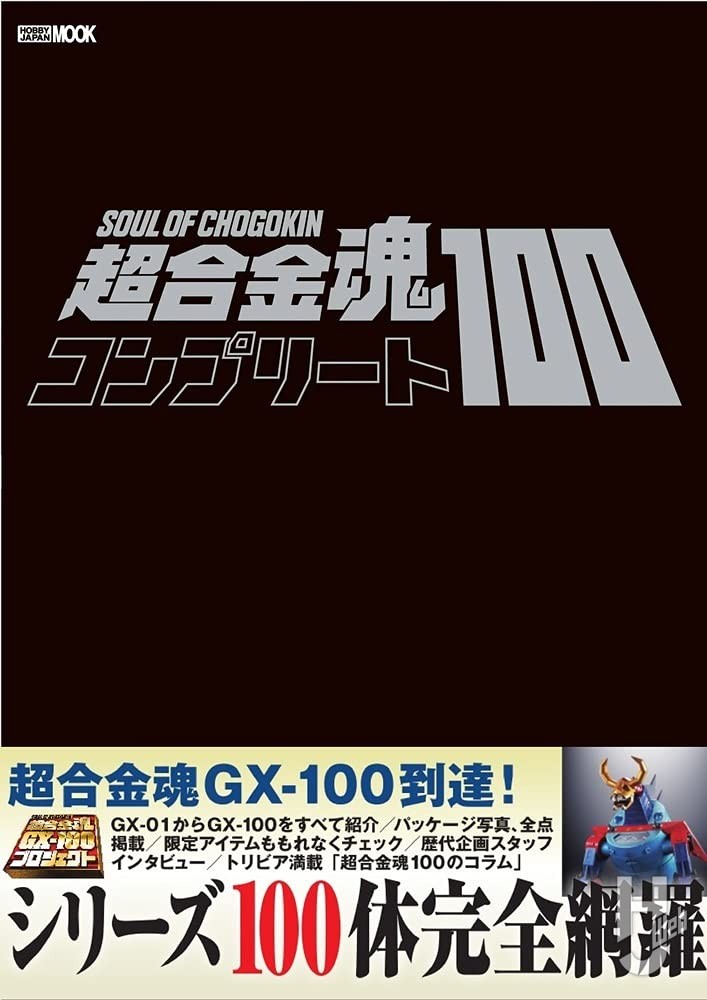グレンダイザーINFINITISM 月刊ホビージャパン2019年7月号(5月25日発売)

ダイナミック企画×BANDAI SPIRITS ホビー事業部×月刊ホビージャパンで贈る新たなるフォトストーリー『グレンダイザーINFINITISM』。『マジンガーZ』『グレートマジンガー』のその後に続く『グレンダイザー』の世界を描く、オリジナルストーリー第3回!
原作・企画
ダイナミック企画
ストーリー
早川 正
メカニックデザイン
柳瀬敬之
協力
BANDAI SPIRITS ホビー事業部
ホビージャパン
第3回
アガルタ
日本――北海道・摩周湖。
9万ヘクタールに及ぶ阿寒・摩周国立公園は古代の火山活動以来、凡そ三万年、殆ど人の文明も踏み入らず、自然の原生を保っている。周辺には観光用の質素な展望台が三ヶ所あるだけで、この四年で建設されたGCR《摩周湖国際宇宙観測センター》とその関連施設である白樺牧場を除けば、何もない北の原野だった。
午後2時45分――霧もなく、視界は開けている。静止衛星フォトン・アルファーからの急報を受けたGCR《摩周湖国際宇宙観測センター》は未確認物体を速やかにレーダーで捉えた。落下軌道を辿り直前には肉眼でも捉えたが、それは湖の上空に到達した瞬間、視界からもレーダーからも消失した。
――消えた? そんなことが……!
所長の宇門源蔵は目を疑った。物理法則なら、未確認物体は湖面に22.3度の角度で突入し、湖底をえぐりカルデラの湖岸を突き破って溝を穿ちながら数キロ進み、やっと停止するかどうかのインパクトを起こすはずだった。
「反応が、湖底から……!」
大型スクリーンに映し出された近域のデータMAPに目を移すと摩周湖の湖底に同一と思われる物体の反応が浮かび上がった。
――瞬間移動して……停止しただと?
「波一つ立てず、湖底に静止しています」
2時間後――第5警備地区の管轄である別海と美幌の駐屯地から陸上自衛隊の部隊車両が到着し湖岸に設営を開始した。未確認物体は摩周湖のほぼ中央に位置するカムイシュ島の北東400メートルの湖底にあり、カムイヌプリの内輪の外斜面に建つGCR(グランドコントロール)《摩周湖国際宇宙観測センター》との丁度対岸に自衛隊の本部が設けられた。
静止衛星フォトン・アルファーで一部始終を目撃し地上に報告した剣鉄也は、万が一を考えて光子力研究所の着陸施設に直行するオービターに乗り込んだ。
亜空間トンネルから現れた、角の生えた巨大な人型の物体が、もし、何らかの〝悪意〟を持った戦闘用ロボットなら、それに備える必要がある。鉄也はアメリカで新しい生活を謳歌している兜甲児を戦場に引き戻したくはなかった。
「ジュン、ここは頼んだぞ」
「わかってる。鉄也こそ、気を付けてね」
「ああ、行って来る――」
鉄也を乗せたオービターがフォトン・アルファーから発進した。
地球周回軌道からの離脱に1時間。着陸ポイントを逆算した大気圏再突入に30分。地上の光子力研究所に戻るには、最低でも1時間半を要する。
――また、闘いの日々が始まるのか……!
ミケーネ帝国との戦いが終結した後、マジンガーZとグレートマシンガーは光子力研究所の地下格納庫に動態保存された。
鉄也はその時の光景を思い出していた。
「お爺ちゃん……。お陰で、助かったよ」
格納庫のマジンガーZを見上げ、兜甲児は亡き祖父に話し掛けていた。
「甲児君、君はどうするんだ? これから」
鉄也がそう尋ねると、甲児は笑みを浮かべて答えた。
「とりあえず、足りなくなった高校の単位の補習を受けて、卒業するまでには決めようと思ってる。せっかく、お爺ちゃんが残してくれた力だけど、今の俺には、いろんな意味で大き過ぎて……。戦いが終わった今じゃ、神にも悪魔にもなれる力なんてのは、俺には、でか過ぎるんだ」
「そうか……」
「こいつと――マジンガーとちゃんと向き合うには、いろいろ勉強する時間が必要だってことかな……」
あの時、もし再び〝新たなる敵〟が現れるようなことがあれば、兜甲児の日常を守り、自分が戦いの矢面に立つ――。剣鉄也はそう心に誓った。兜甲児は自らの意思で祖父・十蔵の遺産・マジンガーZを平和の盾として戦ったが、本来、彼は普通の青年であり、〝戦士〟としての生き方を強いられるべき存在ではない。鉄也は甲児の父・剣造と過ごした、甲児の知らない日々の中で、いかに剣造が父として、甲児や志郎の身を案じていたかを知っている。十蔵だけでなく、剣造までもがミケーネ帝国との戦いで亡くなった今、兜甲児の未来を守るのは自分の役目だと思っていた。
炎ジュンと通信を交わす光子力研究所の弓所長とさやかも、未確認物体の出現にミケーネ帝国との戦いを終えてから、この四年、見せたことのない緊張を浮かべた。
「わかった。鉄也君がこちらに向かっているんだな。2時間後にはグレートを稼働出来るよう、早速、調整を始めよう」
「ジュンさん、ありがとう。お陰で状況が掴めたわ。こっちは混乱してて、もう、何が何だか……」
陽はつるべ落としに陰り、無数のサーチライトとフォグランプが湖畔に並び湖面を照らし出した。
午後6時15分――千歳基地を経由して対策チームのメンバーを乗せた輸送ヘリ《CH-47》が観測センターのヘリポートに到着した。
事態を認知して、ほぼ4時間で危機管理マニュアルにある基本準備は整った。その間、湖底の未確認物体は一切の動きを見せず、まるで準備が整うのを待っているかのように静寂を保っていた。
輸送ヘリから降りた防衛省《MOD》の事務次官・鳴沢芳平は観測センターの会議室に歩みながら随行した広報担当の女性隊員に確認した。
「マスコミへの対応は?」
「第一報は廃棄衛星の残骸と思われる未確認スペース・デブリの確認・調査と発表しました。二時間後、通信社の代表取材を行うまではこのままで――」
「内閣府は?」
「閣僚の方々も揃い、通信会議システムも東京と繋がっています」
「国連軍《UNF》への対応は改めて内閣府を通して宇門所長と私が行う。状況を掌握するまでは国連にはオブザーバーとしての中継開示に留める」
「了解しました」
鳴沢は一度立ち止まり、声のトーンを落として尋ねた。
「それと――グレイス博士とは、連絡は付いたか?」
「まだです。フランスの御自宅にはいらっしゃらないようです」
「そうか……。きっと彼女が必要になる。見付け次第、すぐに、こちらに来るよう頼んでくれ」
「はい」
女性隊員は会議室の扉の前で敬礼し、鳴沢を見送った。
鳴沢が会議室に入ると、既に所長の宇門源蔵を始めとし、警察、消防、医療、近隣市政の代表からなる対策チームのメンバーが顔を揃えていた。
会議用大型ディスプレイには光子力研究所の弓弥之助、フォトン・アルファーの炎ジュン、東京の内閣府会議室、国連の広報局、それに、対岸の自衛隊本部が会議システムで繋がっている。ヘリで到着した幕僚組が腰を下ろした瞬間、湖面を映していたモニターに変化があった。
物体が沈んでいる辺りから、薄っすらと金色の発光が広がった。
「本部、湖面に向けているライトを消し、湖底からの発光を確認しろ――」
〝了解――〟
湖面を照らしていた照明が消えた。
原生の闇が取り巻く静寂の中、僅かに揺らぐ金色の光は、まるで、湖底の物体が発する言葉のように感じられた。
「――まるで、我々に話し掛けているかのようだ」
宇門所長がそう口にすると、会議室の面々がそれぞれに持ち込んだモバイルノートが一斉に話し始めた。
〝初めまして〟〝ハウ・ドゥー・ユー・ドゥー〟〝アンシャンテ〟〝チューツージエンミエン〟〝チョウムベケスンニダ〟
その音声は個々のモバイルに搭載されている音声インターフェイス機能を使い、対応可能な全ての言語で語り掛けた。
先手を取られた会議室の面々は動揺し、互いの顔と自分のモバイルを交互に眺めた。
〝驚かせて、すまない――〟
モバイルの人工音声は機械的な声で詫びた。
〝敵意はない。どうか、信じてもらいたい〟
会議室の全員が眉間に皺を寄せ、危惧と困惑の表情を浮かべた。
〝そちらの準備が宜しければ、代表者と直接お目に掛かって事情を説明したい――〟
テーブルの上のモバイルノートを覗き込むようにして鳴沢が話し掛けた。
「私は責任者を務める鳴沢という者だ。君は何者だ――? 異星人――なのか?」
〝混乱を避けるために、先ずは、そちらの代表者との会見を希望する――〟
「代表者を一人決め、その者と、じかに会って話すというのだな――?」
〝ええ――そう、お願いしたい〟
「私でいいのなら、話を聞くが――」
〝感謝します。しかし、出来れば代表者は、こちらに指定させて貰いたい――〟
鳴沢は一瞬考えたが、すぐに応えた。
「わかった。希望に沿えるよう計らおう。だが、こちらにも頼みがある。君が乗ってきた巨人は、我々にとって脅威にも見える。君が危険でないと理解するまで、絶対に動かさないと約束してくれ――」
〝承知した。こちらは私だけです。先ずは、私が外に出る。私を拘束し、貴公らの指定の場所に幽閉してくれ。私はそこで待とう〟
――貴公……? 幽閉……?
古めかしい言葉を使うものだと鳴沢は思った。
「恐らく、我々のパソコンに入っている翻訳機を経由しているせいでしょう。意味合い的には〝敵意〟のニュアンスは感じられません」
宇宙考古学者でもある宇門所長が感想を述べた。鳴沢はそれに頷いてから通信相手である〝異星人〟に応えた。
「わかった。こちらは手荒なことをするつもりはない。一刻も早く、正しく状況を把握したいだけだ――」
湖面に滲む淡い金色の光とだぶるように、直径3メートル程の眩しい光球が光の尾を引いて上昇した。それは、人魂かUFOのように重力を無視して何度かうねり、湖畔に設置された自衛隊本部の前へと静かに着地した。
光が収まると青年が立っていた。身に着けているのは体にぴったりとフィットした特殊素材の宇宙防護服のようだが、その上から宮廷装具を思わせる藍色のマントを羽織っていた。月明りに照らされたその姿は幻想的で、お伽噺に出て来る〝王子〟を想起させた。顔立ちも二十代の地球人にしか見えない。
月明りの王子は迎えに出た女性隊員にしっかりとした日本語でいった。
「突然、来訪し、混乱を生んでしまったことを謝罪する――」
気品のある青年だった。
〝異星人〟との肉声による初めてのコンタクトを果たしたのは鳴沢事務次官と一緒に居た、あの広報局の女性隊員だった。
「いえ……。気になさらず。あちらの建物にお連れします」
そう応えて対岸のGCR《摩周湖国際宇宙観測センター》に視線を送ると月明りの王子は頷いた。
「承知した」
「会見を希望する人物を教えて下さい。こちらに来るよう手配します」
「手数を掛ける」
地球人と同じ顔。誠実そうな表情だった。
それにしても、目の前の人物が事の流れ通りの〝異星人〟なら、その者が会見の相手に指定する人物とは、一体、どんな基準から導き出された相手なのか……。それとも、この〝異星人〟とその〝地球人〟は、何か特別な関わりがあるのだろうかと興味が膨らんだ。
月明りの王子は、まるで、まだ見ぬ友に思いを馳せるかのように、十三夜を描く美しい月を見上げた。
デューク・フリードは湖底で待機していた数時間のうちに、自身のパーソナルモバイルであるアストラルAI《守護妖精》のテュールと、この惑星での知的生命体との接触について検討した。
〝信頼の置ける協力者が必要です――〟
「ああ――そうだな」
〝遺物科学の上位データに、この時空の人物で、強くメモリーされている地球人が居ます――〟
「メモリー? 初めて来たのに記録されてるって、どういうことなんだ……?」
〝グレンダイザーのマルチバースメモリーです。グレンダイザーが異なるタイムラインを経由して、過去に別時空のこの惑星を訪れた形跡があるということです。詳細はエイルが居ないので不明ですが、その際に、この人物がデューク様と特別な関係にあったと考えられます〟
「私と――?」
〝はい――。但し、別の時空のタイムラインを経由したデューク様ですが――〟
デュークはコクピットのディスプレイに映し出された〝地球人〟を見た。
「まったく、記憶にないが――そういわれると、不思議に懐かしい感じもする……。悪い人間ではなさそうだ」
〝この時空のタイムラインではまだ逢って居ませんから、その感覚も致し方ありません〟
「つまり、証明は出来ないが遺物科学のメモリーが別時空での〝友〟である彼のことは信じられるといっている――そういうことなのか?」
〝はい――〟
初めての惑星でマリアやスペイザーとも未だ合流出来ず、どの道一人だった。
「わかった。彼に懸けてみよう」
そしてデュークは女性隊員にその名を告げた。
「名前は――兜甲児。兜甲児殿に会見を申し出る」
――兜…甲児……。
勿論、女性隊員もその人物がどんな人物か知っていた。天才科学者・兜十蔵の孫で米軍や自衛隊も叶わなかった〝ミケーネ帝国〟にマジンガーZで挑み、見事、人類を守った若者――。
――確か…戦いを終えた後、アメリカに留学したと聞いた記憶が……。
「その方なら、私も存じています。でも今は、たぶん、ここからは少し遠いところに居るので、連絡が付いても、こちらに来るには少し時間が掛かるかも」
そう言いながら、目の前の相手が何処から来たのだろうかと女性隊員は考えた。少なくとも、アメリカよりずっと遠い所から来たことだけは確かだった。
日本とアメリカのカリフォルニア州とでは16時間の時差がある。兜甲児は深夜の2時30分に日本の防衛省からの国際電話に叩き起こされた。
「はい…兜です。え? 誰に指名されたって……? 宇宙人って――?」
電話を終えて、何事かとやって来たワトソン博士と夫人に甲児が自分でも理解していない説明をしているうちに迎えの車が到着した。
「とにかく、行って来ます」
アメリカに駐在する防衛省のエージェントが用意した車にそのまま飛び乗り、ボブ・ホープ空港で日本政府のチャーター機《ボンバルディアCRJ》に乗り換え、電話から僅か1時間後には、甲児は機上の人となっていた。
「どういうことなんですか?」
自分の移送に携わる者たちも詳しく事態を把握していない様子だった。
甲児は少しでも正確な情報を得ようと、光子力研究所にホットラインを繋げると機内のTVモニターに弓さやかの顔が映し出された。
「さやかさん」
「甲児くん」
「いったい、北海道の観測センターで何が起こってるんだ?」
すると、モニターに映ったさやかの横から剣鉄也が顔を出した。
「甲児君、久しぶりだな」
「鉄也さん」
「宇宙からの落とし物だ。最初に遭遇したのは〝フォトン・アルファー〟の俺たちだ。奴は、突然ワープアウトして来た」
「ワープアウトって……?!」
百戦錬磨の兜甲児にも些か信じ難い話だった。
「未確認物体はマジンガーサイズの人型をしている」
「巨大ロボットなんですか?」
「動くかどうかは今のところ判らない。未確認物体は我々のGCR《摩周湖国際宇宙観測センター》を目指し、摩周湖に不時着した。万が一を考えて、俺も追い駆けて来たが……。乗員は〝異星人〟が一名。敵意はないと自分では言っているらしいが、地球に現れた事情など、詳細は混乱を避けるために、自分が指定する代表者一人と、先ず、話がしたい――そう希望しているそうだ」
「それが、何で、俺なんです?」
「ああ、そこも謎だ――。君とは話すと言っているから、直接、聞いてみるんだな」
「弓所長は?」
甲児の質問にさやかが割り込んで応えた。
「衛星通信でずっと会議中よ。異星人との未知との遭遇なんだから、そりゃーもう、世界中、大騒ぎよ……!」
「……わかったよ。こっちは直接観測センターに向かうから、もしもの時は、鉄也さん」
「ああ、分かってる。グレートなら、何処へでも、ひとっ飛びだ――」
GCR《摩周湖国際宇宙観測センター》に身柄を移されたデューク・フリードはリビングの三人掛けのソファーに腰を下ろしていた。部屋は家族用マンションの間取りで、普段は来客用の予備ルームに使われている場所だった。室内には湖畔で言葉を交わした女性隊員が一人、入口の外側には警備の自衛官が二人待機していた。
モバイルノートをチェックした女性隊員は月明りの王子に話し掛けた。
「こちらに向かったそうです。しかし、専用機でも10時間は掛かります。休まれて、横になってお待ちになっては如何です?」
「いや――迷惑を掛け、その上、人を呼びつけておいて自分が休むなど……。ここで待たせて貰えるだけで、感謝している」
折り目正しく、言葉にすればどこか滑稽に感じられる台詞をこともなげに返した。月明りの王子がいうと不思議に違和感が無かった。
――まるで、本当の王子様みたい……。
「名前をまだ、名乗っていなかった」
――え……?
女性隊員は不意を突かれた。
「……お名前も、兜さんがここにいらしてから仰るのかと思っていました」
「いや、タイミングを逃してしまっただけさ。緊張しているんだ。私にとっても、すべてが初めての経験だから――。礼儀を欠いて、すまなかった」
「いえ、そんな……」
「私の名はデューク。デューク・フリード。君の名前も教えて欲しい」
女性隊員は「はい」と頷いた。
「私の名前はひかる。自衛隊広報局・三尉の、牧葉ひかるです」
現地時間AM3時25分――凍える夜の闇の中、海と氷河と大地が揺れた。
南極大陸――ケイシー・ステーション。
オーストラリア基地の観測員たちは母国のオーストラリア大陸を臨む海底に異変が発生したことを確認した。
「マグネチュードは6.2。基地内の震度は4。震源地はここから北に凡そ800キロの海底。地震の規模は中地震だが震源地に近い観測システムが海流の変化を記録している。データを照合し、解析を急げ!」
それは、只の海底地震ではなかった。震源地の海底では人類が想像も及ばない凶事が起きていた。巨大な大穴が開き、地殻の狭間を抜けた地球の内部からそれは浮上した。
人工大陸デルパレス。面積にして6400ヘクタールの弩級の巨大円盤。それは地球の内部に異なる時空から転送された異物だった。
上部中央には水晶の結晶で出来たかのようなクリスタルパレスが聳え、裾に広がるにつれなだらかな尾根を描いた。それ自体が都市であり、それ自体が城だった。
「巨大な島が、浮き上がって来る!」
「いや…、これはもう、大陸サイズのプレートだ!」
それは氷河の海を下から突き破り、何億年も前からそこにあったかのように悠然と鎮座した。その出現により、一夜にして南極圏の地図は塗り替えられた。
中央に聳えるクリスタルパレスには地球の科学とは異なる進化を遂げた軍事的作戦指令室が設けられていた。
水晶の柱が幾重にも折り重なり、透明な寄木細工が空間を組み立てているかのようだった。作戦指令室にはヒューマノイド型、爬虫類型、昆虫型など、様々なタイプの型・属性の惑星人たちの姿があった。
光が透過する司令席にはデネブ星の皇太子・先遣帝ティラ・デルが着いていた。デネブ星の惑星人はヒューマノイド型巨人族の中でも最も美しいといわれる種族で、ティラ・デルはその中に於いても群を抜く美しさだった。
「テラ星の地上人《アウザー》への干渉を始める――。アガルタの使徒・炎のエルディル、疾風のケニング。そなたらに名誉ある一番槍を競わせよう。存分に――名を上げよ」
人工大陸デルパレスから巨神獣のエルディルとケニングが天使のような翼を広げ、オーロラの揺らぐ空に飛び上がった。
巨神獣とは機械の〝器〟にベガ星連合の傘下の惑星人たちの〝魂〟を転位させた戦闘兵器で華々しい戦果を上げた兵士のみが元の肉体に戻り、階級を上げ、新たなる統率者となる栄誉を約束されていた。
恐星大王ベガール・ベガⅢ世の懐刀である軍将ダントスが科学長官ズリルの推し進める〝アガルタ計画〟に基づき新たに組み立てた新参者の惑星人たちを服従させるための掟だった。
二体の巨神獣は海上を北北東に飛びタスマニア島に上陸し、歴史と近代建築が融合した美しさで知られる港湾都市ホバートを襲った。
高層ビルの谷間で巨神獣エルディルが叫び、炎を撒き散らす。海に面した斜面に密集した近代ホテル群が火の海に包まれる。巨神獣ケニングが腕に仕込まれた水晶の刃を振るうと、切断された高層ビルが達磨落としのように崩れ去った。
海底地震を認知した時点で防衛軍は動き出した。把握と迎撃のためのスクランブルがオーストラリアの全ての基地で即座に掛かった。
だが、王立オーストラリア国防軍の誇る戦闘機スーパーホーネットも自国内で起こった未知の巨大ロボットの破壊活動には対応策がなかった。攻撃すれば一定の成果は得られても、自国の都市を自ら破壊するのと同じだった。被害を最小限に留め、超局所戦に持ち込むことが出来るのは、敵の戦闘スタイルと同じ目線を持つスーパーロボットだけだった。
「スクランブルッ、ダーッシュ!!!」
南極圏での海底地震の発生を知った剣鉄也は戦士の勘で飛び立っていた。マッハ4(時速4,320km/h)で飛行可能なグレートマジンガーでも2時間かかる。迷っている場合ではなかった。
突如、南極海に浮上した謎の巨大島。そこから現れた二体の巨大ロボットがオーストラリアのタスマニア島に上陸して破壊活動を始めたニュースはすぐに世界を駆け巡り、当然のように、このタイミングで北海道に現れた〝異星人〟であるデュークに疑いの目が向けられた。
部屋の外に待機していた自衛官の数が増え、神妙な面持ちで鳴沢が入って来た。
デュークは鳴沢の表情から事態の変化を読み取った。
「何か、起きたのですね?」
「未知の巨大ロボットが現れ、破壊活動を始めた。不躾だが、もし心当たりがあれば、教えて欲しい――」
デュークは静かに尋ねた。
「声明はあったのですか?」
「いや、何もない。分かっているのは、地球の底から、突然、浮上して来た〝勢力〟に属す、と、いうことだけだ」
「地球の底から……?」
デュークは想像出来得るあらゆる可能性を考えた。
「私に関係することで、もし、あるとすれば、私を追って来た〝追跡者〟という可能性ですが、その可能性は今のところ、限りなくゼロに近いものです」
「君は…、追われているのかね?」
思わず質問を重ねた鳴沢は、目の前の〝異星人〟との約束を思い出し、「いや、すまない」と詫びた。会見は兜甲児に委任する。現状が如何なる突発的事態であるにせよ、その約束には初めて接近遭遇を果たした〝地球人〟としての〝信用〟が懸かっている。
だが、兜甲児が到着するまでには、まだ、8時間以上を要した。現地の被害を考えれば、今の対応が地球の未来を変えることにも成り兼ねない。
「宜しいですか」
牧葉ひかるが気を使いながら発言した。
「ん、ああ」
「衛星通信は機上の兜さんとも繋がります。直接会見ではなく、通信会見にお切り替えになっては如何でしょう」
見事な折衷案だった。
デュークも同意し、観測センターの中枢であるGCRに場所は移された。
通信会見に同席するのは鳴沢芳平、牧葉ひかる、宇門源蔵の三名に絞られた。
フォトン・アルファーと交信する管制設備の中央にシートを設け、そこにデュークが座り、正面の壁の大型モニターに兜甲児の姿が映し出された。
「兜甲児だ」
「デューク・フリード」
二人は自分の名前を互いに名乗った。
第3回 アガルタ 完
【グレンダイザーINFINITISM】
第3回 アガルタ
【マジンカイザーINFINITISM】
【ゲッタードラゴンINFINITISM】
【鋼鉄ジークINFINITISM】
新たなる「INFINITISM」
【マジンガーZERO INFINITISM】
第5回 永劫因果 (終)
©ダイナミック企画・東映アニメーション