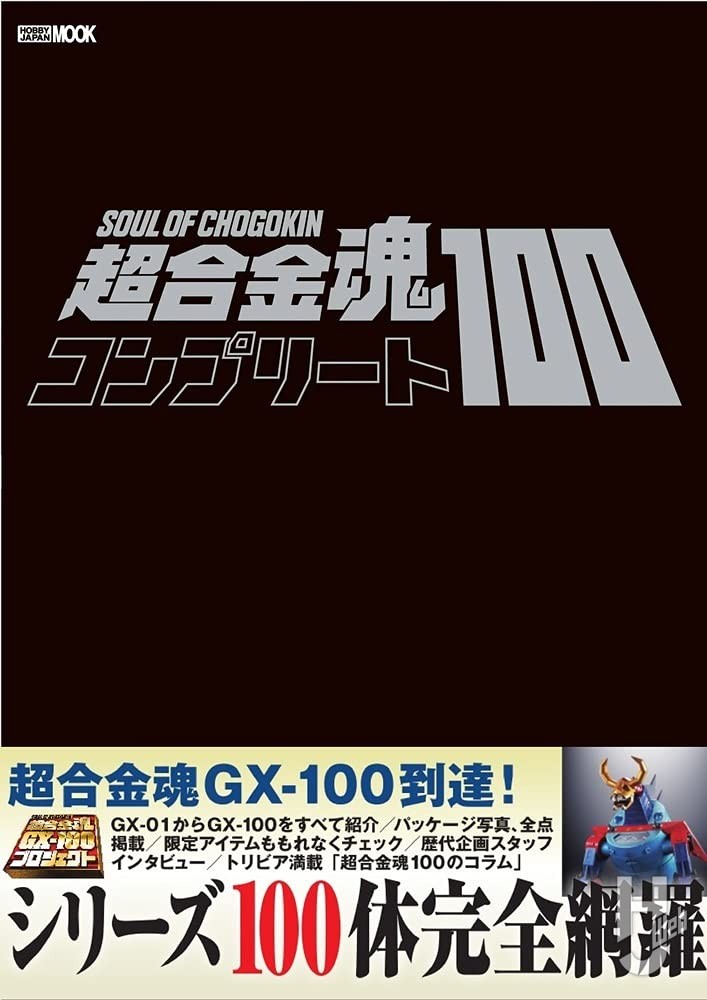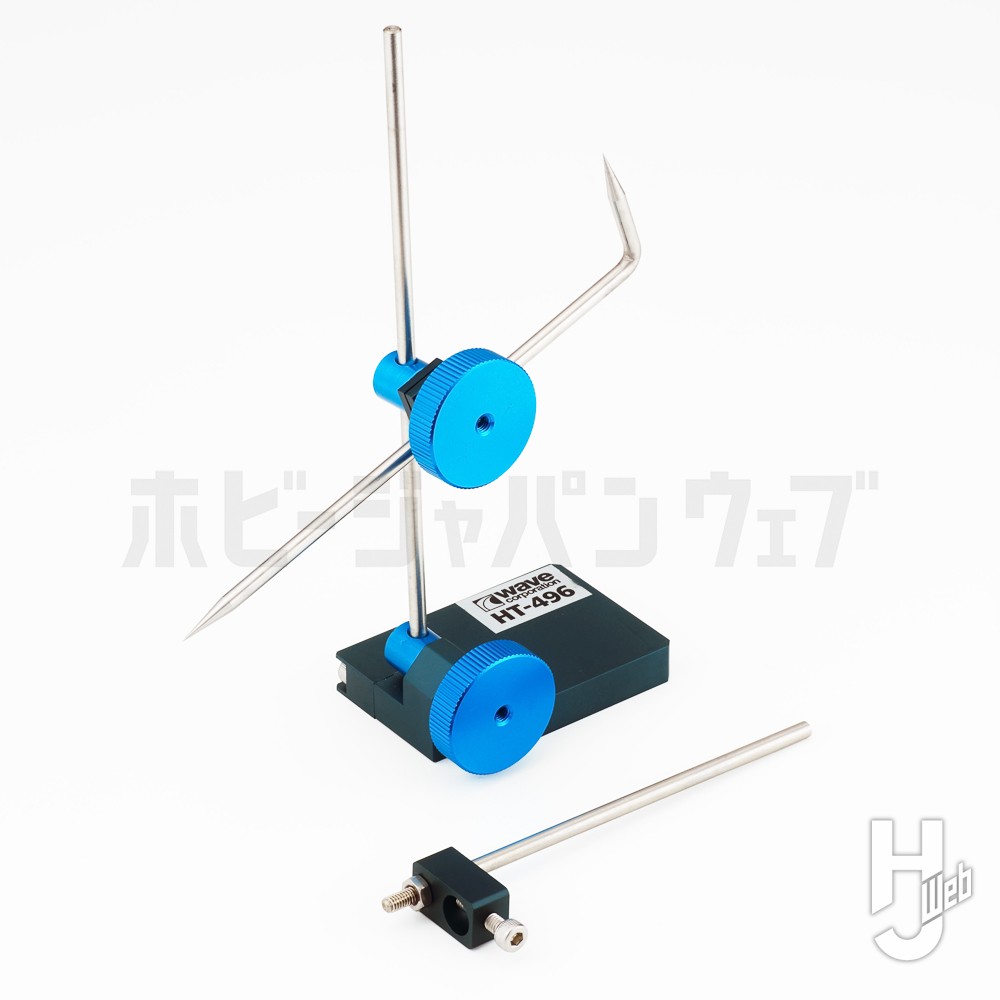スーパーロボットINFINITISM 月刊ホビージャパン2020年9月号(7月25日発売)

ダイナミック企画×BANDAI SPIRITS ホビー事業部×月刊ホビージャパンで贈るフォトストーリー『INFINITISM』。『グレンダイザー』編、『マジンカイザー』編に続くシリーズ第3弾は『ゲッタードラゴン』編。まずは次回本格連載開始を前にプロローグをお届けしよう。いまゲッターロボGの新たなエピソードの幕は上がる!
原作・企画
ダイナミック企画
ストーリー
早川 正
メカニックデザイン
柳瀬敬之
協力
BANDAI SPIRITS ホビー事業部
ホビージャパン
PROLOGUE
人類は傲慢だったのか――?
「地上の人類よ、貴様らは、断じて地球の支配者などではない……!」
恐竜帝国の帝王ゴールは最期にそう言い放った。
あの戦いの結末から始まった百鬼帝国との戦い――!! 猛攻の果て戦場に散った武蔵。
辛勝の先に現れた新たなる敵に立ち向かうため、生まれるべくして生まれたその姿――。
だが、〝ゲッターロボG〟の雄姿にはそれ以上の存在理由が隠されていた。
爬虫人類との戦いの影で密かに暗躍を始めていた百鬼帝国の魔の手。
その正体さえ認知されず、第四の勢力として地球に介入を始める謎の蟲軍たち――。
後に、全ての宇宙から〝赤壁の鬼神〟〝聖なるドラゴン〟と畏れられた〝ゲッターロボG〟は如何にして誕生し、最初の形を得たのか――?!
遥かなる未知の力〝ゲッター線〟に翻弄されながらも進化と成長を続ける宇宙――。
その特異点の中心に隠されていたメッセージが、今、解き明かされようとしている。
▼ ▼ ▼
それは――恐竜帝国《爬虫人類》が地上に姿を現す五年程前のこと。
世界中の人々が自由に利用する衛星MAP。
それに映る、とあるポイントの不可思議な映像を検証するために探検隊が編成された。探検隊の目的は氷に閉ざされた南極の奥地に映る宇宙人の円盤としか思えない巨大で黒い円形の影の確認だった。
そもそもがイギリスのTV局による都市伝説の検証番組で、地球物理学や宇宙考古学、動物分類学、軍事史研究家、気象の専門家から宗教学者、果ては自称UFO研究家まで各部門の専門家と呼ばれる顔ぶれをクルーやスタジオゲストに揃えていたが、当然ながら初めからそれが宇宙人の円盤だと本気で思っている者など誰もおらず、自然の神秘でそのように見えていたというオチを彼らのコメントで神秘的に綴ろうというネイチャリングスペシャル企画でしかなかった。
撮影は探検隊の移動に合わせ、部分的にスタジオとのライブ通信を織り交ぜながら進行し、編集して完成する手順で進められた。
現地で行動する探検隊は撮影スタッフが二十名、カメラに映るリポート部分を進行させるための隊長役の俳優が一名、体力自慢で知られるタレント隊員が三名、現地で直接調査する識者として各部門から七名の学者が同行した。それ以外にも荷運びのポーター隊と食事係、それぞれの学者に随伴する助手たちを含めれば総勢五十名に及ぶ大クルーだった。
探検隊はアメリカのマクマード基地を経由して定員十名の大型雪上車五台に分乗し、三日をかけて映像のポイントを目指した。
最後尾の雪上車にはカメラに映ることのない者たちが押し込められていた。荷運びたちだ。その屈強なポーターたちに混じり、背丈はあるが気弱そうな男が、狭い車内の壁に背中を付け、腰を丸めて静かに座っていた。
「ドレフェス博士、もっと楽にしてくれていいんだぜ」
「かまわんよ、私はこれで十分だ」
声を掛けたのはポーターの頭を務めるマイケルだった。期間は短いがこの濃厚な旅で、ドレフェスとマイケルは裏方仲間として奇妙な絆を築きかけていた。
才能はあるが伝統的な学閥に入りそこね、いつまでも助手に甘んじ、梲が上がらない考古学者のドレフェス。
マイケルはリュック一つで故郷のアメリカを飛び出し、自由を体現することを信条に世界を巡って来たが、いつの間にか知らない土地で日銭稼ぎのポーターとして縛られている自分に気づき、密かに苛立ちを感じていた。荷運びの頭としての仕事に生き甲斐を感じないこともなかったが、何かが違う、そう何処かで思っていた。
雪上車のコンボイは無限軌道で銀粒の氷霞を振り撒きながら永久凍土の大地を疾走した。
氷原に出て三日目の昼――。最後尾の雪上車が軽いエンジントラブルを起こし、修理のために停止してコンボイから離れた。
最後尾が遅れたところで撮影には支障なく、四台はそのままポイントに向けて走行を続けた。
「もうすぐ到着なのに、ついてないな……。私の人生の、運の悪いところがまた顔を出してしまったか……。まあ、いつものことだが……」
ドレフェスは力なく自嘲した。
「ディーゼルのプラグを交換するだけだ。二時間で追い着く」
マイケルはドレフェスの肩を軽く叩き、力づけるようにいった。
果たして――不運だったのか幸運だったのか――?
その二時間が、彼らの運命の大きな分かれ道となった。
ドレフェスらが乗る雪上車が遅れてポイントに到着すると、先に到着していた四台の扉が開け放たれており、その周囲には銃で撃ち合い、殺し合ったと思われる隊員やクルーたちの死体が散乱していた。
「これはッ……?!」
ドレフェスはその光景を見て、じわじわと呼吸が苦しくなった。目の前の事実が理解出来ず、経緯も想像出来ない。途端に吐き気がし、嘔吐し、自分の吐瀉物に顔を埋めるように粉氷の山に倒れ込んだ。
マイケルは情報を得るために生きている者を探した。三人目に確認したタレントの隊員が虫の息で答えた。
近くで死んでいる軍事史研究家を震える指で差し、
「本物だった……。奴が、アレが本物だったから、絶対に明らかにはしてはならないと……! 突然、クルーを……! 撃ち合いになった。訳が分からなくなって……」
隊員は息を引き取った。
「本物って……?」
マイケルはゆっくりと立ち上がり、足元を見下ろした。足元の氷原の下には、巨大で黒い円形の影が不気味に広がっていた。
「なんてこった……!?」
軍でも警察でも、何でもいい。一刻も早く公的機関にこの事態を報せ、自分たちも安全なところに身を寄せなければ……と、マイケルは思った。
「ボルマン、レイモンド、カーバイン……。どれも学閥に守られ、才能以上の地位に恵まれて来た無能たちだ――」
いつの間にか立ち上がったドレフェスは、血塗れの死体となった知人の科学者たちの顔を一つずつ確認しながら、マイケルに歩み寄った。
ドレフェスの気配が変わったのをマイケルは本能で察した。巨体を縮め、物陰で静かにしているだけの、只の気の優しい末席の学者だとばかり思われていたドレフェスが、人が変わったかのように語り始めた。
「その隊員のいったことが本当なら、生き残った私たちが連絡を付けようとすれば敵の思うツボだ――。撃ち合った様子を見れば、準備をしていたのが一人ではなかったのは明らかだ。どんな組織かは分からないが、必ず、追っ手が現れ、私たちは口封じのために殺されるだろう。恐らく、氷の下に眠るこの遺物には、それだけの価値がある――!」
「ドレフェス博士――?!」
普段は自虐の枷のため、ほとんど黙っているので気付かれはしないが、ドレフェスの状況把握能力は人並み外れていた。そして、それに加え、長年科学者として鍛えられ、備わった論理的思考が拍車を掛け、彼の脳には時折、閃光のように〝未来〟が見えた。それは一言でいえば、不世出の天才と狂気だった。
状況と才能が上手く機能すれば心強いが、場合によっては独裁的指導者に自らを成長させる危険性をも孕んでいた。
ドレフェスとマイケル。それに八人のポーターはもう一度手分けして生き残りを探した。先行した雪上車に乗っていた者で生き残っていたのは、雪上車の中で息を殺して震えていたロボット工学の助教のグラディウスだけだった。
ドレフェスは氷原の下に眠るその物体を睨みながら力強くいった。
「連絡も出来ず、人が居る場所に戻ることも出来ない。この状況では、日が落ちれば車の中で一晩を持ち堪えられるかも怪しい。私たちが生き残る手段は唯一つだ。この未知なるものに身を委ね、これまでの全てを捨て去り、生まれ変わること――! 今、この瞬間の選択こそが、神が与えたもうた奇跡かも知れない――!」
幼い頃から学者に成ることを夢見て人並み以上に勉学に励みながらも、全ての運から見放され、雪辱に甘んじて来た人生――。その反動は予期せぬ非常時の到来に尋常ならざる狂気さを増して彼の中の何かを揺り戻した。
マイケル、グラディウス、荷運びのポーターたちは南極の氷原で誓いを立てた。
「ブライアン・ドレフェス博士。ブライよ、俺たちは、貴方に運命を賭けてみる……!」
PROLOGUE 完
【グレンダイザーINFINITISM】
【マジンカイザーINFINITISM】
【ゲッタードラゴンINFINITISM】
PROLOGUE
【鋼鉄ジークINFINITISM】
新たなる「INFINITISM」
【マジンガーZERO INFINITISM】
第5回 永劫因果 (終)
©ダイナミック企画・東映アニメーション