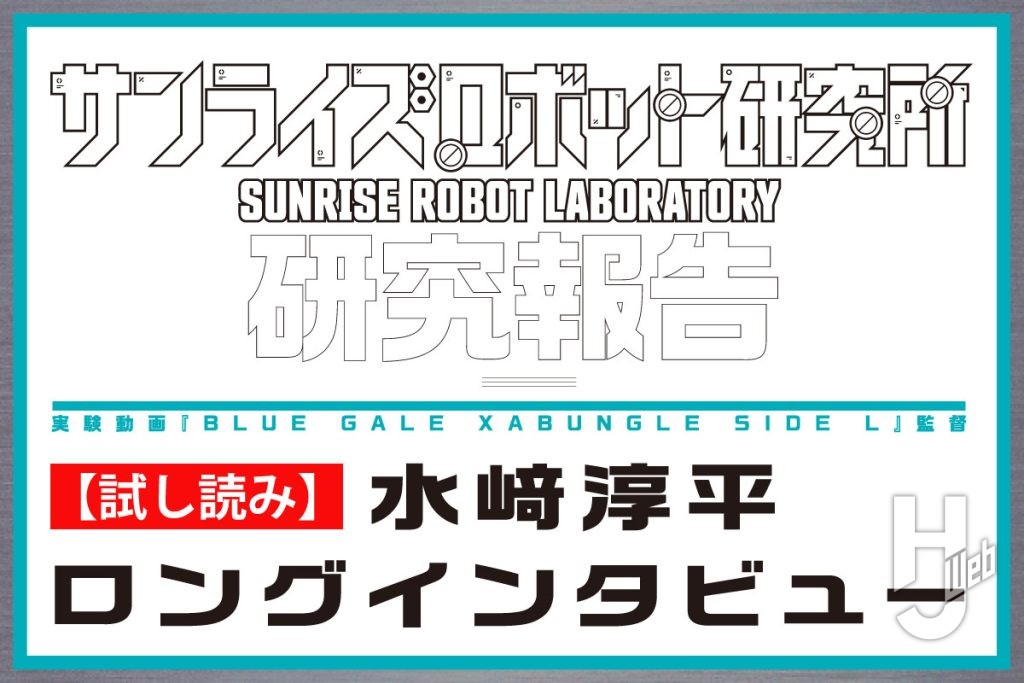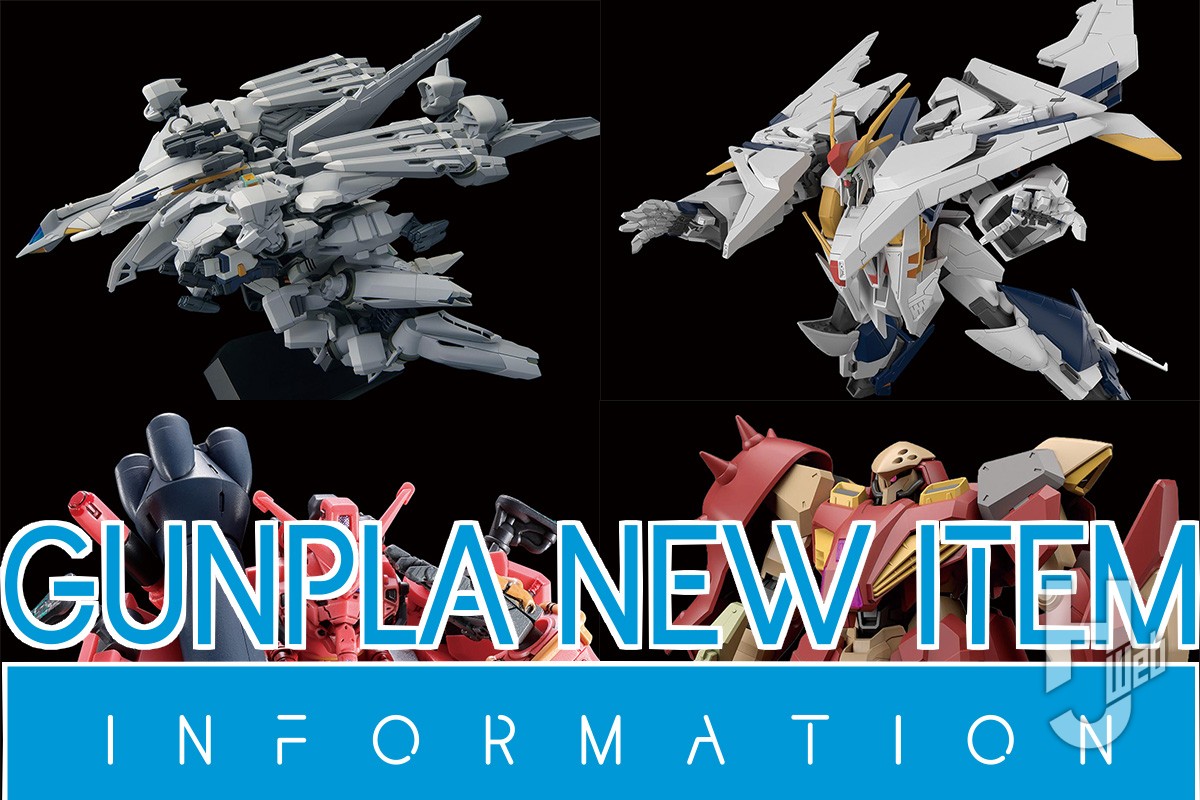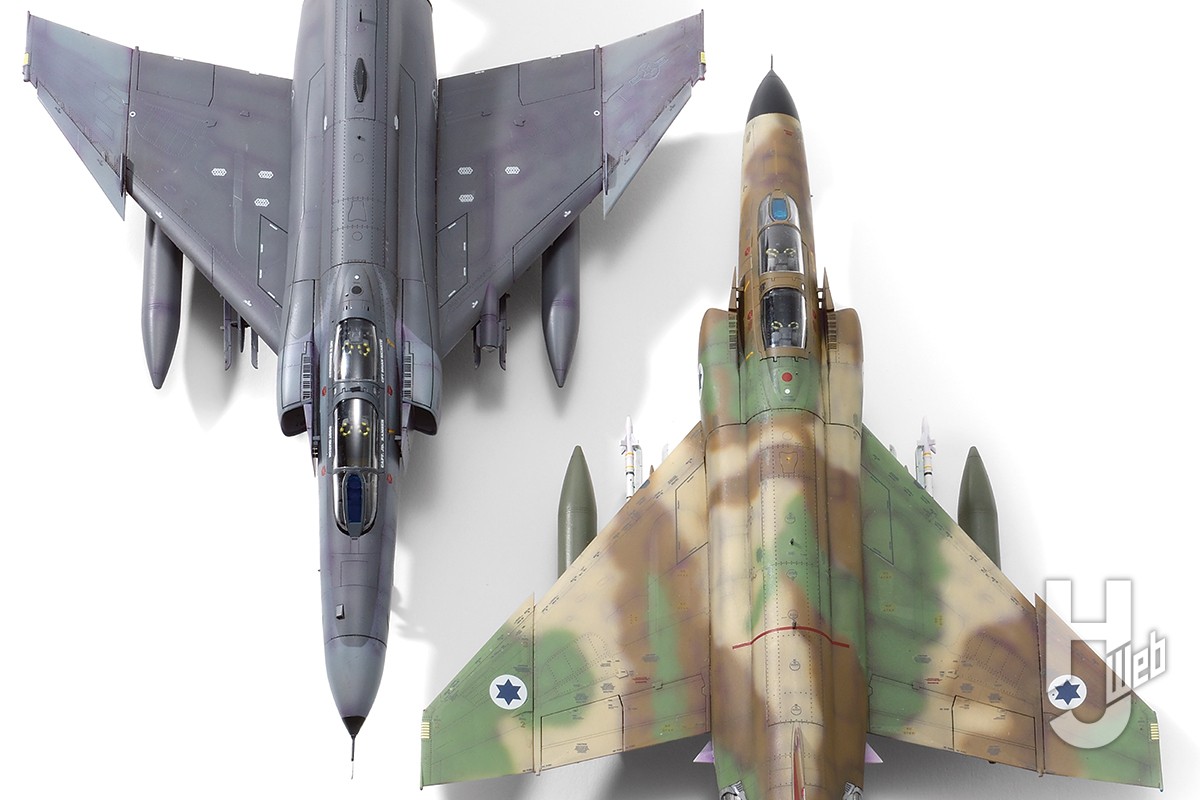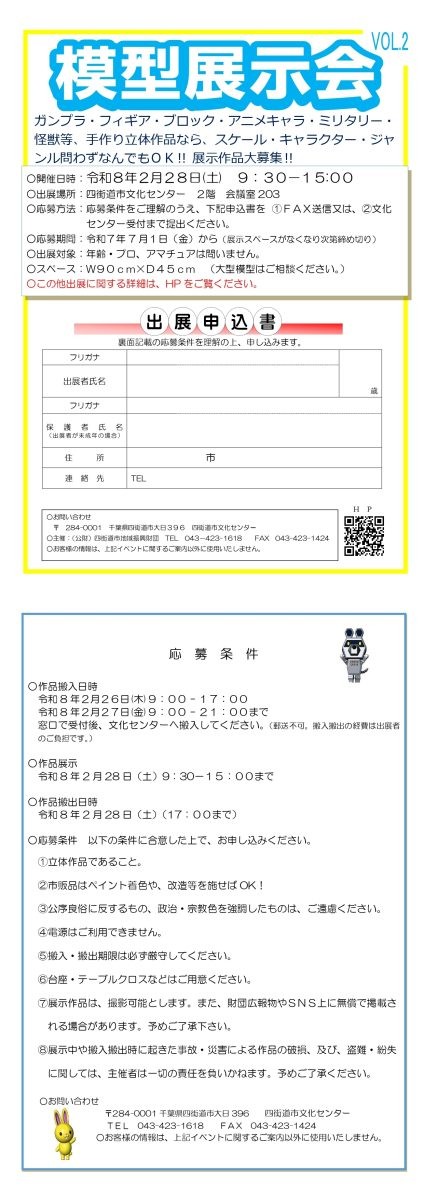【試し読み】『BLUE GALE XABUNGLE SIDE L』監督の水﨑淳平氏に『戦闘メカ ザブングル』との出会いや制作裏話をインタビュー【月刊ホビージャパン8月号より抜粋】
2025.07.06今回は『BLUE GALE XABUNGLE SIDE L』の水﨑監督に、実験動画のメイキングにフォーカスした内容をお尋ねした。『SIDE L』への思い、そして『SIDE R』はどのような作品なのか、ぜひご一読を乞う。
(取材/五十嵐浩司(TARKUS))
『SIDE L』は子供の頃にワクワクして見ていた感覚を頼りに作りました
子供の頃はウォーカーマシンのプラモデルに夢中でした
――水﨑監督と『戦闘メカ ザブングル』との出会いからお願いします。
水﨑:『ザブングル』の放送が始まった頃は、自分がちょうどプラモデルを作り始める年齢になっていた頃にも重なっていまして、バンダイ模型の「ウォーカーマシンシリーズ」(※1)に夢中になっていたんですよ。最初に買ったのは今でも覚えていますが1/100のギャロップ・タイプでした。部品が細かくて組み立てそのものが面白かったですし、アニメのメカではありますが、スケールモデルに寄せた商品でしたからドラム缶や荷物などが付属していて、それがまた楽しさを盛り上げてくれたんです。他のウォーカーマシンだとカプリコ・タイプが好きでしたね。劇中で雪原をスキーで滑っていく場面が記憶に残っています。
入口がギャロップ・タイプということもあったのか、ザブングルよりも周りのウォーカーマシンのほうが好きでしたね。そういったメカどうしのサイズ差に魅力を感じていたので、実験動画にテーマのひとつとして、ウォーカーマシン間でのサイズ比を盛り込んでいます。
(※1)1982年から1983年にかけてバンダイ模型(現:BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン)より発売されたプラモデルシリーズ。あえて番組名ではなく、登場メカである「ウォーカーマシン」をタイトルに使用していた。1/100、1/144、1/1000(アイアン・ギアーのみ)、1/48(ホバギーのみ)と4つのスケールが存在し、特にフラッグシップの1/100スケールはクリアーパーツやポリキャップを多用したハイエンドモデルであった。また、プラモデル用に「リアルタイプイラスト」としてデザイン画を新たに起こし、それに基づいて設計を行ったことも含め、非常に先鋭的なコンセプトで作られている。
――最近も「ウォーカーマシンシリーズ」を作られましたか?
水﨑:今回の映像制作にあたって1/100のギャロップ・タイプやトラッド11・タイプ、カプリコ・タイプを新たに作ったんですよ。他にも再販された1/144サイズのセットですとか。1/144は手軽に作れるのがいいんですよね。自分の父も『ザブングル』のプラモデルが好きだったことを思い出したりして、感慨深い思いのなかで実験動画に取り組みました。
『ザブングル』のユーモアに寄せた作風を活かしています
―それでは『BLUE GALE XABUNGLE SIDE L』のお話に入ります。制作スタート時にはどのようなことを検討されていましたか?
水﨑:制作当初の段階で検討したのは、人物キャラクターに声を入れるかどうかということでした。オリジナル映像に出演した声優さんが引退されていたり、亡くなっている方もいらっしゃるので、声を入れない方向性も検討していたんです。それで最終的に、銀河万丈さんのナレーションだけはぜひとも欲しかったので入れさせていただきました。このナレーションで、『ザブングル』の世界観を保つことができて本当によかったと思います。また、人物キャラクターの声をあえて入れなかったことで、ウォーカーマシンのアクションシーンに没入していただくことができたのではないでしょうか。“サンライズロボット研究所”とは、そもそもメカニックの魅力を掘り下げる取り組みですから、結果的によかったと考えています。
――実験動画には『ザブングル』の面白さやユーモアがすごく凝縮されていましたね。
水﨑:『ザブングル』の作風がユーモアに寄せていたことが、小学校低学年の自分にとても響いたんですよ。子供にもわかりやすくて楽しめました。シリーズ後半になってくると、敵であるはずのティンプ・シャローンのギャグ描写があって、葉巻の吸い殻を鼻に付けたりとかね。「この人、敵じゃなかったっけ?」と不思議な感覚で観ていました(笑)。そんなふうに当時から『ザブングル』には楽しい印象がありましたから、実験動画のウォーカーマシンの演出にもオリジナル作品で見られたコミカルな動きを反映させています。
――確かにオリジナル作品でも人が乗っている機械というよりは人物キャラクターのように描かれていましたね。
水﨑:操縦者がわざとコミカルに操縦をしているわけではなく、搭乗者の感情をウォーカーマシンで演出していたのではないだろうかと思い、そこを拾わせていただきました。
――変形完了後にザブングルの頭がなかなか出ない演出も本編から拾われたものですね。
水﨑:実験動画で頭の出てこないシーンは第12話でダイクとチルが乗ったザブングルの頭が出てこないシーンがモチーフです。実験動画ではチルがザブングルに乗っているということで入れていますね。
――合体直後のザブングルが上半身を変形させながら走ったり、タイトルバックもオリジナル作品のジロンではなくザブングルだったりと、ザブングルの活躍が印象に残りますね。
水﨑:ウォーカーギャリアもザブングルと同じくらい活躍させたかったんですが、予算や制作期間などの都合もあり、今回はメインタイトルになっているザブングルにフォーカスを当てさせてもらいました。改めて見ると、ウォーカーギャリアのほうが『ザブングル』の世界観に合わせたデザインですね。
――リアルタイムで観た時は、ヒーロー的なザブングルが他のウォーカーマシンのなかで浮いていると思われましたか?
水﨑:『無敵超人ザンボット3』や『無敵鋼人ダイターン3』、『機動戦士ガンダム』の流れがありますから、ヒロイックなスタイルのロボットが出てくるのはむしろ当然と思っていました。だからザブングルよりも周りのダッガー・タイプやカプリコ・タイプなどのウォーカーマシンのほうに違和感があり、逆にザブングルが浮いているようには思っていなかったですね。でも今見ると、そういう異質感がよりロボットとしてのキャラを立たせていたのかな、と。色も他のウォーカーマシンと違いますからね。ボディに塗るための青いペンキを調達するのは大変だろうな、なんて思います(笑)。
・
・
・
■メカの汚しでザブングル独特の世界を表現しました
■アイアン・ギアの変形はあえてアーム移動を選びました
■ハッピーエンドがザブングルのアイデンティティー
■若い世代に向けた展開を『SIDE R』では試みたい
■新たに描き起こされたザブングルたち
続きは「月刊ホビージャパン2025年8月号」に掲載!
▼ 関連記事はこちら
ⓒSOTSU・SUNRISE