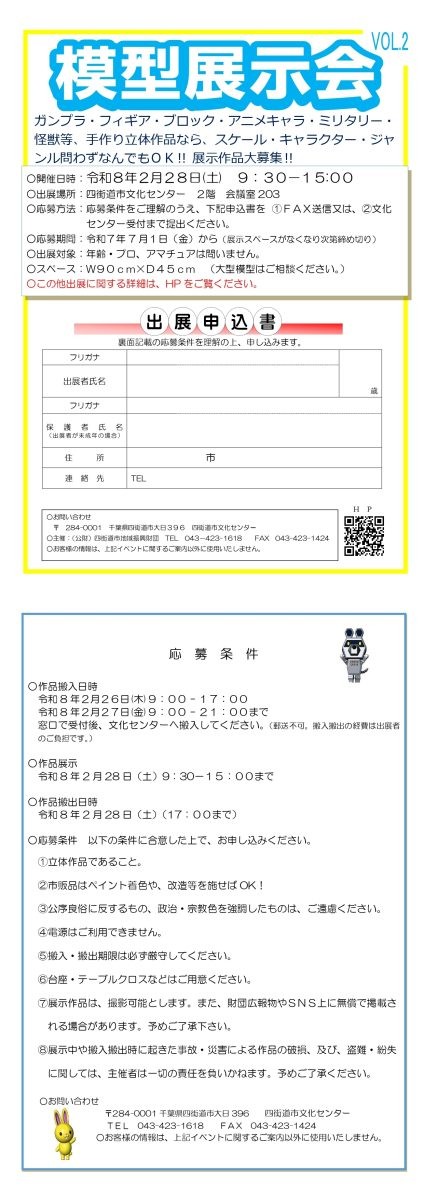メーカー×モデラーエアブラシ放談 月刊ホビージャパン2025年5月号(3月25日発売)
プロにはありがたい、
高圧・高濃度の塗装
コ そういう、新しいものへの反発みたいなところでいうと、2020年頃に「高圧で濃い塗料を吹いたら一発で発色する」ということを推した時の、「低圧で薄い塗料をじわじわ吹く派」からの反発ってけっこうあったんですよ。
矢 昔だったら塗装ブースもなくて、エアブラシも低圧のものしかなくて、さらに塗料の選択肢も少なかったから、薄い塗料を何度も吹き付けるしかなかったんですよね。だからそういうやり方になった、というのはわかるんです。
コ わかります。ただ、なかなか難しいのが、塗料や道具のアップデートを無視して、流儀だけが前に出てくるとおかしなことになるんですよね。今まで自分が費やしてきた手間や時間が無駄になる気がするっていうのも、わからなくはないんですけど。
け 模型の作り方ってそれこそ「一人一流派」みたいなところがありますからねえ。僕は自分のことを「締切派」と名乗ってるんですが、高圧・高濃度で一発で発色させるやり方って、締切派からするとありがたいんですよ。何日までに納品しなくちゃいけないっていうスケジュールから逆算する作り方をしていると、何度も塗り重ねなくて済むほうがいいに決まってるんで。じっくりやりたい人は10回塗り重ねたっていいんですけどね。
R 手間をかけることが満足につながるなら、それで全然いいんですよ。
ガールズプラモの隆盛は
エアブラシの重要度を上げた
け あと近年のエアブラシに関する話題というと、この10年でガールズプラモというジャンルが大きく盛り上がって、完全に定着したということがありますよね。このジャンルって、パール塗料とか偏光塗料とものすごく相性がいいんですよ。
コ あんまり細かいこと言われないしね。
け そうそう。あとは巨大感とかも表現しなくていいし。やっぱり1/100とか1/144のロボットのプラモデルって、スケール感を意識して塗らないとダメなんだっていう精神的な縛りがあるじゃないですか。それに比べると、ガールズプラモってどんなスケールでも全然不自然じゃない。
矢 うちの商品もかなりそのジャンルに助けられている部分はありますね。
け で、ガールズプラモって自分好みにカスタマイズするには髪の毛を塗る必要があるじゃないですか。この髪の毛の塗装とエアブラシというのが、めちゃくちゃ相性が良いんですよ。
コ ああ~、グラデーションが必須だからね。
け それこそ今って、Vtuberとかでものすごい髪の色をしてる方がたくさんいるんですよね。金髪なんだけど末端は緑とか、ピンクで始まって水色で終わるとか、インナーだけ違う色が入ってるとか。そういうものからインスピレーションを得て、模型でもこれを表現しようと思うと、エアブラシ無しでは難しいんですよ。パール塗装にしても偏光塗料にしても、やっぱりエアブラシ無しでは難しい。こういうものが流行っている状況なので、「エアブラシを始めてみようぜ」って言いやすいと思ってます。
コ ある意味、ものすごく自由なジャンルですからね。
け そうそう。こういうガールズプラモにしてもそうですけど、エアブラシって何が一番面白いかって、「対象物を簡単に自分の好きな色に塗れる」っていうところだと思うんですよ。自分が思った色でパッと塗れて、自分のものになるっていう。筆塗りでも塗装はできますけど、時間がかかるぶん塗ってるうちに我に返っちゃうところがあるじゃないですか。「これがやりたかったんだっけ?」みたいな。
コ 筆の難しいところって、同じ筆を使ってもタッチがそれぞれ人によって違うから、再現性が低いことなんですよね。上手くいく人といかない人が出てくる。でも、エアブラシってセッティングが共通だったら同じ結果が出るはずのツールなんですよ。
矢 ただ、著名なモデラーさんのエアブラシ作例を見ると、やっぱり他とは違う出来になるわけじゃないですか。だからやっぱり、エアブラシもひとつの道具として、自分がどういうものを作りたいかしっかり思い描いて、そこからどんな塗り方をするか取捨選択してもらうといいのかもとは思います。
R そこは一番大事なところですよね。自分の中に「こういうものが作りたい」というものがないと、どんな技法や道具が必要なのかもわからないですから。
成功体験があれば、
エアブラシは怖くない
コ それを判断するにしても、エアブラシは楽なんだと思うんですよ。「この組み合わせでこの塗料をこう吹けば、この結果に近いところまではいける」っていうのがわかりやすいので。安心材料にはなりますよね。
け 我々はあんまり使いたくない言葉ですけど、「正解」というのが決まってるっていうことですよね。
コ 特に模型作りに慣れていない方に顕著ですけど、基準を知りたいという需要があるんですよね。「いや、そこはもう経験ですよ」と言いたくなるような部分でも、「具体的に何対何の比率で割ればいいんですか?」みたいな質問があったりする。
矢 そこに関しては、先ほども言いましたけど自分は「塗料と溶剤を1:1で混ぜてください」と言うようにしています。それで光沢が出なかったら、溶剤を加えてください、というのが基本の回答ですね。
け エアブラシでも「正解」のレンジが狭い道具はあって、例えば吸い上げ式のハンドピースとか。あれは塗料が濃すぎると絶対に出てこないから、吹ける最低条件を満たすのが難しい。それで上手くいかなくてイヤになっちゃった、という人もいるんじゃないかな。
R 特にエアブラシに関しては、そういう人が多いと思います。もうちょっと知識や経験があればいけたのに、「自分には向いてない」って思っちゃったパターンというか。そこをもうひと頑張りして上手くいったらそれが成功体験になって、もう一生ハマる趣味になると思うんですけどね。
け 自分なりの工夫が上手くいった瞬間の良さといったら、格別ですからね。
R でもメーカーとしては「これならまず絶対失敗しないです」という基準というか、この設定なら普通に塗れます、という基準をポンと置いておいたら、いろんなところで迷走した人が模型をやめなくて済むんじゃないかと思うんですよ。みんなレシピが欲しいんですよね。「解凍」とか「飲み物」とかを選べる電子レンジのおまかせ設定みたいな、「カーモデルをツヤツヤに塗りたい」なら、じゃあコンプレッサーを3番の設定しよう、くらいまで簡単にできる機械があればいいんですけどね。
コ 匙加減みたいな部分はできるだけなくして、ロジカルに詰めればうまくいく、というのが理想だと思うんですけどねえ。これは難しいかな……。
次ページ──手軽なステップアップ