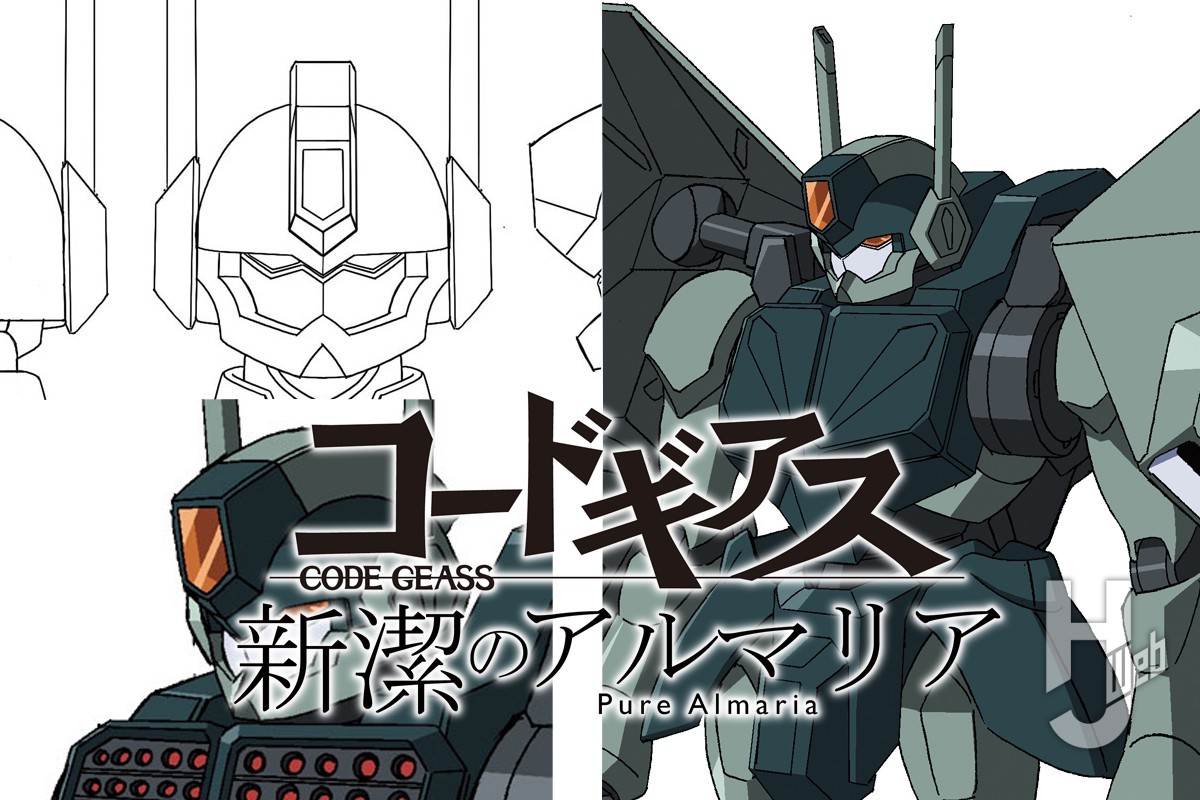【最終回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.11.10マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
終章
眠っていて、ベッドから落ちて目覚めるという経験は無い。
だけど、電車で居眠りをしていて、突然体がビクリとなって飛び起きるということはよくある。
今の感じは両者の中間あたりだろうか。
だが直後、おれは全身が粉々になるような衝撃で意識を取り戻した。
これではベッドから落ちるよりひどい。
すぐ、背中に第二の衝撃。何かが降って来た。手で払いのけると、大小の建材らしき物がバラバラと体から落ちた。
横に転がってから上体を起こす。体が何かで覆われているのがわかった。痛みはほとんど無い。ショックだけが残っている。
次の瞬間、おれはすべての記憶を取り戻した。
処理施設を破壊し、S.A.T.O.ごと多摩川の〝時空の裂け目〟に飛び込んでから──。
おれは薄暗がりの中、シールド越しに目を凝らした。広場にいた。周囲に水は無い。河川敷だ。
おれの周りには建物の残骸。前方には橋。オレンジ色の道路灯が点々としている。
空を見上げると雲が割れ、隙間から星がちらほら覗いている。川下の地平線が微かに白み始めていた。
ディスプレイの時計を見る。午前三時五〇分だった。
静かだ。
明らかにさっきまでの世界ではない。
とうとう、元の世界に戻って来たのだと直感した。
立ち上がった。五体は揃っていた。
一〇メートルほどの高さから落下したが、S.A.T.O.のお陰でたぶん怪我は無い。
〔OKサトー、ダメージを報告〕
〔マイクロパイルドライバーが作動不能です〕
〔それだけか〕
〔はい、以上です〕
突然、右前方で車のヘッドライトが灯った。
車は音も無く動き出した。電気自動車か。おれの方へゆっくりと近付いてくる。
まずい。S.A.T.O.のような物はこちらの世界には無い。こんな物を装着している姿を見られたら何と思われるだろうか……。コスプレだと言い張るしかないだろう。覚悟を決めた。
車は黒のワンボックスカーだった。運転席のウインドウから女性の白い顔が覗いた。夜目にも美しい。しかも見憶えのある顔だった。
礼子──星野礼子だ。
だが、少し違和感。
「お帰りなさい、ゴリさん。一〇年と三カ月後の世界へようこそ」
おれはその言葉に驚いた。明らかにおれだとわかって言っているのだ。疑問が頭の中に渦巻く。
なぜ、S.A.T.O.を装着しているおれが判別できるのか。
なぜ、おれがどこからか戻って来たことがわかるのか。
なぜ、おれがこの場所にいるのを知っていたのか。
なぜ、一〇年三ヶ月後なのか。
なぜ、おれの渾名を──。
おれはシールドを開けた。
「何て言ったらいいのか……」
「『ただいま』でいいんじゃない?」
と、礼子は言った。
「ただいま……。さっき一〇年と言いましたね。すると今は二〇二九年──?」
「そうよ。あそこの〝裂け目〟は一〇年のズレがあるでしょ」
そうか。
鈴木もそうだった……。鈴木が戻りたくなかったのは、不在の間に一〇年先行した世界に来ることも不安の種だったのかもしれない。
「まずは車に乗って」
「このままで?」
「いいわ」
礼子が運転席から降り、夜風に髪をなびかせながら横のスライドドアを開けた。おれは素直に従った。内部は明らかに未来的なインテリアで、スペースも充分にあった。おれはS.A.T.O.のまま転がり込んだ。横臥したまま車が走り出す。
「なぜ君は……」
「箱根で待ってたのに、ちっとも来てくれないから迎えに来たの。待ちくたびれたわ」
おれは遥かな記憶を呼び起こした。
「……ああ。そうでした。──申し訳ない」
「──というのはフリだけ。本当はあなたがどうなるか知っていたわ」
絶句する。
知っていたって……?
「話せば長くなるんだけど──」
おれは横臥したまま苦労してS.A.T.O.を除装した。胸の傷が疼き、大怪我をしていたことを思い出した。
身軽になると、そろりそろりと助手席に移動する。
礼子が冷えていないペットボトルをよこした。変わった形をしていた。品名からスポーツドリンクらしい。長時間飲まず食わずだったからありがたい。おれはすぐに開栓して渇いた喉を潤した。
「経緯はだいたい知ってたわ。そして、あなたが経験してくれたことで説明が省ける」
「……? どういうことですか」
「説明することが多過ぎるわ。一番訊きたいことから順番に、一問一答形式で答えるわよ」
礼子は何もかもおれの事情を知っているようだ。
しかも話し方が変化している。記憶にあるよりもずっとフランクだ。
一番訊きたいこと──そうだ、新宿はどうなったんだ。お袋は……?
「新宿にミサイルが落ちたはずだ。本当に落ちたのか? その後どうなった?」
と、おれもフランクに話すことにした。
「落ちたわ。でも不発だった。もちろん街並みはかなり破壊されたわ。半径三百メートルが粉々。──あれは事故だったの。当然、国際問題に発展しそうになったけど、例によって政府は弱腰」
少なくとも核汚染は無かったらしい。
「そうだったのか……抜け弁天の方は?」
「あそこまでは距離があるから大丈夫。女子医大病院も問題無し。お母様の手術も無事成功して今も元気に暮らしてる。実はこの十年の間に致死性の新型肺炎のパンデミックもあったけど、なんとかサバイバルできた。今は松本の老人ホームで──」
え、老人ホーム?
「働いているわ。親戚のお家の近くだそうね」
確かに母の田舎は長野県だ。
「しかし新型肺炎って」
「ええ、大変だったわ」
マルゾンに並ぶような危機があったのか……。しかしお袋は無事だったらしい。おれは胸を撫で下ろした。
「よかった……」
「あなたのことは、あたしから伝えておいたわ」
「伝えておいたって……どんな風に……?」
「爆発で怪我をしたからアメリカで特別な治療を受けるって」
「お袋は信じたのかい」
「たぶん。──時々あなたの写真を見せておいた。喜んでたみたい」
「写真て……」
「もちろんAI生成よ。あたしと結婚したことにしておいた」
「結婚……」
そういえばそんなことも夢想していた。実質三か月前なのに、懐かしく思い出す。
「お袋は納得した?」
「たぶん」
礼子の説明で、おれは心底安堵した。またスポーツドリンクを口に含む。
「とにかく……とにかく色々ありがとう」
礼子は顎を軽く引いて答えた。
「今日は先に箱根に寄るけれど、その後お母様にも会いに行きましょう。方向はだいたい同じだし」
おれは頷いた。
「ところで、こんなこと今さらだけど、君はいったい──何者、なんだ?」
考えてみれば質問の順番が逆だった。
礼子という女は多くのことを知り過ぎている。それに──彼女の話し方には既視感があった。
「星野礼子。パートナー探し中の三十二歳」
「そうか、君は三十代になったのか……」
「年上は嫌?」
「というか、君はいったい──」
「あたしのママの名前は星野美伶。旧姓はアンダーソン芳井」
「えっ、何だって?」
おれは腰が抜けるほど驚いた。
この礼子は出会い系サイトで知り合った女で、ひょっとするとおれを騙しているのかもとさえ思っていた相手だ。それなのに。
「そう。あたしは美伶の娘よ。ママが四十五の時の子」
十歳だったあの美伶が四十五歳だって? いや、違う。混乱した。今ならもっと歳を取っていることになる。
「ということは、美伶ちゃんはこっちの世界に来たというのか?」
「ええ、昔からいるわ」
車はランプを昇っていた。首都高に入ったようだ。
「なんで……なんで隠していたんだ?」
「だって、いきなり言ったって訳わからないでしょう?」
確かにそうだ。おれがあっちの世界に行くまでは、美伶のことを知るわけがない。
「彼女はあっちにいた。なのにどうやってこっちに……」
「あっちとかこっちとか、よくわからないわ」
つまり美伶はあの時、多摩川に飛び込んだはずが、〝時空の裂け目〟に落ち込んだということか。
あの場所にもあったのだ。〝裂け目〟が。川の上流に。
おれがインテリホンのメッセージに残した並行世界の話を、美伶は図らずもその晩のうちに身をもって証明することになったというのか。
「だけどおれの知っている美伶ちゃんは十歳だった。時系列がおかしい……」
「ママは戸籍上は一九五二年生まれよ」
今二〇二九年ということは、七十七歳ということか。溜息が出た。立派な老人だ。おれは年齢を重ねた美伶を想像してみたが、具体的な映像はまったく頭に浮かばなかった。
「彼女は今、どうしてる?」
礼子の横顔がたちまち暗くなった。
「……いないわ。あたしを産んだ後すぐ亡くなった。高齢出産だったから──」
おれは再びショックを味わった。生き延びていたと知って喜んだのも束の間、また落とされた。おれはしばし目を瞑った。美伶の四十五年の人生とは、どういうものだったのだろうか。
「そうか……残念だ。ついさっき電話で話したばかりなのに」
──彼女は空間だけでなく、長い長い時間をも跳躍したらしい。
七十七歳から十歳を引くと六十七年前ということになる。一九六二年か。彼女はそんな時代まで跳ばされたというのか。
川というものは古来より時空の境目だと言われてきた。
それは真実だったらしい。
そして川の上流と下流とでは流れる時間もきっと違うのだ。〈二子橋〉と〈新二子橋〉の間は三、四〇〇メートルしかない。だがそのわずかの間に数十年のズレが生じたということなのだろう。
しかも並行世界だ。左右は逆転しているだろうし、固有名詞も価値観も、歴史だって変わっている。おれの場合と同様、ひどく混乱し、心細かったろう。それもわずか十歳だ。かてて加えて、この世界には嘘のような〝フィクション〟が溢れかえっている。
待てよ……。
おれはふと思った。ということはあのアンディも一緒だったかもしれない。
「アンディというクバナカン系アメリゴ──いや、アメリカ人のことを知らないか?」
おれがそう尋ねると、礼子は頷いた。
「なんとなく聞いたことがあるわ。ママの父親、つまりあたしのお爺ちゃんはアメリカ人だったから、ママはアメリカに帰ったの。その時に連れて行ってくれたのが……確かアンディという人だったような」
そうだったのか。美伶はボランティアの交換条件ではないが、アンディとある程度は行動を共にしていたらしい。二十歳そこそこのアンディだったが、異世界に飛ばされても状況に対応し、美伶を助けながら首尾よく生き延びたらしい。
それにしてもアンディは──いや、ジョージ・アンディ・ロメロは、あのロメロなんだろうか。
おれはふと思い立ち、礼子に言った。
「インテリ──いや……スマホを貸してくれないかい? 調べ物をしたい」
「タブレットでもいいかしら」
礼子がグローブボックスから出してくれた。おれが持っていた物よりもずっと薄型軽量だ。
「ありがとう」
受け取るなり、おれはウィキペディアで〝ジョージ・A・ロメロ〟を調べた。
文字は当然ながら正像だ。だが逆に違和感があった。すっかり鏡文字に慣れてしまっていたのだ。
一九六三年には友人と映像制作会社〈ラテント・イメージ社〉を立ち上げたという。
おれはあちらから持って来たインテリホンを取り出した。もちろん通信はできないが、撮った画像はアーカイブされているはずだ。
開く。
猿座が転送して来た画像を呼び出す。アンディのビデオカメラとパスの画像だ。
GEORGE ANDREW ROMERO
Director of photography
LATENT IMAGE Co.,Ltd.
社名が同じだった。ウィキをさらに読み進める。その五年後の一九六八年、ロメロ監督は『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』を制作したとある。
〝リビングデッド〟──そうか、〝存命遺体〟の直訳ではないか!
さらに目を移すと、ロメロは〝キューバ系〟とある。キューバを検索すると、その国名の由来が〝クバナカン〟というらしい。
やはりあのアンディだったとしか思えない。
あっちでの経験を元に、『ナイト~』以降のゾンビ作品を作り続けたのだ。そして世界が認める有名ホラー監督になった。
そう考えると、アンディは幸運だったと言えなくもない。
「君はジョージ・A・ロメロというアメリカの映画監督を知っているかい?」
礼子は首を傾げた。
「名前は聞いたことはあるけど、よく知らないわ。確かホラー映画の監督なんでしょ。あたしはホラーは嫌いだから」
おれは苦笑するしかなかった。
「美伶ちゃんは──君のお袋さんはどんな暮らしだったんだろう」
「結局パパ、つまりあたしのお爺ちゃんとは会えず、施設で育ったと言ってたわ。日本に戻ったのは成人してから。しばらく独身だったけど、三十を過ぎて日本人のパパと結婚したわ。ずっと仕事が忙しかったから、四十代になってやっと子供を産むことができた。でも……」
美伶の父親は当然こっちにはいない。それにしても──今でこそ四十代の高齢出産は珍しくなくなったが、二十年、いや三十年前はリスクが大きかったはずだ。
ということは礼子はクォーターということになる。最初、どこかエキゾチックな顔立ちだと思ったのはそういうわけか。
「そんなに見つめないで……恥ずかしい」
「いや……君のその率直な話し方になぜか覚えがあるんだ」
「これはママ譲りよ」
そうなのか? しかし十歳の美伶はそこまでではなかった。
ああ、そうか。
あの坊丸に似ているのだ。
しかしなぜだ。
もしかすると、坊丸もまた生き残って、美伶たちと行動を──。
だが、確かめる術はない。
車は東名高速道路に入り、加速した。
「ママが遺した日記には、あなたのことがよく出てきたわ。初恋の人だって」
「それは……嬉しいね」
おれはそう言ってみたが、ひどく虚しく響いたのは自分でもわかった。
美伶は礼子におれのことを含め一連のマルゾンパニックについて一切合財伝えていたのだろう。だから戻って来てからのこの流れになっているらしい。
「お陰であたしも〝ブサ専〟になっちゃった」
おれのことだろう。
「ずいぶんとハッキリ言うね」
そう言いながら、おれは気分が落ち着くのを感じていた。あっちの世界で美男だイケメンだともてはやされ、自分の中で精神の均衡を取るのが難しくなっていたのだ。
だからブサイク呼ばわりは逆に嬉しい。
「ブサ専だから近付いたわけじゃないわ。いえ……それもあるけど、もちろんそれだけじゃない。パートナー探し中って言ったでしょ。本来の意味のパートナーよ」
「……というと?」
「あなたでなければ出来ない仕事を、暫定的にあたしが預かっているからよ。あなたを見付けた時から少しずつ話をしようと思っていた」
見付けた? 出会い系サイトで? そうか、美伶にそんな話をしたっけ。彼女にはおれの素性までは知らせていない。だからそれが唯一の手掛かりだったのだ。
「仕事というのは……どんな?」
「それについては箱根に着いてから説明するわ」
車は厚木に差し掛かったようだ。大きくカーブした。
道路標示を見ると小田原厚木道路とある。後方から朝日が差してきた。徐々に明るくなっていく。
太陽の方向が新鮮だった。
「──そういえば、なぜ今日おれが戻って来ると知っていたかを聞いていない」
「ああ、それ。──それもママの日記にあったの。あなたの名前の横に今日の日付と〝ハーメルン〟〝二子橋〟って。場所はわかるけど、ハーメルンが何かは気になった。調べたのは大昔、子供の頃よ。『ハーメルンの笛吹男』というお伽話ね。その出来事が起きた日付がやっぱり今日、六月二十六日。だから、あなたがいなくなってから、その日その場所に行けばいいと直感した。でも、年がわからなかったから毎年通ったし、時間もわからなかったから午前〇十時から丸一日ずっとあそこで待っていたわ。今日もよ。冬じゃなくてよかった」
そうだったのか。毎年とは。まるで七夕だ。
しかし鈴木はハーメルンの伝承の日付をよく憶えていたものだ。それともただの偶然だろうか……。
おれは礼子の十年を想った。
「十年も……申し訳ない」
「あなたが謝る必要はないわ」
それから一時間弱で、おれたちは箱根湯本に到着した。
市街地を抜け、峻嶮な山の中へ分け入っていく。
やがて山を切り開いて造成された平地が現れた。
その真ん中に、朝日を受けて近代的な建物がそびえていた。
輝くばかりのメタリックな看板に『大××××C××××D×××マルゾン研究所』とある。
サ×××ダ××だって? マルゾンだって?
これはいったい……。
車は地下の駐車場に滑り込む。
エレベーターでオフィスへ。シンプルで真新しい小奇麗なフロアが広がっていた。
「ようこそ我が社へ」
「え、我が社って……」
「正確にはパパが大手に吸収合併された会社の一部よ。──さあこちらへ」
礼子に連れられてガラスで仕切られた一画に入って行く。
反対側の窓から見下ろすと、そこはまだ屋内で、下のフロアが見下ろせた。横長の研究室になっていた。
部屋の隅の大きなデスクへ誘導された。上にはPCとマルチモニターが載っている。
礼子が左手でマウスを操作すると、映像が現れた。
海に停泊する豪華客船が映っていた。
「十年前の映像よ。新×××号だわ」
と言って、礼子は画像を切り換えた。
船の中と思しき動画だった。大勢の狂乱した人々がでたらめに動き回っていた。
これも見覚えがある光景だ。
まるでマルゾンではないか。
「船内がこの状態のまま日本海に停泊していたの。新宿に落ちたミサイルは、実はこの船を目標に発射されたとの情報がある。でも、設定ミスで日本本土まで飛んでしまったんだと言われているわ。メチャクチャ杜撰よね」
「ということは……」
「そう。当時、かの国ではゾンビ、いえマルゾンが大量発生したらしいの。その一部が国外に出てしまったというわけ。事実を揉み消すためにかの国が行ったのがこれ。でも失敗したわ。だからパパたちが中心になっているNGOが秘密裡に客船ごと処分した。少なくとも日本国内では一件落着となった。でも──その後再び、かの国でマルゾン再発の噂が流れてきた。いずれまた日本にも、そして世界中に拡大するのは時間の問題。ママはそれを予期していたみたい。
それでパパたちは新たな対抗手段を講じることにした。具体的にはH××の改良ね。──ママはとっくの昔にマルゾンのことを予期していて、H××の影も形も無い時に進言していたらしいんだけど、当時は変人扱いで誰も信じなかった。だから、とにかく詳細な手記を書き遺した。ママが亡くなってだいぶ経って、誰もその時のことを忘れてしまった頃、予言のような事件が起きたから、パパは慌ててママの手記を読み直した。そして対策のためにこのラボを改造した。それから十年──今に至るというわけ」
そうか。
恐らく美伶は二子玉川の阻止作戦が失敗した場合のことを心配していたのだろう。
結果的に形は違うものの、予言は当たった。
「ところで……おれに何をしろと?」
おれは疲れから立っているのが辛くなり、性急に訊いてしまった。
「あなたはマルゾンの原因も知っているし、多くを経験している。頭の中には対策のためのアイディアがあるはずだから、あなたを探し出すようにと書かれていたのよ」
ここでもVIP扱いか。おれは戸惑った。
「……確かに鈴木のZIMの開発は手伝った。美伶ちゃんはそのことを覚えていたのか。──だが、おれは外装の設計を手伝っただけだ。マルゾンの原因だってこっちでも同じとは限らない」
「でも、本物のマルゾンとやり合ったんでしょう。貴重な存在だわ。こちらでは誰もがフィクションの世界でしか知らないもの」
フィクションか、改めていい響きだ。
特にゾンビに関しては。
──確かに警予隊に出向し、結果的に特別な経験をした。しかも、こっちでは未開発のはずのS.A.T.O.まで持って来てしまった。ZIMを一から開発したあっちよりは圧倒的に時間短縮ができるだろう。
おれは黙って頷いた。
礼子がアメリカ人のような仕草で肩を竦めた。
「──あたしの役目はここまで。あなたを見つけ出して案内するまでが仕事。これで……やっとママの遺言を実行することができた。あの日記が遺言と言えるならだけど。あとはあたしの自由にさせてもらうわ。ところで、あなた──ゴリさんさえよければなんだけど、その……あたしと──」
そういう礼子の美しい顔が急速にぼやけた。瞼が重い。
「悪いけど、ちょっとソファを貸してくれないか。眠くて立っていられない」
言うが早いか、おれは柔らかなソファの上に崩れ落ちた。
意識が遠のいていくのに任せた。
次に目覚めた時、おれはちゃんとここにいるだろうかと思いながら……。
マルゾン第一部・完
この物語はフィクションであり、実在する人物・団体等とは一切関係がありません。
【マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした】
最終回 new ←いまココ
\オススメブック!!/