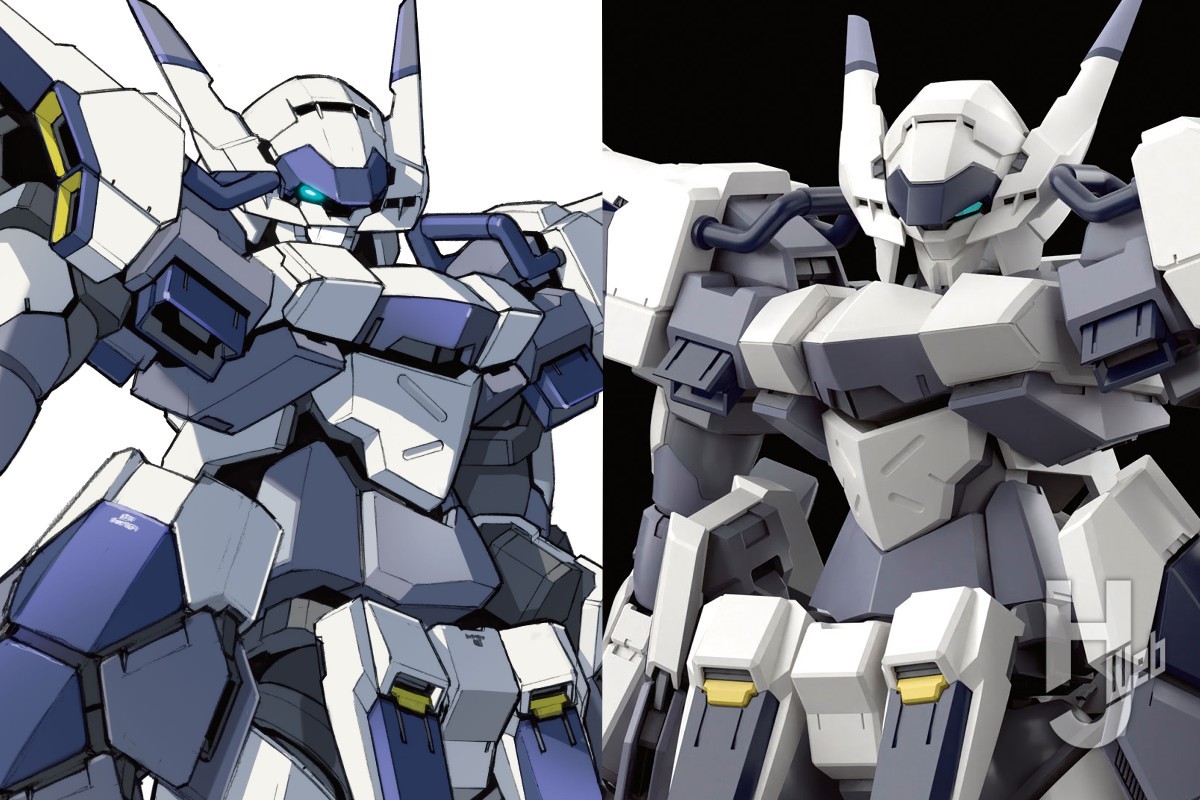【第8回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.10.13マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
第23章 奪還
日曜日、午前八時過ぎ、おれたちを乗せたレンタカーは霞ヶ関近辺を走っていた。
六本木を出て、ひとまず東京駅方向に向かったのだ。
おれと坊丸の服装はスーツ姿だった。二人とも会社から貸与されている。彼女はさらにサングラスとマスクと帽子で顔を隠している。坊丸にとって、相手は味方だからだ。
サトーコーポレーション本社はJR、いや国鉄御茶ノ水駅の隣にあった。坊丸によれば、関連施設も会社を中心とした半径一〇キロメートル圏内にあるはずだという。そのどこかに美伶はいる。
おれたちは出発地点として大雑把にアタリを付けた。これは賭けだった。外れた場合は最大でほぼ二〇キロメートル、ロスの見込みになる。
ひとまず山手線に沿って反時計回り、いや時計回りに走ることにした。小回りを利かせるため、首都高にはまだ乗らずにいた。休日なので道はそれほど混んではいない。
作戦はこうだ。
まず、予め美伶のインテリホンにメッセージを入れておく。内容は、彼女が今置かれている状況、そしてこちらの救出計画についてだ。美伶がインテリホンの電源を入れ次第、メッセージに気付くはずだ。
彼女が自宅の住所を返信してくれればこちらの仕事が早いが、打ち込み作業中に付添いのサトー社員に見とがめられると面倒なことになる。ましてや通話はもっとまずい。美伶の自宅住所を漏らしたからと言って彼らの不利益になることはないが、それ以前に妨害されたと勘繰られれば、即座にインテリホンを取り上げられて電源を落とされるだろう。だから、極力レスポンスは控えるように書いておいた。
後はこちらがインテリホンの所在を察知次第、追跡を開始する。家の近くに停車した時点で彼らに詰問し、ニセ児相であることを喝破して美伶を奪還する。もしごねられたら警察を呼んでもいいが、そこでヘタに親が巻き込まれると面倒だ。
もし彼らがDV継父への引き渡しを済ませてしまったら、坊丸と共に新たな児相に扮し、理屈を付けて美伶を再度引き取る。そのためのスーツ姿だった。
父親が暴力で抵抗したら、坊丸がサトー社から持ち出した屠畜用スタンガンで応戦することにしていた。バトンタイプの強力なもので、牛さえも落ちる一五〇万ボルトの電気ショックを与えることができるという。
大半を運に頼った雑で強引な作戦だが、仕方がない。おれはひたすら脳内でイメージトレーニングを繰り返した。
「鈴木社長にはどう説明するつもり?」
運転をしながら坊丸が訊いた。
「まだ何も考えていない」
と、おれは答えた。
「そう」
「……猿座には何か言ったのかい?」
「言う必要は無いわ」
おれは首を傾げた。
「君らはパートナーじゃなかったのか」
坊丸は顔をしかめた。
「仕事上はそうだけど……プライベートは関係ない」
「しかし猿座の方は違うようだけど」
「それが悩み所ね。あいつ、あたしに執着し過ぎなのよ。もうほとんどストーカー。ほとほとウンザリしてきた」
おれは歌舞伎町偵察の時のことを思い出していた。
「……そうだったのか」
「だいたい、タイプじゃないのよ、あんなブサイク。まあ、人のことは言えないけど」
また自嘲的な言葉が出た。この感覚ばかりはなかなか慣れない。バランスを取るために言う。
「君は全然ブサイクじゃないと思うけどなあ」
ついでに猿座もそうは思わない。おれからしたらすこぶるイケメンだ。
「お世辞でも嬉しい」
そう言って坊丸はわずかに頬を紅潮させた。
「本当さ」
「本当にそう思う? そしたら、あの子を連れ戻した暁にはサシで呑まない?」
いや、おれには礼子という女性が……。
言葉を濁す。
「うーん……考えとくよ」
坊丸は頷いた。
「考えといて」
その後もおれは何度も追跡アプリを立ち上げ、反応を見た。相変わらずエラーメッセージが出る。
池袋駅を過ぎた九時一五分頃だった。
遂にアプリに反応あり!
地図画面に青いマーカーが点滅していた。
美伶がインテリホンを受け取って電源を入れたのだ。予想がうまく的中した。
アプリの地図では、中野駅近辺を指していた。早稲田通りを西、いや東に向かっている。
おれたちはすぐに車線変更し、山手通りに入ってひたすら南下した。
おれたちが早稲田通りに入った頃、美伶の乗った車は阿佐ヶ谷駅付近に達していた。
「距離がなかなか縮まらないな。もっと急げないか」
おれは言った。
「でも、今スピード違反で捕まるわけにはいかないわ」
「……それもそうだな」
この世界の警察は四角四面にきっちり取り締まると、いつか鈴木にも聞いたことがある。
焦り始めた。なんとか追い着きたい。
できるだけDV親父との大立ち回りは避けたかった。ZIMを着ていない時はてんで心細い。
「時間稼ぎをする。美伶ちゃんにメッセージを送って、『トイレに行きたい』と言ってコンビニに立ち寄るように書いてみるよ」
「さっきのもそうだけど、うまく読んでくれるかしら」
「わからない……」
一〇分後、アプリの地図上のマーカーが動きを止めた。
「〈オールデーマート〉というのは、普通のコンビニかい?」
おれは念のため訊いた。
「当たり前じゃない。あんな有名な店」
「おれは田舎の出なんだ。──美伶ちゃんはメッセージを実行してくれたようだ」
「よかった。できるだけ時間を引き延ばしてほしいわね」
「『お腹が痛い』とか理由を付けてくれると助かるんだが」
マーカーは一五分ほど止まっていたが、また動き出した。
微々たるものだが上出来だろう。もう一度くらいトライしてほしいところだが。
だが、その後はマーカーは止まることなく荻窪を過ぎ、府道三一一号線を南下していた。
次にマーカーが止まったのは南荻窪一丁目辺りだった。地図を見ると今度はコンビニではなく、明らかに入り組んだ住宅街の一角だった。たぶん自宅に着いたのだ。
だがおれたちはまだ荻窪駅を過ぎた辺りだった。焦る。
一方通行に苦労しながら、なんとかマーカーの停止位置に到着した。
おれたちは二〇分遅れていた……。
そこは、元はクリーム色だったと思しき、シミだらけのモルタル壁の二階建てアパートだった。前の道路には白い軽自動車が停まっていた。たぶんサトー社の車だ。
辺りには人の気配は無い。彼らはまだ室内にいるのだろう。
壁に掛かった錆びだらけの集合ポストを見る。一階の角部屋のポストに雑な字で〝芳井〟とあった。
間違いない。美伶の家だ。
ニセ児相を含めた大人四人を相手にどう立ち回るか、おれは何度目かのイメージトレーニングを繰り返していた。
おれたちは角部屋の前に立った。ドアチャイムを押すが返答は無い。
ドアに近付くと、中で微かに物音がする。
ノックをしたが、これまた返答が無い。
坊丸を振り向く。手にはスタンバトンを握っていた。
おれはドアノブを回した。
ロックされていない。開ける。
狭い玄関に人が倒れていた。
スーツ姿の男だ。サトー社の社員だろう。
おれと坊丸は顔を見合わせた。
男の身体の下に大きな血だまり。壁にも血しぶき。
おれの鼻孔に新しい鉄の匂いと、籠ったような腐敗臭が押し寄せる。
宙にはハエが飛び交っている。
嫌な予感……どころではない。
「警察を呼ぶわ」
と、坊丸がインテリホンを掴んで外へ出て行く。
おれは彼女からスタンバトンを引ったくり、土足のまま中へ入った。美伶が心配だ。
小さな台所兼食堂に入ると、腐臭と排泄物臭が強くなった。
もう何が起きたか、薄々わかった。しかしここは杉並区だ。内藤新宿とは違うはずなのだが……。
おれは怯みながらもスタンバトンを突き出し、引き戸を開けてゆっくりと奥の部屋へ進んだ。
飛んでいるハエが増え、おれは口許を庇った。
窓際で、脱色した髪の痩せた女と斑のスキンヘッドの巨漢が蹲っていた。
両者とも一目でマルゾンだと分かった。
彼らは倒れている人間の腹から赤い肉塊を引きずり出しては口に運んでいた。
辺りにはまだ鮮やかな色の血が飛び散っている。
犠牲者はこれもスーツ姿だった。サトー社の社員だ。
すると……美伶はどこにいる?
おれは部屋の中を見回した。
家具・寝具・衣服・食器類・雑誌・食品の袋・空き瓶と、あらゆる物が散乱している。まさにゴミ屋敷だ。
中でもペットボトルとカップ麺の空容器、菓子類の袋が目立つ。
足元の青いポリバケツには白っぽい物が山盛りになっていた。よく見ると、それは全て噛みかけのガムだった。歯型が残っている。取ってあるということは、再び噛むということか。それは貧しさゆえのことだろうか。
昔何かの本で見たアメリカの有名なサイコキラー、エド・ゲインの家を思い出した。彼もガムのクズを空き缶に大量に溜め込んでいた。
新型エサウ病の発症以前から、この家族の破綻した暮らしぶりが窺える。
こんな家なら美伶でなくても逃げ出したくなるだろう。
その時、後ろから人の気配。
はっとして振り向くと、坊丸だった。
「これはひどい!」
そう声を上げたのは、坊丸の後ろから現れた男だった。
制服を着ている。警官だ。
その声にマルゾンたちが反応し、おれたちの方を見上げた。ゆっくり立ち上がる。
「しっ!」
と、おれは言った。
「お巡りさんがちょうど近くにいたので頼んだの」
と、坊丸。
「あれはきっと、あの子の両親だよ」
おれはマルゾンの方に顎をしゃくった。
生身のまま、この狭い空間でマルゾン二体を相手にするのは危険だった。ひとたび捕まれば最後、容易には逃れられない。
「美伶ちゃん、いるのかい?」
おれは部屋の奥に向かって小声で問い掛けた。
マルゾンの後ろの押入れの扉がススッと開いた。
一〇センチほどの隙間から、小さな白い顔が覗いた。
そこに美伶が隠れていたのだ。
「助けに来たよ。もう大丈夫だ」
だが、マルゾンが前にいて美伶は出て来れない。
警官が腰のホルスターから回転式拳銃を抜いて、撃鉄をカチリと上げた。
「撃たないでください」
と、おれは警官に言った。
マルゾンを殺していい法律はまだ無いし、まがりなりにも美伶の親だ。美伶の見ている前ではまずい。
おれはスタンバトンを最大の百五十万ボルトに設定してスイッチを入れた。
男のマルゾンに近付く。
胸元目がけて突き立てた。
バチバチと音がして、マルゾンが軽く痙攣した。
だが、昏倒することはなかった。
電撃が効かない……!
マルゾンがスタンバトンを掴んだ。
急いで引き剥がそうとしたが、圧倒的な握力でビクともしない。
おれはなんとか取り戻そうと頑張ったが、結局諦めた。手を放す。
おれはすぐに後ろに飛び退った。こんなことなら無理をしてでもZIMを持って来ればよかった。
だが予想できなかったのだ。
女のマルゾンが坊丸に迫る。
おれからスタンバトンを取られた坊丸には防御の手段が何も無い。その辺にある物を手当たり次第に投げ付けていた。
警官は拳銃を構えたまま、おろおろしているばかりだった。この世界の警官がこんなに使えないとは。
ガシャン!
突然、ベランダの掃き出し窓のガラスが割れた。
手摺を越えて外から男が入ってきた。
「あっ」
坊丸が叫んだ。
なんと、男は猿座だった。手にはモンキースパナを持っていた。
なぜ猿座がここにいるのだ。そうか。坊丸をストーキングしていたのだ。
猿座は男のマルゾンを後ろから掴むと、自分の体重を利用して窓の外へ引きずり出した。
地面に引き倒すと、頭めがけてモンキースパナを振り下ろした。何度も。何度も。
その度に血飛沫と脳漿が辺りに飛び散った。
「やめろ! 警察にまかせるんだ!」
おれは言ったものの、その警察が頼りにならない。我ながら虚しく聞こえた。
パン! パン!
拳銃の発射音がして、室内に目を戻した。
おれの言葉を聞いたせいなのか、警官が急に仕事を始めたようだ。女のマルゾンを撃っている。
「やめて!」
坊丸が言ったが、警官は射撃をやめようとしない。
パン! パン!
また二発。
坊丸が女マルゾンを庇って飛び出した。
パン!
坊丸が前にいるにも拘わらず、警官が拳銃をまた一発。そしてカチカチと撃鉄だけが当たる音が続く。五連発か。
坊丸は胸を押さえてその場にくずおれた。
ワイシャツの前が真っ赤に染まっている。
「馬鹿!」
おれは誰にともなく叫んで坊丸に走り寄った。
「坊丸!」
猿座が叫んで室内に飛び込んできた。
二人で坊丸の体を抱えると、玄関へ走った。
女マルゾンが追って来た。
それが押入れの前から離れると、中から美伶が飛び出すのが見えた。
「ママ、ごめん!」
美伶が女マルゾンの脚にタックルをした。
マルゾンは前のめりに倒れた。その上を美伶が跳び越えてきた。
全員が玄関を出ると、美伶がすかさずドアを閉めた。
腕の中の坊丸は微かに息があるようだったが、ほとんど風前の灯に見えた。
「坊丸よ……」
嘆きの声を上げる猿座に坊丸の身体を預けると、おれはおどおどしている警官に喝を入れ、一緒に廊下の洗濯機を動かしてドアのバリケードにした。
その前にへたり込むと、おれはやっと息を整えた。
誰かが呼んだのか、救急車のサイレンの音が聴こえてきた。
つづく
この物語はフィクションであり、実在する人物・団体等とは一切関係がありません。
【マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした】
第8回 new ←いまココ
\オススメブック!!/