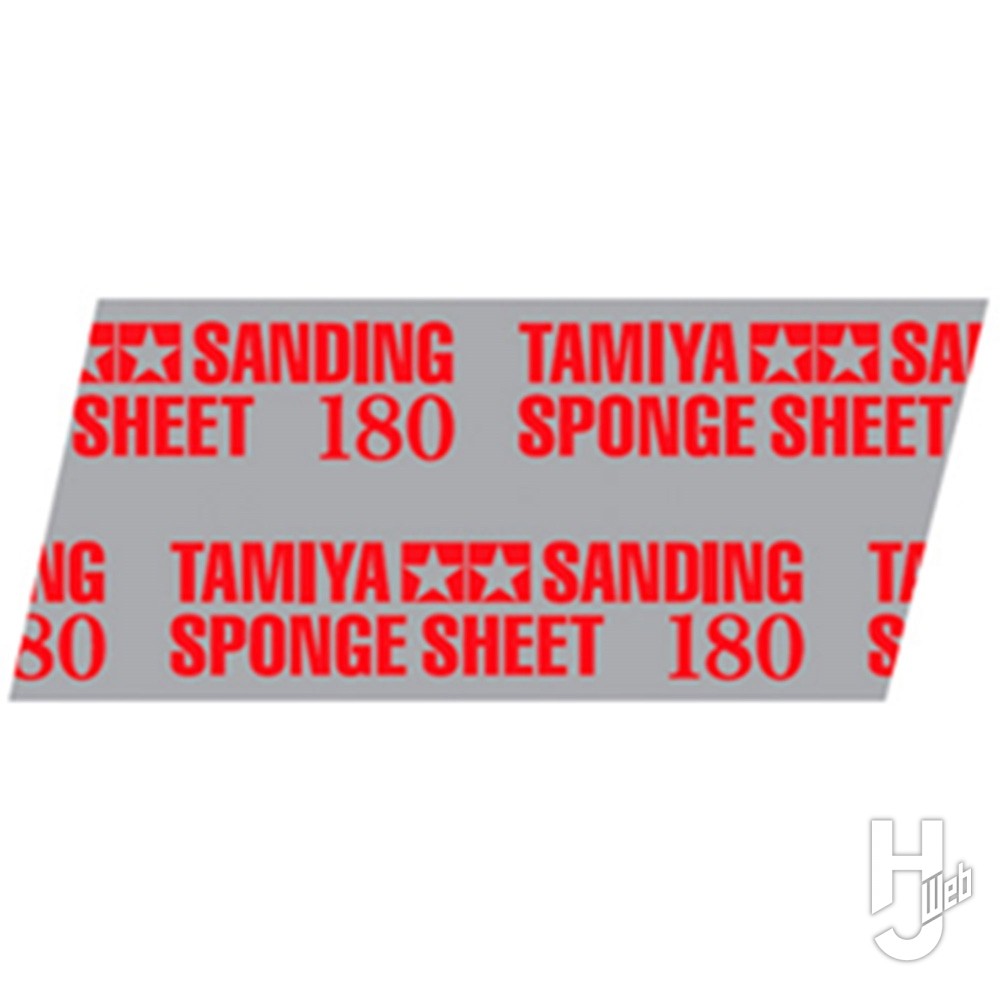【第5回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.09.22マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
第14章 存対会議
〈保健社会省〉通称〝保社省〟なる、おれの知っている厚生労働省に相当する行政機関内に、〈存命遺体対策進行委員会〉通称〝存対〟が設置された。
鈴木がその民間委員の一人に任命され、対策会議に参加することになった。
鈴木に乞われて、おれも補佐役として背広を着て帯同することになった。ゾンビを知っていることと、ZIMで歌舞伎町を偵察してきたことが役に立つかもしれないという判断らしい。果たしておれに発言の機会などあるのだろうか。
作ってもらった名刺によると、おれの肩書は〝ハインライン株式会社企画部主任〟ということだった。
存対本部は霞ヶ関の保社省の庁舎内の会議室に設置された。
入ってみると、思ったよりも狭かった。ロの字に並べられた長テーブルに中年の男女数人が着いていたが、当然ながらおれの知らない人ばかりだった。
各人の前には弁当の包みと緑茶のペットボトルが置かれていた。めいめいに雑談をしている。鈴木とおれは出入り業者のごとく席を回り、各人と名刺交換をした。
まずは一番年齢が高いと思しき人物へ。小柄な白髪のオールバック。名刺は質素だったが、字面を見ると〝東京府副知事 三田正弘〟とある。
東京府? そうか。時々感じていた違和感の元はこれか。この世界では東京は〝都〟ではなく〝府〟らしい。
次に〈教育科学省〉通称〝教科省〟の高橋課長。黒縁メガネをかけた三十代くらいの長身の優男だった。こっそり鈴木に訊くと、以前の世界の文科省に相当する省らしい。
パンツスーツ姿の若手のキャリアウーマン風は、〈環境保全省〉通称〝環保省〟の市原課長補佐。名称からして以前の世界では環境省のことだろう。以前の世界ならクールビューティーと呼ばれるような冷たく整った容貌は、ここでは〝ちょいブス〟に属するのかもしれないなと思った。
〝商工省〟の吉田部長はまるで時代劇に出て来る悪徳商人風だ。鈴木によると経産省に相当するとのこと。
迷彩服を着て日焼け顔のスポーツマンタイプは、〈警察予備隊〉通称〝警予隊〟の谷口警察士長。警察とは微妙に違うその古臭い組織名に微かな記憶があった。
確か──自衛隊の前身の名称だったはず。鈴木に耳打ちすると、やはりそうだと答えた。どういう経緯でこの名称が存続したのかが気になる。
〈東京府防災課〉の局長で、諏訪という人間もいた。前歯がはみ出していて、『ゲゲゲの鬼太郎』のねずみ男そっくりだと思った。
そして、鈴木の会社のライバルとされる製造会社も参加していた。名を〈サトーコーポレーション〉といい、社長も佐藤と名乗った。色白の細面、きっちり七三に分けた髪、銀縁メガネと、上品そうな佇まいだ。
雑談の喧噪に紛れて鈴木がおれに耳打ちする。なんでも佐藤は鈴木より一回り上の年代で、鈴木以上のやり手らしい。農業・畜産関係の機械・用具の製造を一手に扱っているという。
封鎖中の歌舞伎町を事前に空中偵察したマルチコプターはこの会社の製品らしい。性能の高さから国内シェアナンバーワンだという。
マルチコプターは元の世界でいうドローンのことだが、元々は農薬の空中散布用に開発されたものだと聞いたことがある。しかしマルチコプター以外のサトーコーポレーションのどんな製品がマルゾン対策に有用なのかはよくわからない。まさかトラクターや耕運機でマルゾン制圧なんてことは……いや、ありか?
対策会議が始まった。
見渡すと布陣は思ったよりこぢんまりしていた。『シン・ゴジラ』のような規模感はない。だが、マルゾンつまりゾンビの謎を解明しようという場だ。期待せずにはいられなかった。
おれの隣で、鈴木が愛用のアイディアノートとノートマイコンをテーブルの上に並べた。
保社省の山田課長が存対委員長ということで、議長を務めた。
「早速ですが、桝先生から〝存命遺体〟に関するご報告をお願いします」
「はい」
おれもすでにお馴染みとなった元治大学医学部の桝博士が立ち上がり、コホンと一つ咳払いをした。
「いや、座ったままでどうぞ」
議長の山田が言った。
「ありがとう。──先般、サンプルを仔細に観察させていただきましたが、率直に申しまして、アレは〝遺体〟ではありません。従って〝存命遺体〟という呼称は不適切かと思われます」
いきなり名称の否定か。
桝博士の横には六〇インチほどの大型モニターが置かれていた。そこに、俺が撮影した歌舞伎町の様子と、それに続いておれたちが捕獲したマルゾンの映像が映し出された。
「えー、名称の問題はともかくとして──具体的にはどういう点でそう言えるのでしょう」
と、山田委員長は訊く。
「まず一見してわかりますが、あれは呼吸をしていました。呻き声が出ているのも証拠です。つまり肺が生きています。次に、心音がしていました。心臓も生きています。電極を取り付けると、心電図モニターに表示されました。
次に脳ですが、自発呼吸ができている時点で脳幹が生きていることがわかります。MRI画像によると、大部分が脳梗塞で壊死してはいましたが、一部は生きています。そのため、外部刺激への反応は希薄で、動作も異常です。知的活動もほとんど無いと言っていいでしょう」
博士が手元のノートマイコンを操作すると、モニターには心電図の波形に続いて頭部の輪切り画像が連続写真のように映し出された。
「それじゃあ馬鹿症だ」
と、商工省の吉田部長。
今、〝馬鹿症〟と言った? そんな侮辱的な病名があるわけがない。この男は実に粗野な人間だ。ここは〝認知症〟と言うべきではないのか。
「それも重度の馬鹿症です」
桝博士が平然と同じ言葉を繰り返した。
おれは驚いた。医学者の彼が堂々と口にするということは、どうやらこの世界では〝馬鹿症〟が正式名称としてまかり通っているらしい。
おれはペットボトルのフタを開けて、緑茶を飲み、心を落ち着けた。
「結局、解剖はしなかったんですか」
防災課の諏訪局長が訊いた。
「生きている者を解剖することはできません」
「ということは、彼らは超自然的な何かではなく、病人の一種ということになりますか」
と、環保省の市原女史。〝超自然的〟という概念はあるらしい。
「そういうことです」
元の世界のフィクションにおけるゾンビは当初、呪術等の超自然的原因だったが、ロメロの〝モダン・ゾンビ〟以降はある程度の合理的な理由が付けられることが多かった。まるで今回の件を予言したかのように思えた。
「やはり伝染病ですか?」
と、山田委員長が保社省として一番気になる所を訊いた。
「恐らく未知のそれです」
桝博士が認めると、山田委員長と防災課の諏訪局長が互いに顔を見合わせた。
「感染経路は? 空気感染はどうですか?」
諏訪局長が身を乗り出して畳みかける。
おれも気になっていた。坊丸が封鎖地区のど真ん中で頭を曝したのだ。
「感染経路はまだわかっていません。範囲が限定的なので、おそらく空気感染の可能性は低いと思われます」
「とりあえず封鎖の意味はあったのか……」
諏訪局長が安堵したように言うと、背凭れに寄りかかった。
おれもホッと胸を撫でおろした。
警予隊の谷口士長が挙手した。
「どうぞ」
「凶暴性を発揮して人を襲うのはなぜなんですか?」
桝博士が顎を引いて答える。
「目的は捕食です。おそらく満腹中枢が機能していないのと、慢性的な低血糖のため、異常に食欲があるのでしょう」
何人かがテーブルの上の弁当箱に目を落した。
「ところが食糧を手に入れる方法がわからなくて、手近な生物──つまり人を襲うというわけですか。まるで野獣ですね」
と、教科省の高橋課長。
「だったら、食糧を与えればおとなしくなるということですか」
と、すかさず市原が訊いた。
「それが……他の食品を見せても無視するのです」
桝博士が困惑げに答え、ノートマイコンを操作しモニターに動画を出した。
画面では、マルゾンの鼻先にトングで摘まんだソーセージ、パン、チーズなどを近付けていた。マルゾンはまったく興味を示そうとはしなかった。
しかし研究員が自分の手を近付けた途端、大口を開けて黄色い歯を剥き出し、噛み付こうとした。ガチガチと上下の歯がぶつかる音がする。
「おおっ!」
人々の間からどよめきが起こった。
「動物の生肉も一切、手を付けませんか」
市原女史がさらに訊く。
「まったく」
「恐ろしい……。なぜ、人肉なんでしょうか」
「それは……まだわかりません」
「彼ら同士で食い合うということはないんですか?」
と、高橋課長が踏み込んで訊く。
「偵察隊からの報告ですと、それはない模様です」
おれは人知れず頷いた。
「彼らは、自分たちと健常者とを区別しているということですか。なぜなんでしょう」
桝博士が肩を竦める。
「──これは推察ですが、人から発するフェロモンか何かを感知して区別しているのではないかと。これは元々動物や昆虫に顕著な習性です。死んだゴキブリが発するフェロモンで仲間が集まり、死骸が食糧にされることが知られています。存命遺体の場合も──効果は逆ですが──似た現象で、いわゆるヒトフェロモンで健常者を食糧と認識して捕食する。だが彼ら自身のフェロモンは変異していて食糧とは認識しない。同士討ちをしない理由はそれです。そして犠牲者も、死後短時間でフェロモンが彼らのように変異してしまう。そのため、食いかけの状態で放置されている遺体が多いのです」
「なるほど……」
「動きは鈍いけれど、怪力があると聞きましたが」
と、ここでまた谷口士長が割り込んだ。
「彼らはほとんどの神経が壊れているので、瞬発力はありません。つまり走ったり素早い動きはできません。しかし、筋力はあります。本来、人間の筋肉にはリミッターがあり、通常はポテンシャルの二〇パーセントほどしか力を出せませんが、彼らはリミッターが壊れているので、一〇〇パーセントに近い力を出すことができます。それゆえの怪力なのです。ですから、ひとたび彼らに捕まると逃げるのは困難です」
「迂闊に近付けないということか……」
「その通りです」
画面では、マルゾンにリンゴを持たせ、それを一握りで粉砕させる動画が流れていた。
「しかしですね、内藤新宿は日本一の繁華街・歓楽街だ。商業の中心地が封鎖されたままだと、東京の経済活動が停滞するばかりです。彼らから内藤新宿を取り返す方法を考えてもらいたいのですが。──ねえ、副知事」
と、吉田部長が商工省の立場から、当然の意見を具申した。
「うん、吉田部長の仰るとおりだ。インバウンドもかなり取り逃がしているからね」
と、三田副知事が言葉を選ばず同調した。
「焼き払ってしまえ」
と、諏訪が防災課局長らしからぬ暴言を吐いた。
「どうしてそんな短絡的ことを言うんですか。博士が仰ったとおり、存命遺体と言っても本当の遺体ではないんですよ」
と、市原女史が怒気を孕みながら言い返した。若いわりに慎重だし、ガッツもあるとおれは思った。
「だが、死んだも同然なんだろう?」
「確かに死にかけてはいます。放置すれば時間の問題でしょう」
桝博士が坦々と言った。
「でも、病人なら救けなければ。まずは保護しましょう」
と、市原女史があくまでも正論を言う。
「同感」
と、教科省の高橋課長。基本的に市原女史に同調する姿勢のようだ。年齢が近いせいだろうか。
「しかし保護したところで、治る見込みはあるんですかね」
諏訪局長は相変わらず冷たく言う。
「正直言って、元通りになることはありません。個体差はあるにせよ、脳の大部分が壊死していますから、障害者になるのは確かです」
桝博士の返答も冷然としていた。
「……」
「……」
一同黙り込んだ。
「確かに理想を言えば、保護して治療だと思います」
と、山田委員長が議事進行をするべく言った。
保護という観点は日本らしいとおれは思った。ハリウッド映画だとこうはならない。
「……では、どうやって保護しますか?」
三田副知事が眉間を揉みながら言った。
「それなら檻にでも入れますか」
吉田部長が冗談交じりに言った。
「それこそ猛獣扱いだ」
と、高橋課長。
「しかし現実的です」
と、谷口士長が同意を示す。
「有効でしょう」
「それしかない」
皆が口々に言った。賛成多数だと思った。
「では……檻を使うとして、充分な数があるんですか?」
三田副知事が誰にともなく訊いた。
「動物園から借りるしかないでしょうな」
諏訪局長が投げやりに言う。
「全然足りないでしょうね。確認されただけでも二百体超います」
と、谷口士長。
「……」
「……」
再び皆が押し黙った。何人かが、ペットボトルの緑茶を飲んで間を持たせている。
「──そうだ。佐藤社長の所では、確か大型家畜用輸送カプセルのユニットを作っている部門がありましたよね」
と、吉田部長が商工省の人脈で召喚したという佐藤社長に訊いた。
「はい、ございます」
佐藤社長が、待ってましたとばかりに微笑を浮かべて答えた。絶好のビジネスチャンスなのだろう。
「あれはかなり頑丈な物ですよね」
「はい。FRP製ですが、象でも入れない限りは壊れません」
「はっは、象なんて、まさか」
誰かが笑った。
「モニターの切り換えよろしいですか」
と、佐藤社長。
「どうぞ」
佐藤が手元のノートマイコンに接続してあるデバイスを操作すると、大型モニターの画面が切り替わった。佐藤のデスクトップが映し出されているようだ。
フォルダの一つが開かれ、画像が現れた。
それはクリーム色で、コンテナ型のトランクルームをやや小型にしたような外観をしていた。空気穴が各部に開けてあるようだ。アングル別の画像がスライドショーされている。
「そうか。あれを現場の近くにたくさん設置して、ひとまず保護するということだな」
と、三田副知事。
「なるほど。もし死んだとしてもエクスキューズにはなりますな」
と、諏訪局長。
「ひどい言い方」
市原女史が顔を顰めた。高橋課長が顎を引いて同意を示す。
「二百基……いや、三百基をすぐに用意できますか? 佐藤社長」
と、三田副知事が訊いた。
「……一週間はいただきたいですね」
佐藤社長がキッパリ答えた。
「決まった!」
と、吉田部長が手を一つ叩く。
「しかし、どうやって保護しますか」
「……やはり、鈴木社長の所のヨロイの出番ということになりますか」
と、吉田部長が言った。鈴木もまた彼に召喚されたのだ。
皆の視線が一斉におれの隣にいる鈴木に注がれた。それまでずっと眉間に皺を寄せていた市原女史があからさまに相好を崩した。鈴木のファンだろうか。
「吉田部長の仰るヨロイというのは、今回のサンプルを入手するために使用されたパワーアシストマシンのことですね。──どうですか、鈴木社長」
古臭い言い方だが、確かにZIMはヨロイの一種と言える。吉田部長はZIMに対して〝着る〟という概念をちゃんと理解しているようだ。
山田はZIMについて皆に簡単に説明してから、鈴木に発言を促した。
「はい。ではモニターを切り替えさせてください」
と、鈴木が言った。
「ユー・ハブ・コントロール!」
と、佐藤社長。冗談を言う人だったのか。
鈴木もデバイスとノートマイコンを操作して、ZIMの画像をモニターに映し出した。
おれが描いた三面図に始まり、CGによる透視図、稼働中の動画。そして歌舞伎町を偵察する様子。
映像の最後にZIMを除装して中から坊丸が現れると、また「おお」とどよめきの声が上がった。
「実はすでに量産態勢を整えています。こちらも一週間あれば二十体は用意できます。その間に、今ある試作品三体で装着者の訓練をすればいいでしょう」
鈴木にもビジネスチャンスが巡ってきたはずなのだが、彼は表情も変えずに淡々と答えた。
「すばらしい!」
と、吉田部長が言った。
「操縦は一週間の訓練で充分なのか?」
と、谷口士長が訊く。やはり人員は警察予備隊が手配することになるのだろうか。
「操縦ではなく、ただ着ればいいのです。早い人なら三日あれば」
と、鈴木。早い人とは、おれのことを言っているらしい。
「着る?」
と、三田副知事がぼんやりした顔で訊き返す。
「そうです」
「ヨロイだから当然、着るんでしょうな」
と、吉田部長。
「着る……」
「こちらも決まりでしょう!」
と、再び吉田部長。
きっと彼は佐藤社長や鈴木から袖の下を渡されているのであろう。いつかハインライン社内のロビーで顔を見かけた記憶が微かに蘇った。
「収容場所はどこになりましょうか」
と、山田委員長が訊いた。肝心なことだった。
「近隣で広い場所と言えば中央公園でしょうな」
と、三田副知事。
「遠くないですか」
「まさか御苑というわけにはいかんでしょう」
「確かに……」
御苑もこの世界ではアンタッチャブルらしい。
「車に乗せてしまえば距離は関係ないのでは」
と、谷口士長。
「確かに……」
「決まった!」
と、また吉田部長。さっさと休憩に入りたいのかもしれない。
「では、存命遺体の収容に関しては以上で決定とします。これから一時間のお昼休憩を挟んで、その後は治療や予防、そして病原体の特定について考えたいと思います」
山田委員長が一旦締めると、皆はめいめいに弁当の包みを開け始めた。
つづく
この物語はフィクションであり、実在する人物・団体等とは一切関係がありません。
【マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした】
第5回 new ←いまココ
\オススメブック!!/