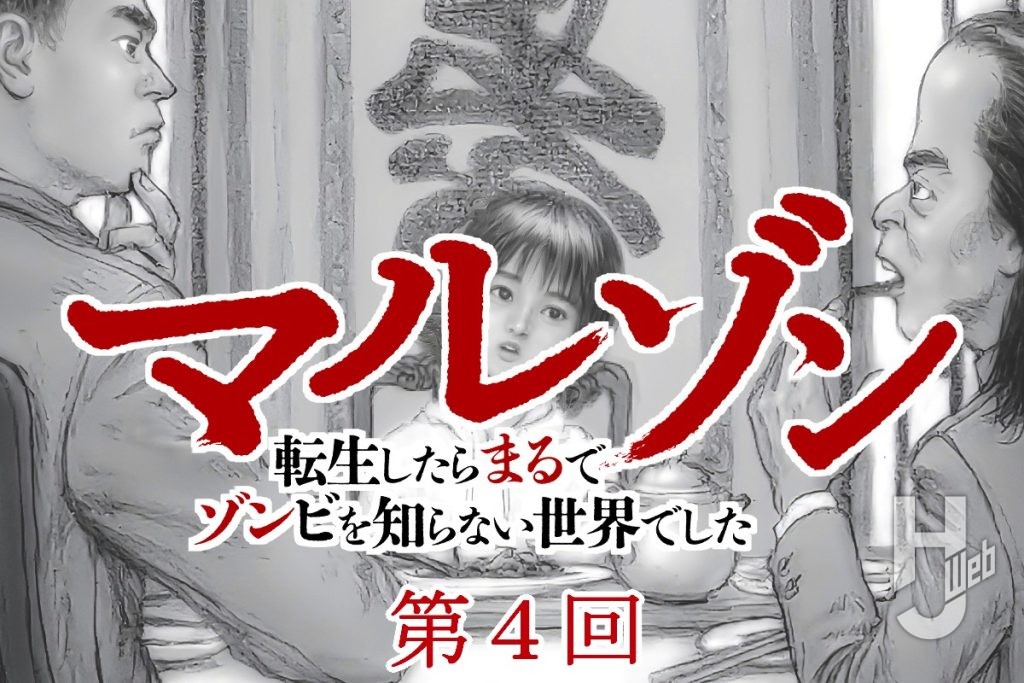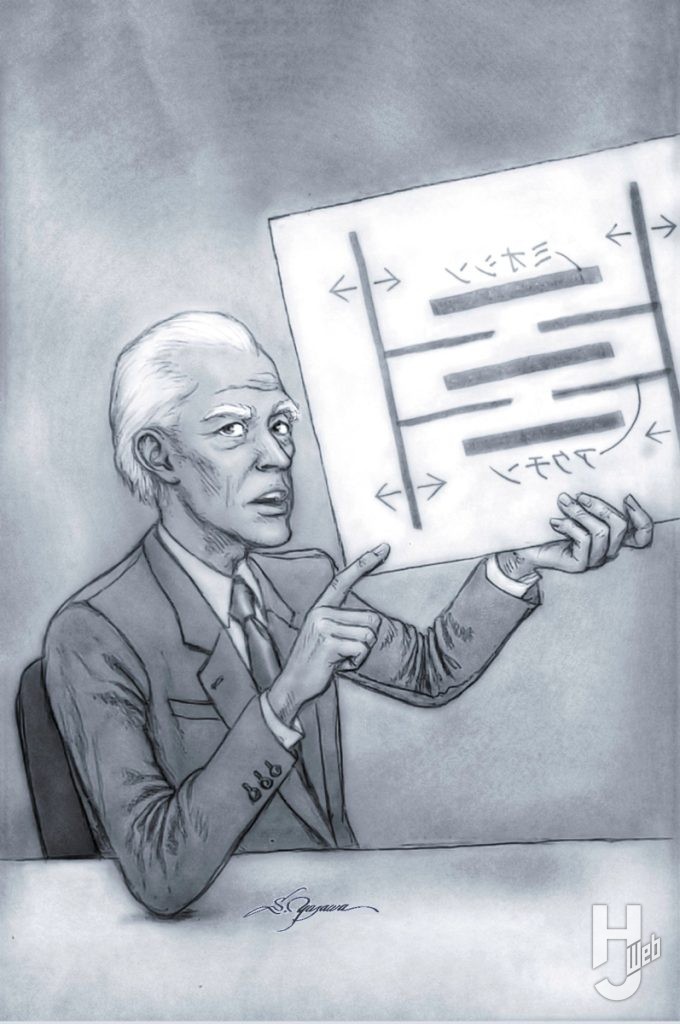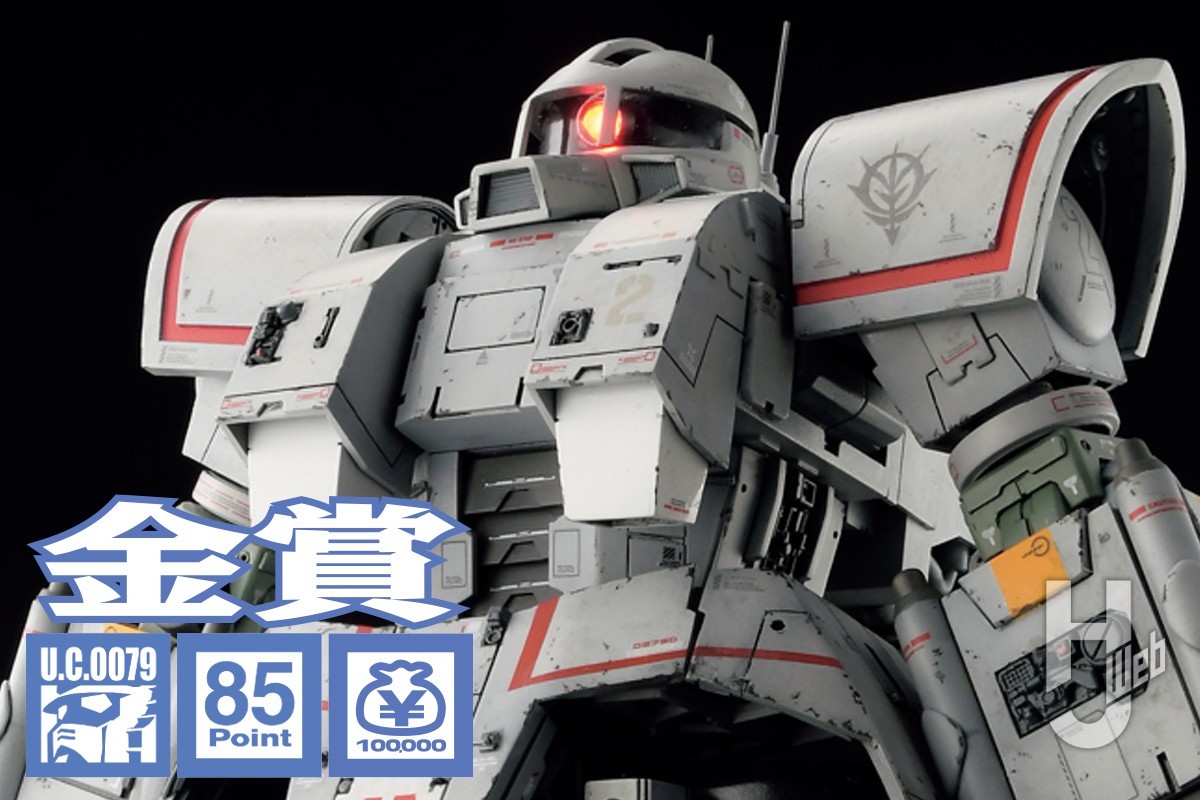【第4回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.09.15マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
ハイテク企業・ハイライン社の社長、鈴木鉄人は、やはり鷲尾の親友、鈴木賢治であった。彼は偶然発生した次元の裂け目から異世界にたどり着くと、自身の優れた頭脳と命ともいえるアイデアノートによってこの世界で成功者となっていた。元の世界に未練の無いという彼を説得し、鷲尾はなんとか元の世界に戻るための協力を取り付けるが、それと引き換えに、現在この世界に広がる存命遺体対策への協力を要請されるのだった……。
原作/歌田年
イラスト/矢沢俊吾
ZIMデザイン/Niθ
第4回
第9章 テレビ討論
おれと美伶は、鈴木のオフィスの上にある居住フロアへ案内され、一室ずつゲストルームをあてがわれた。
室内はビジネスホテルを少し豪華にした感じだった。鈴木の住まいが同じフロアにあり、半分のスペースを占有しているらしい。
内線電話などはなく、おれたちはスマホならぬインテリホンを一台ずつ貸与された。社員は全員持たされているらしい。
シャワーを浴び、備え付けの部屋着に着替えてベッドに腰を下ろすと、最新型のテレビを点けた。
ちょうど漫才番組をやっていた。見ていておれは唖然とした。小柄なボケ役がギャグ──というより単なる言い間違いを連発し、大柄なツッコミ役が相方を殴ったり蹴ったりしている。その都度、観覧席が爆笑の渦に巻き込まれる。元の世界でもどつき漫才はあったが、あの数倍ひどかった。
やがて六時になった。鈴木が出るという番組が始まった。
美伶には、トラウマになるから見ないようにと強く言っておいた。アニメでも観ているようにと念を押すと、美伶は素直に『はい』と言った。この世界にも〝アニメ〟はちゃんとあった。
番組は、夕方のニュースショーの一部を割いてのパネルディスカッションだった。
パネリストは、原田というメガネのベテラン風司会者、桝というひどく痩せた白髪の医学博士、瀬野という髪を赤く染めた若い評論家、川上という年長の太った評論家、そして相変わらずカリスマならぬチャオファン起業家という肩書の鈴木の五人だった。全員男性だ。
パネリストたちの後ろは大型モニターなのかグリーンバック合成なのか、JHKで放映していたものと変わり映えのしない映像が流れていた。とにかくモザイクだらけで要領を得ない。
司会の原田が口火を切る。
『今日の昼頃、内藤新宿で同時に何件もの通り傷的な犯行がありました。最初はテロだと思われましたが、多くの目撃証言によれば、どうも犯人たちの挙動が異常であるとのことでした。──警察は彼らを〝存命遺体〟と呼んでいるそうですが、なぜそんな名称になったんでしょうか。まずはその辺の事情に詳しい鈴木さんにお訊きします。なんでも政府から協力要請があったとか──』
『まあ矛盾してるよね。遺体なのに存命って。日本語おかしいですよ』
と、鈴木でなく評論家の瀬野が指名もされていないのに割って入った。
すると鈴木が被せるように言った。
『他局でも話したのですが──まず第一に、彼らには知性がありません。話しかけても言葉が通じないそうです。次に、死体のように感覚がありません。重傷を受けても何も感じず向かってくるそうです。この二点において、便宜的に〝存命遺体〟と呼んでいるそうですが、暫定的なものかも知れません』
鈴木が坦々と話し終えた。椅子の背に凭れかかり、もう今日の仕事は終わったという顔をしている。
『ありがとうございます。──桝先生、存命遺体の特徴を説明してもらえますか?』
桝博士が口を開く。
『存命遺体は無差別に人を襲います。つまり、捕まえて噛み付くんです。なぜ噛み付くかというと、肉を食べるためです。肉食動物が捕食するのと同じです。その力は常人のそれではありません。物凄い力です。ゴリラ以上だと言われています。そして、どうやら犠牲者もやがて存命遺体に変貌するのです。だから数がどんどん増えていきます』
『なぜ同胞の肉を食べるんですか?』
と、評論家の川上が訊いた。〝同胞〟という言葉に年齢を感じさせる。
『はあ、腹が空いていたのでは』
桝博士が真顔で答えると、何人かがフフフと乾いた笑い声を漏らした。
『まじめにやってください』
と、瀬野が赤い髪を掻いてツッコむ。
『元は普通の人間ですよね。それがなぜ凶暴化したんですか』
と、川上があくまで冷静に訊く。
『考えられるのは、何かの薬物を摂取したか、劇症型の病原体に侵されたか』
『薬物とおっしゃいましたが、それは例えば?』
『どうせシャブですよ。内藤新宿なんだから』
また瀬野が乱暴に言った。どうもバンカラを気取っているらしい。この世界でもシャブはシャブのようだ。
『覚醒剤類を投与されていたなら、攻撃的にもなるし、幻覚に襲われて善悪の判断もつかなかったと考えられます』
と、博士。
『覚醒剤だとしたら、どうすればわかりますか?』
と、川上。
『射った痕を見れば一発じゃないんですか?』
また瀬野が口を挟む。
『注射針痕の確認は確かに有効です。それから、常用者なら解剖してみれば心臓の鬱血でわかります』
『しかしそれでは伝染する理由がわかりませんよね』
と、川上。
『互いに射ち合ったんじゃないんですか』
『こんなに短時間に爆発的に増えるでしょうか』
『カルト集団が一斉にクスリを使ったという可能性も考えられますよ』
『それは何のために?』
パネリストたちが勝手に会話を進める。カメラが慌てて発言者の顔を追う。
『そりゃあ……国家転覆でしょう』
『カルトがですか? ナンセンスだなあ』
と、瀬野が吐き捨てる。
『さて!──次は病原体説についても考えてみたいんですが』
司会の原田が話題を覚せい剤とカルトから逸らす。
『病気ですか?』
と、川上が博士に訊く。
『人が凶暴化する病気というと……』
と、博士が答えかけた。
『狂犬病ですね』
瀬野が得意げに横から言った。
『狂犬病を疑っているんですか? 罹った動物は確かに凶暴になるし、何にでも噛み付くのは事実です。しかし、人間に移った場合の見た目は、せいぜいぐったりしたり痙攣したりするだけですよ。あなたの考えているイメージとは違います。それに、現在の日本では、狂犬病はほとんど考えられませんね』
と、桝博士が真っ向から否定した。
『そ、そうですか……それは勉強不足でした』
瀬野が首を竦めた。
『他には何が考えられますか?』
と、司会の原田が促す。
『あとはうつ病ですか。抗うつ剤の副作用で暴れることはあると思います』
『どうしても薬の話になってしまいますねえ』
と、川上。
『病気だとしたら新しい病気ということになりますね。未知の病原体の存在は忘れない方がいいでしょう』
と、桝博士がまとめた。
『原因の特定はいったん後回しにします。──ところで桝先生、人間というのは一度死んで、そしてまた生き返るものなんですか』
と、原田がメガネの位置を直しながら議題を変えた。
桝博士が苦笑する。
『まあ、仮死状態から復帰するという意味ならもちろん、あると言えますが』
『そりゃそうでしょうね』
と、瀬野が小声でチャチャを入れる。
『いや、質問を変えます。人は死んでも……行動することができますか?』
と、原田。
『行動する──つまり動く、ということかね』
『まあ……はい』
桝博士は虚空を見つめ、頭の中を整理しているように見えた。
やがて、フリップにマジックで何やら殴り書きし、それをデスクに立てると、おもむろに話し始めた。
『まず、人間が動くということをミクロの視点から説明しましょう。──動くということは、筋肉が収縮したり戻ったりすることです。そもそも筋肉は、二種類の微細な繊維、つまり〝アクチン〟と〝ミオシン〟がくっ付いたり離れたりすることで収縮します。ミオシンが、燃料であるATPを分解し、アクチンの方に動くからです』
フリップには何本もの横線が互い違いに描かれていた。
『すいません、〝ATP〟というのは?』
と、原田が訊く。
『失敬。〝アデノシン三リン酸〟のことです。で、そのATPを分解するように仕向けたのはカルシウムイオンで、これがどこから来たかというと、繊維を束ねている膜状の組織からです。これに運動神経を伝ってカルシウムイオンを出せという指令を与えたのは、もちろん脳です。これが〝筋肉が動く〟ということです』
『……』
『……』
ついていけないのか、皆が沈黙する。
『ずっと昔、教科書で読んだ気がしますね』
と、司会の原田が応じた。単に合いの手のようだとおれは思った。
桝博士が続ける。
『心肺が停止してもう動かない状態を〝死んでいる〟と言います。死んだ人間は、脳の活動が止まっています。なぜなら、心肺が動いていなければ血液も酸素も脳に送れないからです。だから、脳から指令を出せなければ、筋肉は動かないわけです。したがって、死者は動きません」
『しかし脳の活動が止まっていても、指令が運動神経に伝達されれば、筋肉は動きますよね』
そう川上が返す。
『理屈ではそうです』
『さて、ここでまた話題を変えます。彼らは素手で殺人をやってのけました。だけど決して格闘家とかアスリートとかいうわけではなく、普通の人々です。彼らの怪力はどう説明がつくのでしょうか』
と、原田。
『それもシャブで説明がつきますよ』
と、頼野。
『まだ言うか』
と、川上。
桝博士が答える。
『人体は、自分で自分を破壊してしまわないように、運動時には自然にブレーキがかかるようになっています。筋肉や関節を壊さないように、実際に出せるパワーよりも小さいパワー──だいたい五○から六○パーセントだと言われていますが──それをマックスだと認識するようにできているんです』
『リミッターだ!』
と、誰かが言った。
『時としてそれが、レッドゾーンに入ることがあります。例えば、〝火事場の馬鹿力〟ですね。緊急避難のための潜在能力の発現です』
なじみのある諺が飛び出し、おれは懐かしさを覚えた。ここにもこの程度の喩えは存在するようだ。いや、実際の出来事に基づいているのかも知れない。
『〝火事場の馬鹿力〟とおっしゃいましたが、なぜ〝存命遺体〟は常に〝火事場の馬鹿力〟を出せるんですかね』
と、川上。
『先程どなたかが仰ったように、リミッターが壊れているんですな』
『それはなぜです?』
『動物は、外敵を前にした時、交感神経が刺激されて臨戦態勢に入ります。そういう状態にあるんでしょう。極めて原始的な状態です』
『つまり彼らは動物だと? 私たちを外敵と認識した?』
と、川上が眉根を寄せた。
『そう言えます』
『いや、動物は必要以上の殺しをしません。ところが人間は必要以上に殺す。人が人を殺し過ぎて、地獄が満員になったんですよ。死者が溢れて、地上を歩くしかないんです……』
と、鈴木が突然発言した。私怨が込められているようだった。『地獄が満員になった』云々はおれが教えたフレーズだ。
鈴木の勢いに場が静まり返った。皆一様にポカンとした表情だ。
『〝ジゴク〟って……何のことですか?』
沈黙が続く放送事故寸前に、瀬野がそうポツリと言った。