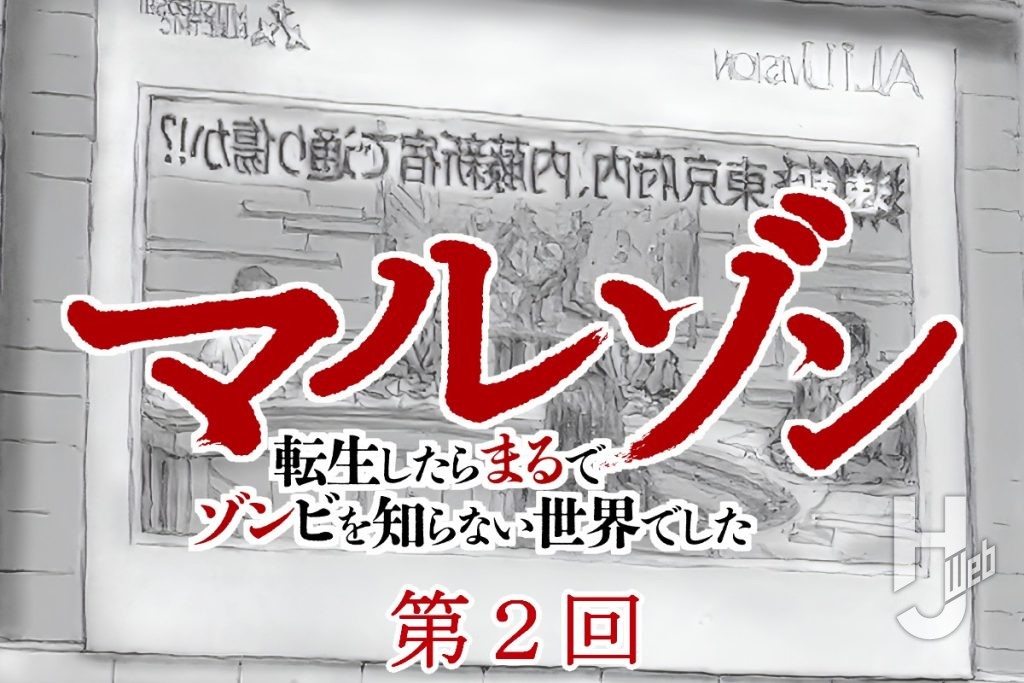【第2回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.09.01マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
入院中の母を見舞いに向かう途中、某国からの突然のミサイル攻撃に遭遇した青年、鷲尾啓介。しかし爆発の衝撃から意識を取り戻した彼が目にしたものは、破壊された街ではなく、すべての文字が反転した奇妙な街、そしてそこで暴れるゾンビだった! 混乱に包まれる街をさまよい、偶然出会った少女、美伶とともになんとか病院にたどりつく鷲尾。だが、病院にもゾンビの脅威は迫っていた……。
原作/歌田年
イラスト/矢沢俊吾
ZIMデザイン/Niθ
第2回
第3章 少女
救急車のサイレンが聴こえる。
おれたちは現場からある程度離れた時点で、薬局を探すことにした。おれのスマホのマップは依然繋がらないが、美伶がだいたいの場所を覚えているという。
「しかし、さっきは怖かったね」
と、おれは言った。
「そんなには……。前にもっとこわいこともあったし……」
と、美伶は速足で歩きながら答えた。
「もっと怖いことって?」
おれの質問に美伶は答えず、ぼそっと呟く。
「あの人たちは、どうして急にああなったのかな……」
「あれはまるで……〝ゾンビ〟だな」
と、思わず答えていた。胸の内に秘めているのが苦しくなってきたからだ。
だが言ってから、しまったと思った。
ゾンビに噛まれたら感染するというのは、その手の映画の常識だ。フィクションとはいえ、噛まれた彼女がそれを意識したら、いよいよ怖がるだろう。
「ゾンビ……って?」
おれの心配をよそに美伶はポカンとした顔で訊き返した。
意外だった。ゾンビを知らないとは。十歳程度ならたいてい知っているはずだと思っていた。
「生ける屍のことだよ」
「イケルシカバネって?」
美伶が小首を傾げる。
「ああ、ごめん。言い方が難し過ぎた。〝生きている死体〟のことだ」
「ええっ? 死体が生きてるわけないです」
「うん。だから、そういう設定のモンスターなんだよ」
そうだ、設定なんだ。現実にあるはずがない。だから心配するな。そう強調したつもりだった。
「モンスター?」
それも知らないのか。
「えーと、怪物のことだ」
「カイブツ?」
「怪物まで知らない? じゃあ怪獣は?」
「カイジュウ……」
今どきの子は、そもそも怪物や怪獣という言い方を知らないのかもしれない。
「そう、怪獣。例えばゴジラとか」
いいぞ。ゾンビから話が横道に逸れてきた。
「クジラ? それともゴリラ?」
ゴジラも無理か。いやまあ、女の子ならそんなものだろう。
「そうじゃない。──クジラみたいにでかくてゴリラみたいな格好をしてるけどね。あれはクジラとゴリラを混ぜた名前だと聞いたことがある」
「そんなの見たことないです」
「映画でも?」
「はい。それで、さっきのゾンビというのがそれなんですか? クジラにもゴリラにも似てないですけど。人が暴れているだけだし」
またゾンビに戻ってしまった。
「混乱してるね……。モンスターとか怪物は大雑把なグループの呼び方だよ。人間が異常な状態にある時もそう呼んだりするということだ。ゾンビはその状態というか……」
「ふーん。難しい……。人間がそのゾンビになるんですか」
美伶の質問は途切れない。
「まあ、そもそもゾンビというのは、映画やマンガやゲームに出てくる架空のキャラクターだ」
念を押しておく。
「カクウのキャラクターって?」
十歳には〝架空〟も難しいか。おれは無い知恵を絞って説明した。
「架空というのは、想像の世界のことだ。想像の意味はわかるよね」
「わかります。頭の中で思ったりすることでしょう」
「まあそうだ。キャラクターはわかるよね」
「……その人の性格、でしょ」
「確かに元はそういう意味だが……」
「〝本当はありえない性格〟ということですか? どうして人間がそうなるんですか?」
美伶なりに頑張って理解しようとしている。
「──とにかく、病気の一種なんだ。感せ……」
おれは〝感染〟と言いかけて言葉を飲み込んだ。
本当に伝染病だったら、やはり噛まれた彼女も感染しているかもしれないと考えるだろう。それを本人に言うのは惨い。
「これはあくまでも架空、想像の話だよ。──人間がある病気にかかると死ぬんだけど、死んだ後で動き出して凶暴化し、暴れ回るんだ」
「狂犬病みたいな感じですか」
実際の狂犬病とは違うが、彼女の質問が核心に近くなってきた。おれはまた軌道修正した。
「いや、それとは全然違う、別物だ。ゾンビはもっと強烈なんだ。ナイフもピストルも効かない。架空のキャラクターだからね」
話を逸らすつもりが、余計な言葉ばかりが口をついて出た。噛まれた少女にゾンビの何たるかをくどくど説明するなんて、馬鹿げている。
「カクウですか。そんな、ありえないものを想像してどうするんですか?」
美伶は意外にも冷静に訊いた。
「それは……楽しむんだよ」
「楽しい……のかな」
美伶という少女はずいぶん現実主義者なんだなと、おれは思った。まあ、そもそも女性は年齢に拘わらず現実主義者なのかもしれないが。
ふと我に返る。並行世界に来て十歳の少女に普通に対応している自分に驚いた。
また新たな救急車のサイレンが近付いた。
話しているうちに薬局に辿り着いた。チェーン店のようだが、聞いたこともない店名だった。
ここではSUICAは使えるだろうか。まずキャッシャーに行き、カードを見せる。「使えますか」と訊く。
「申し訳ありません」
店員は即答した。
「自分で払います」
と美伶は言い、さっさと奥へ入って行った。
おれは追い駆けた。棚を探して消毒薬・ガーゼ・包帯・サージカルテープを探す。
美伶が小さな財布から細かく折り畳んだ紙幣を出して支払った。ちらと見ると確かに肖像の位置が左だった。
店の外へ出ると、バス停のベンチを見つけてそこに座った。
美伶の腕からハンカチを解く。美伶は「痛っ」と小さく声を上げた。
大部分の血は固まっていたが、端が少し開いて再び出血した。いかにも痛々しい。この傷が今後どうなっていくかを想像し、おれは気が滅入った。伝染病でないことを祈るばかりだ。
スプレー式の消毒薬を傷口に噴いた。美伶は可愛い顔をしかめて我慢している。新しいガーゼを当てると手早く包帯を巻き、テープで留める。気休めかもしれないが、何とか処置を終わらせた。
「ひとまずこれでいい。もし痛みが治まらなかったり熱が出たりしたら、近所の医院にでも行った方がいいよ」
我ながら雑な物言いだと思ったが、仕方がない。通りすがりの大人にできることはここまでだ。
「ありがとうございました」
美伶がまたペコリと可愛い頭を下げた。
「じゃあ、また何かあるといけないから駅まで送るよ」
と、おれは言った。正直、少し名残惜しかったのだ。〝吊り橋効果〟みたいなものか。
「はい。お願いします」
おれは相変わらず方向感覚がおかしかったが、美伶が先行するので何も考えずに進むことができた。
つまり、送ってもらったのはおれの方だった。