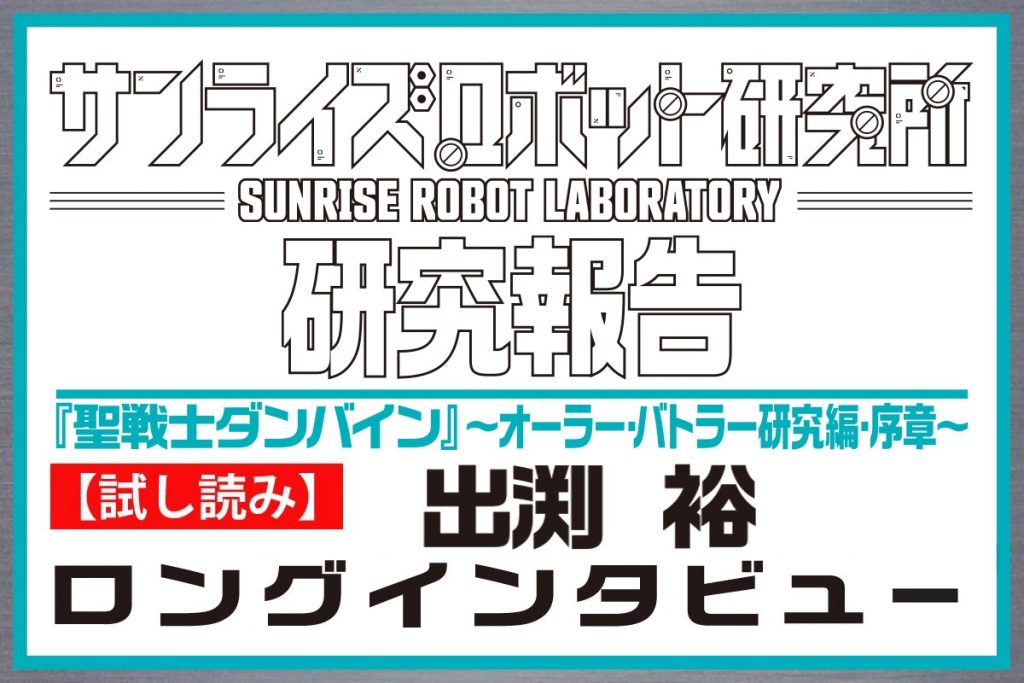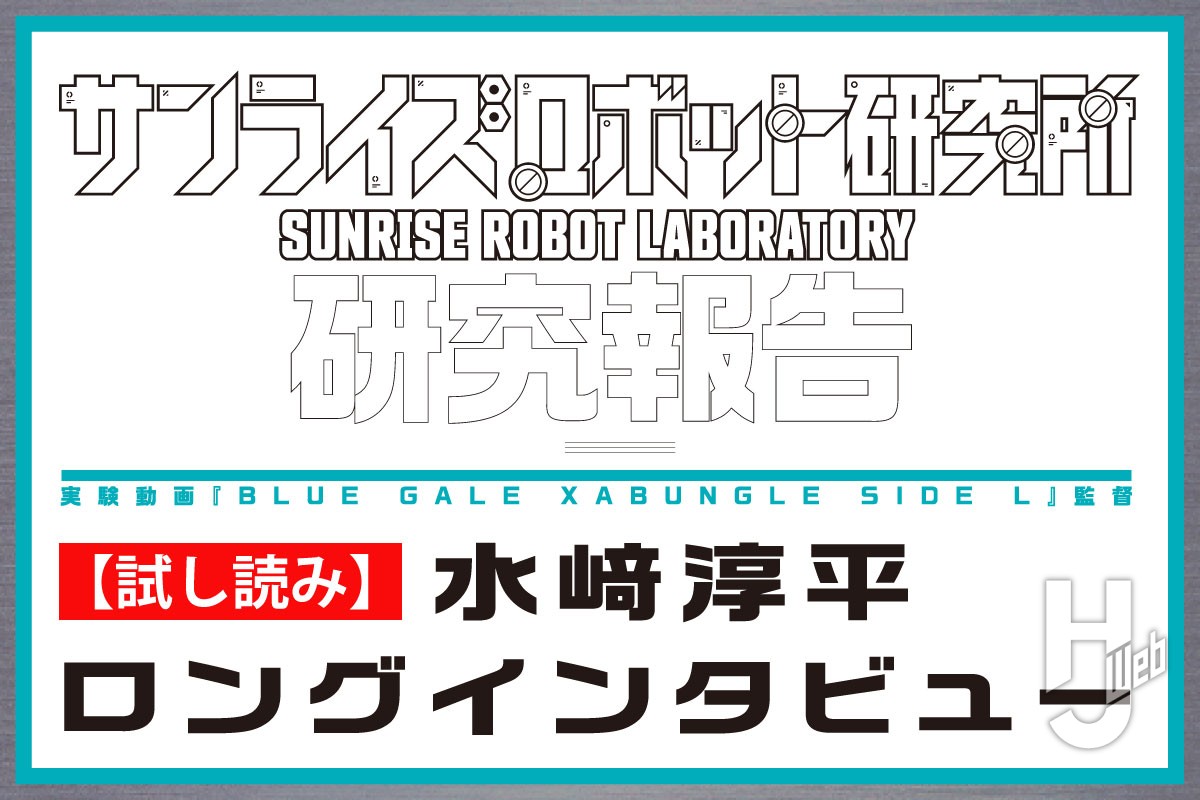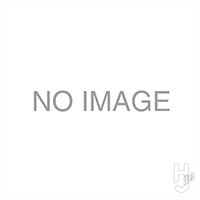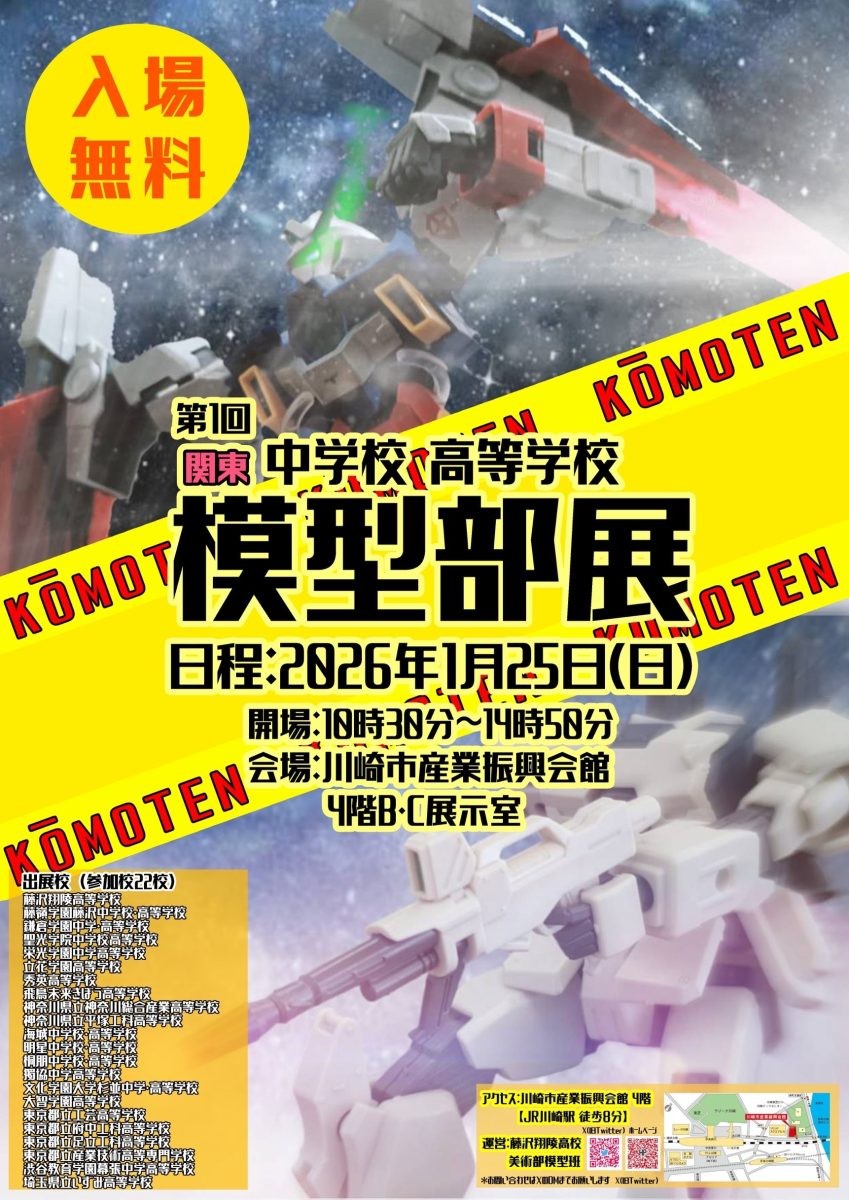【試し読み】出渕裕ロングインタビュー! 『聖戦士ダンバイン』テレビシリーズへの参加の経緯や作品への思いを語る【サンライズロボット研究所 研究報告】
2025.09.03『聖戦士ダンバイン』にメカニカルゲストデザインとしてクレジットされる出渕裕氏へのロングインタビューが実現した。今回はテレビシリーズへの参加の経緯と、当時の仕事や作品に対する思いを、次回からは「B-CLUB」での連載企画『AURA FHANTASM』について、詳しいお話をうかがっていく。
(文:谷崎あきら、取材:五十嵐浩司)
青天の霹靂
──『聖戦士ダンバイン』参加の経緯を教えてください。
企画が動いていること自体は知っていましたが、最初は関わる予定ではありませんでした。『ダンバイン』の設定制作が、『ザブングル』と同じ風間洋さんだったので、会った時に「こんなのやってるよ」「出渕君、好きだと思うよ」と教えてくれて、「いいなあ」と思っていたんです。「宮武(一貴)さんがやっているんだったら、見たいなあ」と。内容というか、世界観みたいなものも断片的にうかがっていたので、どんなふうになるのか期待していました。
──そこから一転、『ダンバイン』に関わることになられたと。
風間さんから「やってくれない?」と言われまして。「え、宮武さんは?」と聞いたら、「いろいろあって」とのことで、そこは正確なところはわからない。青天の霹靂みたいなものでしたよ。空を見上げて「いいなあ」って言っていたら、自分の上に落ちてきたっていう(笑)。言ってみるもんだなと。放映前ではありましたが、フィルムはある程度作り始めていましたので、前半に登場するものについては、僕はあまり関わっていないんですよ。OPに登場するビランビーが、何とか間に合ったというくらいのタイミングでした。あとは、ドロのラフを描いたような気がします。
──オーラ・バトラーに限らず、バイストン・ウェルのさまざまなもののデザインを手掛けられていますね。
宮武さんも、オーラ・シップやグライウイングなどまで描かれていましたから、そのあとを引き継いでほしいということだったんだと思います。ただ、宮武さんが先に描かれたデザインがありますから、それに則って作業したほうがいいのか、違うものを求められているのか、その辺の見極めがつかなくて、最初の頃は観測気球的なラフを描いていた感じはあります。ドロとかは、「これ、ドローメですよね?」と描いたものが要求にドンピシャだったみたいなので、『ライディーン』的なものなのかな? とも思ったんですが、デザインを見るとそれとも違う。昆虫意匠みたいなものが入っているのが特徴的でしたから、そこは継承したほうがいいのかな、とも思いつつ、宮武さんの画稿を見ると、それも怪しい。昆虫にこだわらず、もっと奥深いところで一貫性がある。どう解釈したらいいんだろうと悩みました。そういう意味では、すごいデザインだと思います。
──ビランビーには、宮武さんの原案と富野由悠季監督のラフが残っています。
マサラグですね。その時は宮武さんのものは見てなくて、ダンバインのライバル系ということで、もらった富野ラフに沿ってダンバイン的なフォルムで提出して、それをベースに湖川(友謙)さんがクリンナップされてビランビーになっています。
──それ以降は、基本的にオリジナルでデザインされていたのでしょうか?
最初の頃はとにかく時間がなくて、ビランビーの時のようなラフもなければ細かいオーダーもない。どっちの勢力かわからないけど、とにかく「こんなのどうですか?」っていうのを何枚かダーッと描いたんです。その中から使えそうなものがあったらチョイスして、ビーボォーさんのほうに「これ、何とかして」って投げていた感じだったんじゃないかな。ゲドとかボゾンとかはそうでしたね。ボチューンなんかは、ラフだとあんまり強調したりはしなかったんですけど、「シルエットを変えるにはどうやったらいいんだろう?」と考えながら、鳥脚的な逆関節のニュアンスを入れ、フォルムも鳥型にしてみたりしました。
葛藤と突破口
──ボゾンあたりから、出渕さんの持ち味が発揮されてきたような印象を受けます。
いや、ビランビーの時からそのつもりはあったんですけど、それでも宮武さん風にちょっと戻しているんですよ。これは本当に自分の中でまとまっていないというか、大ラフのイメージスケッチでしか描いていないんだけど、クリンナップを見て「え?」と思ったこともありますし、富野さんや湖川さんから「ぬえ(宮武)を意識しすぎている」と言われたこともあります。「もっと離れていいんだ」という話をされました。とはいえ、先にスタジオぬえのラインがあるわけで、きちんとデザインコンセプトが考えられていて、僕の好きな方向性でもある。それを逸脱していいものか? という葛藤がありました。でも、富野さんも本当は宮武さんのラインとは違うものを求めていた側面があったのかなと思って、ラフ出しで探りを入れたりもしたんです。先ほど「観測気球」と言ったのはそういう意味。その結果、宮崎(駿)さんの『風の谷のナウシカ』に出てくるような、有機的なフォルムのほうなのかなと。あれも王蟲の殻を使って工芸品を作ったりしていますよね。宮武さんの描かれたゼラーナやブル・ベガーって、どちらも昆虫的なシルエットは持っているんですけど、案外むしろメカ寄りで、表面もつるっとしている。コクピットとかキャノピーの部分に、SF的なメカニズム感覚が入ってくるんですね。ゴツゴツ、デコボコっていう感じはあんまりない。なので、ナムワンのラフは意識して、キャノピーの部分などにちょっとバカガラスチックな処理を入れてみた。するとそっちのほうが食いつきがいいんですよ。憶測ですけども、富野さんの中に『ナウシカ』に対する対抗意識があったんじゃないでしょうか。『ナウシカ』っていうと劇場版を思い浮かべるかもしれないけど、漫画版のほうです。「あれを映像化する前に俺がやる!」っていう思いがあったんだと思う。だってグライウイングなんて、まるっきりメーヴェだもの(笑)。
──ビアレス、ライネック、レプラカーン、ズワァースあたりになると、出渕さんのオーラ・バトラーのスタイルが完成していきますね。
後半は、どちらかというと奇をてらった突飛なものではなく、ダンバインのようなスタンダードなタイプの派生型、発展型というイメージでデザインしていたような気がします。ドラムロなんて、量産機ですけど異形ですよね。あの三本爪で剣を持って戦うのは無理があるだろうと。作画だから成立していましたけど、CGなんかだとうまくいかないと思う。デザイン的には面白いんですが、運用の仕方をもっと考えて、重装兵みたいな使い方をするなど、デザインの特性に合わせて兵種を分ければ、もう少し印象が違ったかもしれない。逆にそうした運用上の差を表現しないなら、スタンダードなタイプに収斂していくほうが道理にかなっているのかなと。
・
・
・
■萌芽の時代
■忸怩たる思い
■仕事の広がり
続きは「月刊ホビージャパン2025年10月号」に掲載!
▼ 関連記事はこちら
ⓒSUNRISE ⓒBandai Namco Filmworks Inc. ⓒSOTSU・SUNRISE