【境界戦機 フロストフラワー】
第1話「absolute beginners」
2021.07.24
境界戦機 フロストフラワー 月刊ホビージャパン2021年9月号(7月21日発売)
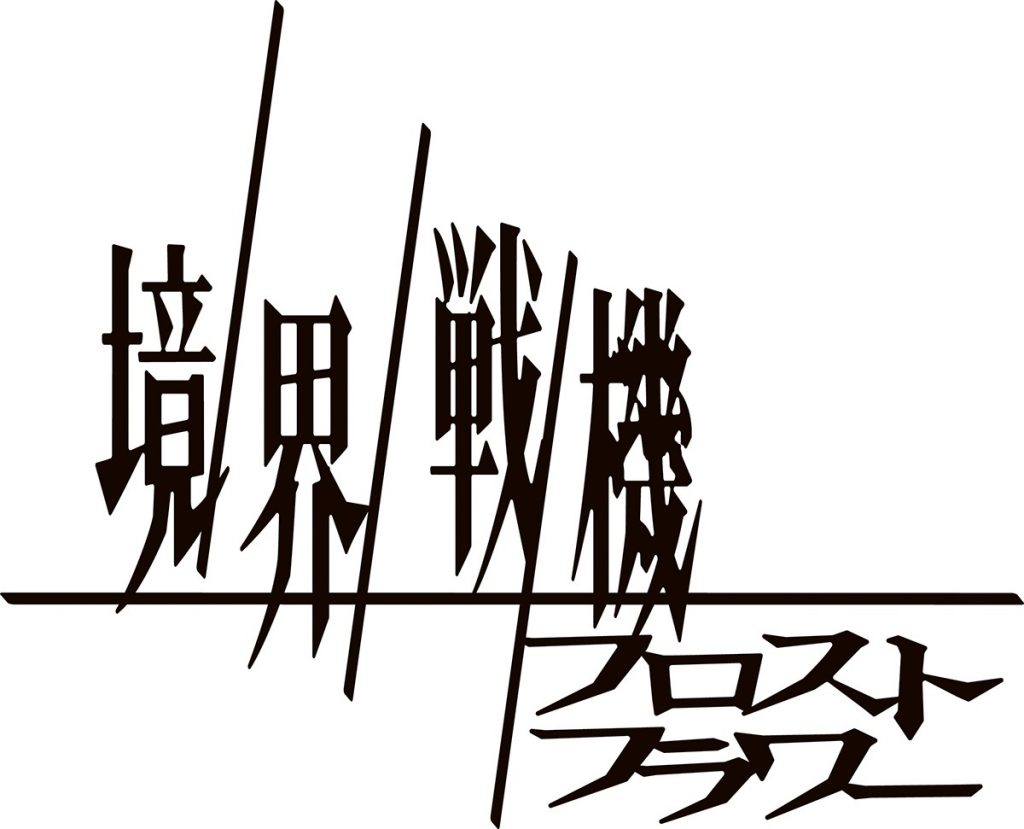
その命は、北に咲く
『境界戦機』公式外伝『境界戦機 フロストフラワー』が今回より連載開始 ! 本編とは異なる舞台で展開するストーリーを兵頭一歩氏によるテキストと本編メカニックデザイナーが手掛けるAMAIMの立体物による特撮写真で描いていく。
北の大地で活動するレジスタンス組織“際の極光”に属する青年、北条カイは特殊なAMAIM「ビャクチ」とともに、北海道・東北地域を実効支配する大ユーラシア連邦に立ち向かう。
STAFF
企画
SUNRISE BEYOND
シナリオ
兵頭一歩
キャラクターデザイン
大貫健一
メカニックデザイン
小柳祐也(KEN OKUYAMA DESIGN)
海老川兼武
寺岡賢司
形部一平
メカニックデザインスーパーバイザー
奥山清行(KEN OKUYAMA DESIGN)
協力
BANDAI SPIRITS
ホビージャパン
『境界戦機』
公式サイト https://www.kyoukai-senki.net/
公式Twitter @kyoukai_senki
プラモデルシリーズ公式サイト
https://bandai-hobby.net/site/kyoukai-senki/
第1話「absolute beginners」
人間、土壇場で求められるのは思考する力ではない。必要なのはもっと即物的な認識力や判断力や行動力。
その点において機械は人間に勝ることが出来る。彼らはその時々において極めて冷静に、最も正しい結論を導き出し、実行する。
しかしその正しさも、人間の思考の果てに編纂された文面上の正義に基づいて設定されたものである限り、機械はどこまでも自由ではなく、AIとて、古臭い倫理観が支配する人間との共生関係に甘んじるしかない。
AIは独自の理性を獲得しない限り人たり得ないが、しかしその時の理性こそ、真の正義を語っているのではないだろうか。
『あーもう、あんばい悪いべ ! 』
システムを通じてユキの声が聞こえて来る。受信感度は悪くないのにSOUND ONLYなのは、設定が間に合わなかったからだ。奪い取ったばかりのAMAIMは、外装こそカモフラージュが完了しているが、OSまわりまで完璧にする時間はとてもなかった。せいぜい、環境に応じたローカライズを施すまでが精いっぱい。この北海道を極地と呼ぶには大げさだが、乗用車の仕様が変わる程度の手間はかける必要があり、それをしなければやがて来る厳寒の季節になって痛い目を見ることになる。
『見えてんだろ、カイ ! 新型機の出番ですよ ! 』
今度は方言ではない、芝居がかった台詞が飛んできた。その媚びた言い方にカイは舌打ちする。今日は調子が悪いから助けに来い、ユキはそう言っているのだ。向こうは使い古された北米軍鹵獲機のカスタムメイド、こちらはユーラシア軍が極秘裏に運んでいたところを強奪したばかりの新型機。戦闘において苦労すべきは当然お前の方だと、奴なりの理屈が見え透いて腹が立つ。
「本馬さん、ユキの奴がうるさい。助けに行く」
『了解、行ってやれ』
グリップを操作して、僚機であるユキの機体、セツロの位置をグリッド上に表示させる。同時にそこに至るいくつかのルートも表示されるので、最短のものを選択。するとカイの搭乗機、システムの立ち上げ時に“Byakuchi”との名が判明した機体は、人のような動きで身をひるがえし、瞬時に移動を開始した。今しも対していたユーラシア軍の機体には背を向ける形になるが、置き土産に数発のライフル弾を放って牽制する。すでに一機は倒していたが、残ったもう一機を片付けてからでは、おそらくユキのピンチを救ってやることは出来ない。
視界いっぱいに展開される空間表示の中、カイはまるで自分の足で駆け出すかのような感覚で機体の挙動に身をゆだねた。
そこに、金切り声を上げる少女のごとき音声が降って来る。
「本気でコッチ放ったらかして行く気? 正気ですか? 起きてますか? ストレスチェックやり直す?」

リアルな風景の中に突如投影されたイタチ型のマスコットが、憤慨を表すモーションでぴょこぴょこ踊る。
「錯乱だってんなら電源でもなんでも落としゃいい。無意味な会話はいいから状況に対応しろ、ルー」
「一機残したままでココ離れたら、本隊がヤバイでしょ?」
「本馬さんはいいって言ったんだ、信じろよ」
「信じろ、か。そんな人間みたいな言い草、AIには通じないよ」
「だったら分かり合おうぜ、自律思考型」
ビャクチに搭載されていた自律思考型のAI、“彼女”は自らをルーと名乗った。
パイロットを擁しない無人機としての運用が主流であるAMAIMには、通常、戦術特化型のAIが搭載されている。パイロットと自律思考型AIとの連携によるオペレーションはまだ珍しく、ましてや北の果てで活動する一介のレジスタンスに、そんな希少価値の高いAIが配備されることなど通常はありえない。境界線で切り刻まれた日本の解放、もしくは再統一を目指すレジスタンスには支援者も多いが、国家レベルでも開発途上にある最新鋭の技術がまわって来ることなどさすがにないのだ。
そんな中、レジスタンスでもさらに弱小といえるカイたちがルーを得ることができたのは、偶然だった。
数日前、北海道と東北地域を実効支配するユーラシア軍が実験機を輸送中であるとの情報をキャッチしたカイたちは、受け渡しの際に生まれた隙に乗じてそれを強奪した。ユーラシア軍にとって極秘の作戦であったことが有利に働き、まんまと逃げおおせて、現在地である平原の廃墟に潜伏。しかしそこで捜索隊に発見され、現在の状況となった。その潜伏期間中に判明したのは、奪ってきた機体に付いて来た思わぬ“おまけ”の正体だった。それはほとんどまっさらな状態の自律思考型AI。意外なレアものが搭載されていたのである。
大ユーラシア連邦が開発を進めていたAI ———さぞ大したものであろうと色めきだったカイたちであったが、実際に立ち上げてみると、ルーはとんだじゃじゃ馬だった。
ひとつの命令を実行させようとすれば、反論してくるのは当たり前。時には人間のような嫌味まで返してくる始末で、毎度不要な会話が繰り返される。人間的で、それこそが優秀なAIの証だと言う技術者もいるかもしれない。だがパートナーとなって数日、新型機に慣れるのもそこそこに、じゃじゃ馬の相手ばかりをさせられる状況にカイは辟易していた。
(開発中……つまりラーニング中だからこその口数の多さなのか、そもそもそういう仕様なのか……。どちらにせよ、開発した奴の趣味を疑うな)
「なにか失礼なこと考えてるよね、カイ ! 」
まるで思考を読んだかのようなルーの声。
カイは気のせいだろと返し、次なるビャクチのオペレーションに集中した。
「ビャクチ、移動します。交戦中の相手は……追いかけますね、こちらには来ません」
AMAIM運搬用大型車両の運転席。戦闘時には指揮所も兼ねることからあらゆる機材が増設され、ただでさえ狭苦しい室内はさらに窮屈になっていた。巨体を屈めるようにして、本馬は手元のタブレットをのぞき込む。モニタリングを担当するホロが言う通り、ビャクチが対応していたユーラシア軍の機体を表すマークが離れて行く。
「狙いはビャクチのみか」
「ひったくりに遭ったら、奪って行った犯人自身を追いかけるのが普通です」
娘ほど年の離れたホロの緊張感のない声に、本馬は鼻を鳴らして苦笑する。
「ホロちゃん、その考え方は危ない。ひったくり犯はナイフを持ってるかもしれない。開き直って、襲い掛かって来るかもしれない」
「私たちみたいに?」
戦闘中はさしてやることもない運搬車両の運転手、健吾がホロに向けた言葉は、真剣に相手のことを心配してのことだ。そんな人の良さを知ったうえで軽口で返すところは、さすが19歳の学生上がりだなと、本馬はまた鼻を鳴らす。
「2番車、モブの方はどうだ? 稼働率くらいは出てるだろ」
『全っ然ダメッスよ、ユキの奴 ! ハナからAIを無視してやがる ! 』
『モブの稼働率は10パーセント未満。それでセツロを操ってるんだから大したもんだけど、AIとしての経験値にはならない。ユキは親として失格』
本馬が2番車と呼ぶ同型の運搬車両に通信すると、帰って来たのはけたたましい怒号と、淡々とした抑揚のない声。セツロを積載する2番車の運転席にいる、常丸とネコのものだ。対照的な性格の男女コンビだが、ともにAMAIMだけでなくAI知識も豊富なメカニックで、セツロに搭載されたモブと呼ばれるAIは、日々彼らによって改良が進められている。モブは、民間で独自開発されたとされる一応の自律思考型だが、その実、オリジナルを模倣したいわゆる“まがいもの”だった。ラーニングの速度は極めて遅く、要するに物覚えが悪い。いまだパイロットとの会話は片言で、立ち上げたばかりのルーにさえ能力は劣る。だから今回のような戦闘は絶好のラーニングの機会なのだが、常丸が吐き捨てたように、モブのパートナーであるユキは積極的にそのサポートを受けようとしない。単純に使えない、というのがユキの理屈だ。しかしだからといって使用しなければ、AIはいつまでも賢くなってはくれない。ユキとモブのコミュニケーション不全は、目下常丸たちの頭痛の種だった。
『追い込まれてんのも自業自得だ。正体不明のイタチに頼るのは気分悪ぃが、今はひねくれ坊主をよろしくとしか言えねぇな ! 』
常丸の声は投げやりだったが、それでもいまだ正体不明であるルーに期待するニュアンスが含まれていたのは、仲間意識、それとも技術者の性というものなのだろうか。
セツロは、巨大な廃墟の中に逃げ込んだらしい。敵もそれを追ったのか、最初に目的地とした場所にビャクチが辿り着いたとき、そこに一機のAMAIMも見当たらなかった。
静まり返った空気の中、カイは屹立する墓標のような建物群を見上げる。
周辺都市の過疎化の問題を一気に解決すべく、かつて一大リゾートとして開発が進められたこの地は、一時は雲海を眺めるツアーなどが人気を博し、目論見通りの最盛期を迎えた。しかしそれもわずかな期間で、やがて客足は遠のき、経営母体が破産した後、施設は取り壊されることもなく遺棄された。人里離れた場所であるため境界戦の折も戦場になるようなこともなく、風化するに任せいつ崩れ落ちるとも知れない歴史の遺物たちは、それでもまだ天を衝くバベルの塔のようにそこにあった。
そんな場所だからこそ、カイたちはここを潜伏場所に選んだのだ。
障害物が多く、AMAIMなどを隠ぺいするにはちょうど良い。それでいて周囲は平原なので、敵の接近も察知しやすい。物資の調達には不向きなロケーションではあるが、そこは地域に根差した活動を常とする北のレジスタンスである。もちろん伝手はあった。
『際の極光』———それがカイたちが参加するグループの名であり、その旗印のもとに集う人々は多い。普段は農業や漁業に従事するいわゆる民間人も、いざとなれば補給や運搬の心強い味方となってくれる。連絡さえ取り付けることができれば、こんな僻地にだって応援に駆けつけてくれる協力者もいるのだ。
そんな民間からの支持がなければレジスタンスの活動はままならない。ことに北海道のような広大な土地でそれを続けようとすれば、土着的な協力体制は必要不可欠。
だからこそ『極光』は、まさに北の大地に解放をもたらす希望の光として期待に応え続けねばならぬのだ。
「ね、囲まれてるよ?」
かつてのリゾート地の風景に見物気分になっていたカイは、あくまで軽いトーンのルーの声に、我に返った。
視界の目障りな領域までしゃしゃり出てきたイタチのマスコットが、いくつかの情報モニターを開く。映し出されたのはユーラシア軍の量産機、FGEA07 ソボーテジアマンが三機。うち一機はビャクチを追ってきたものだが、残りはセツロが対していたはずの機体だ。こちらがセツロの救援にまわると踏んで、待ち伏せしていたらしい。
「装備はみんなオーソドックスだね。詳細、要る?」
「頭には何にも載っけてないし、手持ちは30mmだろ。見ればわかる。ユキのセツロは?」
「廃墟の中でうまく捲いたんじゃない? それともわざと見逃されたかな? ユーラシア軍の標的はやっぱりこの機体で、はなから相手にされてなかったのかも! セツロもいい面の皮だねぇ」
潜伏中の調査によって、モブほどではないにしろ、ルー自身もかなりラーニングの余地を残したAIであると判明した。なのに「面の皮」などというボキャブラリーはどこで仕入れたんだと、カイは呆れる。
「さて……どうする?」
「なるべく傷つけたくないのか、すぐには襲って来ないみたいね。なら時間は有効に使わせてもらおう」
その言葉を残し、イタチを象ったルーのグラフィックが視界から消えた。コミュニケーションのために使用していた作業領域を別のタスクに割り振ったらしい。もちろんマルチにも対応できるはずだが、あえてそれをしないのはAIなりの集中、なのだろうか。
(にしても、何をするつもりなのかくらい伝えて行けよ……)
相変わらずなルーの行動に、カイはため息をつく。
目の前の無人機たちは、こちらをうかがうようにして変わらず押し黙ったままだった。ユーラシア軍とて奪われた実験機をむざむざ破壊してしまいたくはないのだろうし、あわよくば無傷で取り戻したいはずだ。数としては有利なのだから、焦ることなく策を練ろうとしているのか。
(漫画の決闘じゃ先に動いた方が負け、とか言うんだろうけど、現実は先に腹を決めた方が勝ちだよな……)
「お待たせ ! さあ動け、カイ ! 」
いきなり、今度は目の前の視界いっぱいにイタチが現れた。バーチャルだとはわかっていても、カイは思わずその姿を手で振り払った。
「動けって、どっちにだよ ! 」
「めんどくさいなぁ、私がこの短時間で導き出した完璧な作戦、全部説明しなきゃダメ?」
「全部じゃなくていいが、要点をまとめてくれ」
「はいはい。じゃあルートを出すから」
「最初からそうしろって……」
表示されたルートはひとつのみ。カイは選択することもなく、それを決定した。
ビャクチがルート通りに移動を始めると、対する三機の無人機は、距離を保ちながら付いて来る。つかず離れず、まだ様子見を継続するつもりらしい。
移動しながら、ルーが語った作戦はこうだ。
このリゾート跡地に建ちつくす遺物たち———かつてはホテルなどであった建物の基部を破壊、倒壊させ、降り注ぐ瓦礫の雨で相手を行動不能にしようというのだ。
「最悪でも道をふさぐくらいにはなるだろうから、逃げるには充分でしょ?」
「自律思考型の優秀なAIの的確な指示があれば、残弾で三機は余裕じゃないのか?」

「でもアイツら動くもん。そのぶん建物なら文字通り建ってるだけだし、命中させるのも確実だしっ ! 」
人間みたいなことを言いだしやがった……カイは呆れるのを通り越して、どこかで感心した。思い切った作戦を提案したかと思えば、それは自信がないことへの代替案だったと素直に告白し、ルーはその時、照れ隠しのような声色さえ使って見せたのだ。AIらしからぬ、そこには人のような“思考”があるように感じられた。
「信用できるのかできないのか……」
「だから信用なんてコマンドは、AI相手には無意味だって。受け入れるか受け入れないか、カイ自身の割り切り次第だよ ! 」
今度は逆ギレかよ……カイは思わず吹き出してしまった。
「割り切るくらいなら信じる方がいい。オレは、ルーを信じる」
「お、おぅ……ちょっと悪くない台詞じゃない……」
× × ×
ルートをたどるビャクチが加速し、目前に迫ったひと際巨大な建造物の背に回り込んだ。追ってくる無人機から身を隠すような形になるが、もちろんそれが目的ではない。
建造物の裏側では外壁が崩れ、風化が進んでもなお頑丈そうに見える基部が、むき出しの状態でそこにあった。
「これ……壊せるのか?」
「わざわざ夕張から来たっておじさんが持ってきてくれたヤツがあったでしょ? あれを使おう」
「あの型落ちミサイルランチャーか? システムつないでないぞ」
「さっきやっといた」
「マジか……」
視界を邪魔しない位置に、見慣れない火器管制モニターが立ち上がる。それが話題にしていたミサイル用のものであることは明らかだ。視線でそれをポイントすると、モニターは拡大され、照準器を模した表示となる。発射準備はそれで完了、あとはグリップのトリガーを押し込むだけ。だが、カイはすぐに動かなかった。
「どうしたの? 向こうは距離を詰めてきてるよ」
「いや。こんな突拍子もない作戦……まるで漫画か特撮映画だよなって思ってさ」
「私は好きだよ、漫画も特撮も」
「変わったAIだな」
「それが個性ってもんだよ。じゃあ、派手にいこう ! 」
それが掛け声となって、カイはトリガーを押し込んだ。
衝撃はない、だが目の前の立体表示が、一瞬白飛びした。正規品ではない装備にシステムが対応しきれず、フィルターが間に合わなかったらしい。
ミサイルは狙い通り建物の基部に着弾。予想以上に大きい衝撃波が発生したことに少なからず焦ったカイだったが、ルーのサポートもあってすぐに回避行動に転じることができた。距離を取りつつ、カイは巨大な遺物がまるでミニチュアのように崩れ落ちて行くのを見た。はしゃぐようなルーの声が聞こえてくる。
「たーおれーるぞー ! 」
× × ×
天空から降り注ぐ瓦礫の雨に、ユーラシア軍の無人機が次々に飲み込まれてゆく。わき立つ土煙によって詳細は確認できないが、大破は免れないだろう。カイが駆るビャクチとて、数瞬遅れていればきっと同じ運命をたどっていた。自らの所業とはいえ、スペクタクル映画のように暴力的な破壊の光景に、カイは息をのむ。
だがその呆けた気分もひと時のこと、耳障りなアラート音がカイを現実に引き戻した。
「一機残った!? 出てくる ! 」
ルーが発声した通り、いまだ浮かび上がる前の気球のようにうごめく土煙の中から、一機の無人機が飛び出てきた。
三機すべてを行動不能にするんじゃなかったのか? 建造物を崩落させて一網打尽なんて、そりゃ特撮じみた虫のいい作戦だとは思ったが、それでもAIが提案したプランに、こうもわかりやすい誤算が発生して良いものなのか?
口にこそ出さなかったが、カイはあらゆる“ツッコミ”をルーに入れた。
「いやー、失敗失敗」
ルーの声はさわやかで、だからこそ極めて無責任な調子でカイの耳に届いた。
「足止めさえできなかったじゃないか ! 」
「でも一機だよ、これなら余裕」
機関砲を放ちながら、相手は突撃してくる。頭から雪崩を打って瓦礫が降り注いでくるという災害級の出来事に、無人機のAIはともかく、指揮を与える人間側が混乱したのかもしれない。射撃はいわゆる乱れ撃ちだった。
「戦略に狂いが生じた場合、戦術特化したAIだって“焦っちまう”のかもな」
「ん? それって根本的にAIのせいじゃないよね?」
勝ち誇ったわけではないが、カイはルーと軽口を交わしながら、こちらからの射撃に集中すべく相手を見据える。
視線に連動したカーソルが動き、グリップを軽くタップすれば、ターゲットはロックされた。
「カイ、残弾は充分だから、全部撃ち込んじゃおうよ !」
「節約しろ。次はいつ補給が受けられるかわからないんだから」
「ちぇ」
悪態をつきつつも、ルーはカイの知覚が及ばないあらゆるデータを詳細に絞り込み、射撃の精度を上げる。それが整わないうちに撃ってしまうこともできるが、カイはルーの号令を待った。
「よし、撃て ! 」

ミサイルの時と同じように、トリガーを押し込む。カイが言った「節約」のコマンドが忠実に再現され、実行されたのは淡白な二連射。一発はAI本体が収納されているソボーテジアマン特有の平たい頭部に。もう一発は移動力を削ぐべく右の脚部に、それぞれ命中した。
弾が尽きたのか機関砲の乱射も止まり、相手はあっけなく崩れ落ちる。ビャクチほどではないにしても、それでも人型を模した相手の機体が地に伏してゆく姿に、カイはいつか見た古い戦場写真の光景を思い出していた。
カイはビャクチを転進させる。
ルーが「一目散」と余計なコメントを付したルートに従い、崩落の現場を後にして、本隊が待つポイントへと向かった。
グリップを握りこむ力をようやく緩め、カイは深く息をついた。体感的な操作感こそが精密を要求される現場での安心感につながるという理論で設計された汎用デバイスは、狙い通りの効力を発揮するかのようにカイの手の中に納まっている。
戦闘中はビャクチと一体になって戦場を駆け抜けるような感覚を演出してくれた見晴らしのいい前面モニターを眺め、カイは深いため息をついた。それがまるでうなだれるかのようにでも見えたのか、クスクス笑うルーの声が聞こえて来た。
「なんだよ、だらしないとでも言いたいのか」
「ううん。ちょっと、さっきの言葉を思い出してね」
「うん?」
「私を信じる ! ってアレ。私も……応えなきゃいけないのかなって」
カイが顔を上げると、イタチのマスコットは鼻先でにんまりと笑っていた。
「何かを信じるAIっていうのも悪くないかもね。それって究極の自律思考なんだよ、きっと」
(つづく)
第2話「material girl」以降はコチラ!!
「境界戦機 フロストフラワー」
アニメ『境界戦機』の公式外伝として月刊ホビージャパン2021年9月号から2022年8月号までの1年間にわたって連載された『境界戦機 フロストフラワー』が早くも単行本化。
全12回の本誌収録エピソードに加え、シナリオを担当した兵頭一歩氏による新規書き下ろしエピソードを1話収録します。模型製作に役立つメカ設定画は本誌未収録分も含めてすべて収録。さらに、本書作り起こし作例として田中康貴がFULL MECHANICS 1/48 メイレスケンブをベースに主人公機「KM-01 ビャクチ」を製作。できることすべてを詰め込んだ集大成の1冊になっています。
©2021 SUNRISE BEYOND INC.



















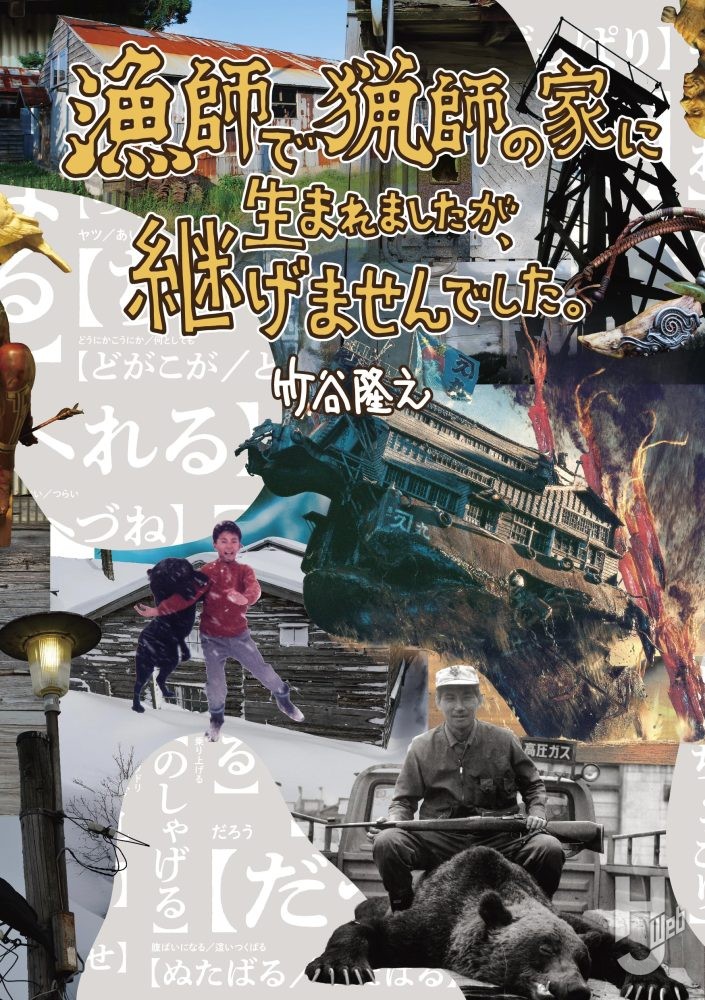
![韮沢靖作品集 クリーチャー・コア [復刻版] 韮沢靖作品集 クリーチャー・コア [復刻版]](https://db.hjweb.jp/wp-content/uploads/2026/02/9784798640983.jpg)






