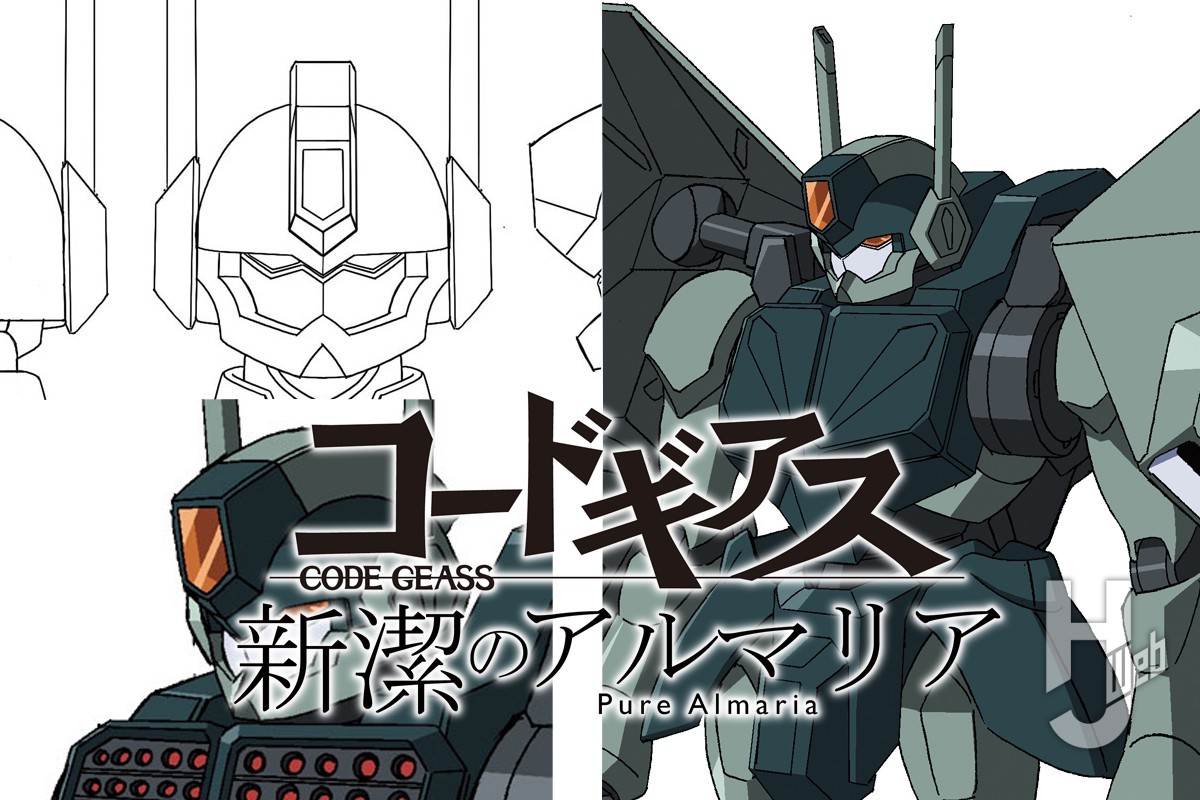【最終回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.11.10マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
東京で爆増したマルゾンを薬品で溶かして一掃するという「ハーメルン作戦」。しかし、その実態は、かつて鈴木がこの世界にやってきた時空の裂け目を利用し、鷲尾たちが本来いた世界へマルゾンを送り込むという恐ろしい作戦だった。真相を知り作戦の中止を求めて鈴木を訪ねる鷲尾。だが彼の説得は実らず、さらに鷲尾に同行していた警予隊の上野の凶行によって鈴木は命を落としてしまう。もはやすべての望みは絶たれたのか? 作戦遂行の時間は迫っていた。
原作/歌田年
イラスト/矢沢俊吾
ZIMデザイン/Niθ
最終回
第33章 阻止
美伶ちゃん
おれは今夜、大仕事を終わらせたら、故郷に帰るつもりだ。
実はおれは、別の世界から来た人間なんだ。並行世界の一つだ。
宇宙には、にているようで少しちがう並行世界というものがいくつもあるらしい。
ある日、新宿にミサイルが落ちて、おれはばくはつで飛ばされてここに来た。
いや、君にはちょっとむずかしいかな。
二子玉川のあの処理場は、アンディが言ったとおり秘密があった。しかもおれの故郷にとってひどい害をおよぼすことになる。
だからこわしてしまうんだ。
その後すぐに、おれは故郷へ帰る。〝ハーメルンの笛ふき男〟にみちびかれて、おれは穴の中へと入って行くよ。そこが元の世界への入口なんだ。
でもこれは二人だけの秘密だ。誰にも言ってはいけない。
短い間だったけど、楽しかったよ。ありがとう。
それから、君はブスなんかじゃない。とても美人だ。自信を持っていいと思う。
それでは、さようなら。
ゴリ(わしおけいすけ)
おれは、もう眠っているはずの美伶のインテリホンにメッセージを残した。
既に病院の外にいた。
再びこっそり抜け出したのだ。
次いで、サトーコーポレーションの代表番号に電話をかけた。業務終了を告げる自動音声が流れてきた。既に午後一〇時を回っているので当然だろう。
おれはインテリホンに取り込んでおいた名刺のデータから、佐藤社長のメールアドレスを呼び出した。身分と、緊急に会いたい旨を手短にメールする。
五分と待たずに返信がきた。佐藤社長はまだ社にいるらしい。鈴木と同じく仕事人間だ。もちろん用件を訊かれたが、直接話したいとだけ答えておいた。
すぐまた返信がきた。
『弊社にてお待ちします。』
さすが話が早い。おれは、すぐに伺うと返した。
大通りでタクシーを拾い、まっすぐサトーコーポレーションへ向かう。運転手は社名を言っただけで御茶ノ水に進路をとった。
既に封鎖されている二四六号は使えないので横道を通り、皇居をぐるりと左回りに回って三〇分ほどで着いた。時計を見ると午後一〇時四〇分だった。
聖橋からほど近い場所にある真新しい高層ビルが目的地だった。
ふと気になってタクシーの運転手に「あれは〈聖橋〉ですよね」と確かめると、「いや、〈ヤノスケ橋〉ですよ」と言った。
ビルの入口で守衛に身分と名を告げる。
鈴木が死に、その元社員が数時間後にライバル会社にいたとなると、おれ自身はともかく、佐藤社長は後々まずい立場に置かれるのではないか。今更ながらに心配になった。
しかしおれはあっさりと二十三階の社長室に通された。
そこは驚くほどハインライン社の社長室に似ていた。すなわち成金趣味だ。窓からの夜景もやはり素晴らしい。室内に流れている音楽はアンビエント系。これらもスパイからの情報を基にしているのだろうか。
促されて応接セットに座る。
「大変だったようですね……」
朝の出社前ではないかと思うほどパリッとしたスーツ姿の佐藤社長は開口一番そう言った。
やはり鈴木のことは既に耳に入っているのだ。説明の必要はなさそうだ。
「〈存対〉以来のご無沙汰です」
佐藤社長は軽く顎を引いた。
「──最初に言っておきますが今回のことは私の差し金ではありませんよ。私は鈴木社長を尊敬していた。あんな独創性のある人はいない。だからずっと彼の真似をしていたんです。これからもずっとずっと追い駆けたいと思っていた。だから死んで欲しいと考えたことなどありません」
謀殺を勘ぐられていると思っていたのか。
「もちろん、そんなことは思っていません」
「それはよかった」
佐藤は特に安堵した風もなく言うと、酒棚の方へ歩み寄った。やることまで鈴木と同じだ。
「おれは結構です」
と、先手を打つ。
「では、勝手にやります」
佐藤社長は自分でオン・ザ・ロックスを作った。
「──今日は佐藤社長にお願いがあって来ました。いや、耳寄りな提案と言いましょうか」
と、おれは切り出した。
「ほう、それはまた異な。かつてライバル会社にいた人が私に提案とは、尋常な事態ではないですね」
佐藤社長は古臭い言い回しが好きなようだ。
「単刀直入に言います。──明日行われる〈ハーメルン作戦〉を潰したいと思いませんか。佐藤社長にとっては、ハインライン社に手柄を取られるのは癪なんじゃないかと思いまして」
佐藤社長の片眉がピクリと上がった。グラスを口に運ぶ。
「人聞きの悪い。──本気ですか」
「大本気です」
「それはどういう理由から?」
当然の質問だ。
「おれは……元は人だったマルゾン──存命遺体があんな風に……廃棄物のように葬られるのが許せないんです。だから、どうしても〈ハーメルン作戦〉を阻止しなくてはならないんです」
車中で用意しておいた偽りの理由を口にした。いや……半分は本心でもある。
真の理由は絶対に教えるわけにはいかなかった。佐藤社長が〝時空の裂け目〟の存在を知ったら、何を企むかわからないからだ。
「なるほど」
と、佐藤社長は表情を変えずに言った。
「その代わり、社長のS.A.T.O.で必ず全てのマルゾンを一体一体葬ってあげてください!」
そう言って、おれは次の言葉を待った。
「──鈴木社長には中止を願い出たのですか? 彼はどういう反応を?」
「……聴く耳を持ってくれませんでした」
「それで──殺したのですか」
と言ってから、今度は片方の口角を微かに上げた。
「それこそ人聞きが悪い。あれは事故です。それに、鈴木社長がどうなろうとも作戦はもはや自動的に遂行されると聞きました。しかし他の〈存対〉メンバーを説得しようにも時間がなく、こうして佐藤社長を頼って来たというわけです」
佐藤社長がグラスを振って氷を鳴らした。
「ふむ……で、どのようにやろうと考えているのですか」
「やることは単純です。二子玉川の処理施設を完全に破壊し、特殊薬品も全て廃棄してしまいます。そこで、建物と連絡橋を粉々にすることができるだけの爆薬を調達して欲しいんです。──それとS.A.T.O.を一機お借りしたい」
佐藤社長の片眉がまた吊り上がった。
「ずいぶん乱暴な話ですね。でも、それで施設を永久に葬れるわけではないでしょう」
「ここでミソなのは溶解用の特殊薬品です。鈴木社長の独自ルートでしか入手できません。そしてルートは機密とされています。社長亡き後、入手するのはもう困難かと」
佐藤社長は右目をピクつかせた。特殊薬品に興味は示したのだろうか。だが、いくら調べてもそんなものは存在しない。
「もし……あなたが逮捕されて取り調べを受けたら、私の身が危なくなりますが」
と、薬品のことには触れずに佐藤社長は言った。
「それはご心配無く。おれは永久に消えますので」
「永久?……死ぬ、ということですか」
佐藤社長はさらりと訊いた。
「いえ、そのつもりはありません。ちゃんと逃げます」
「では逃亡の手助けもしろと?」
「それは自分で何とかします。もう手筈は整っています」
「失敗したらどうしますか」
「絶対に成功させます。──させなくてはいけないんです」
「すると、あなたは絶対に失敗せず、逮捕もされず、必ず逃げおおせて見せると。その保証はありますか?」
「……ありません。信じてもらうしかないです。このとおりです」
おれは頭を下げた。
佐藤社長は尖った顎を撫でながらしばらく考えていた。
やがて思い出したようにグラスの酒を眺め、飲み干した。
「──鈴木社長はとことんついていないですね……人生最後の大事業まで失敗するなんて」
「と言うと……」
「何とかしましょう」
「ありがとうございます!」
おれは再び勢いよく頭を下げた。
「〝ライバル〟という言葉はラテン語の『小川』が語源だそうですね。そこから派生し、川を取り合う人々という意味になったといいます」
佐藤社長はそう言いながらデスクに戻り、内線電話を取り上げて何事かを囁いた。
川か……。おれたちが挑もうとしているのは、まさに〝川取り合戦〟だ。
しばらくして社長室のドアが開いた。
入って来たのは見慣れた顔だった。
「押忍」
ジャージ姿の猿座だ。
やはり出てきたか。
つゆほどだが予期はしていた。それにしても猿座までまだ在社していたとは。
「傷はまだ痛むか」
と、猿座は言った。
「当たり前だ」
「すまんね」
相変わらず、少しもすまなそうではない。
「この人が〈ハーメルン作戦〉を阻止したいそうです。協力してあげてください」
と、佐藤社長は生真面目な声で言った。
「押忍、了解です」
猿座はこともなげに返事をした。
「具体的には、二子玉川の処理施設と新設の連絡橋を爆破したいらしいのです」
「ああ、あそこですか。外観だけなら先日見て来ましたよ。大した建物じゃない。ダイナマイトはウチの関連会社で扱っているから調達は簡単ですが、まあ足が付きやすい。自分なら警予隊からC-4を盗んだ方が早いし、楽です。──あの建屋は脚が六本程度だから、M5A1を……三十六本。建屋自体には……三十本。連絡橋には……八十四本か。合計で──百五十本。余裕を見て百六十本。立川駐屯地なら難なく持ち出せるでしょう」
猿座は直立不動のまま一気に言った。癪だが、さすがだ。
〝C-4〟とは世界的にポピュラーな軍用プラスティック爆薬のことだ。元の世界では陸自も使っていると聞いたことがある。
「今夜中に調達と実行ができますか? 〈ハーメルン作戦〉開始は明くる六時だそうですが、関係者は四時くらいからスタンバイしているらしい。無駄な殺生は避けたいから、それ以前に終わらせましょう」
佐藤社長はまたさらりと〝無駄な殺生〟という言葉を使った。仏教用語ではなかったか。単に人間と家畜を区別していないだけか。
「了解です」
「それと、S.A.T.O.を使いなさい。この鷲尾氏にも貸与します。だが、うちの関与を匂わせてはいけません」
「了解です。そちらも特装機から盗んだ格好にしましょう。富士から予備を持って来させます」
佐藤社長は頷いた。
「強制解除パスコードで何とかなるでしょう。それと、人員はどうしますか」
おれが逮捕されることを心配していた人とは思えなかった。猿座を始め、人員を貸し出すつもりだ。佐藤社長もまた、自信があるのだろう。
「鷲尾氏と自分の二人で充分です。余計にいるとコントロールが難しいし、口止めも徹底できません」
と、猿座は言った。
「そうですか。では頼みました」
ことは、おれの目の前で勝手に忙しなく進んでいった。