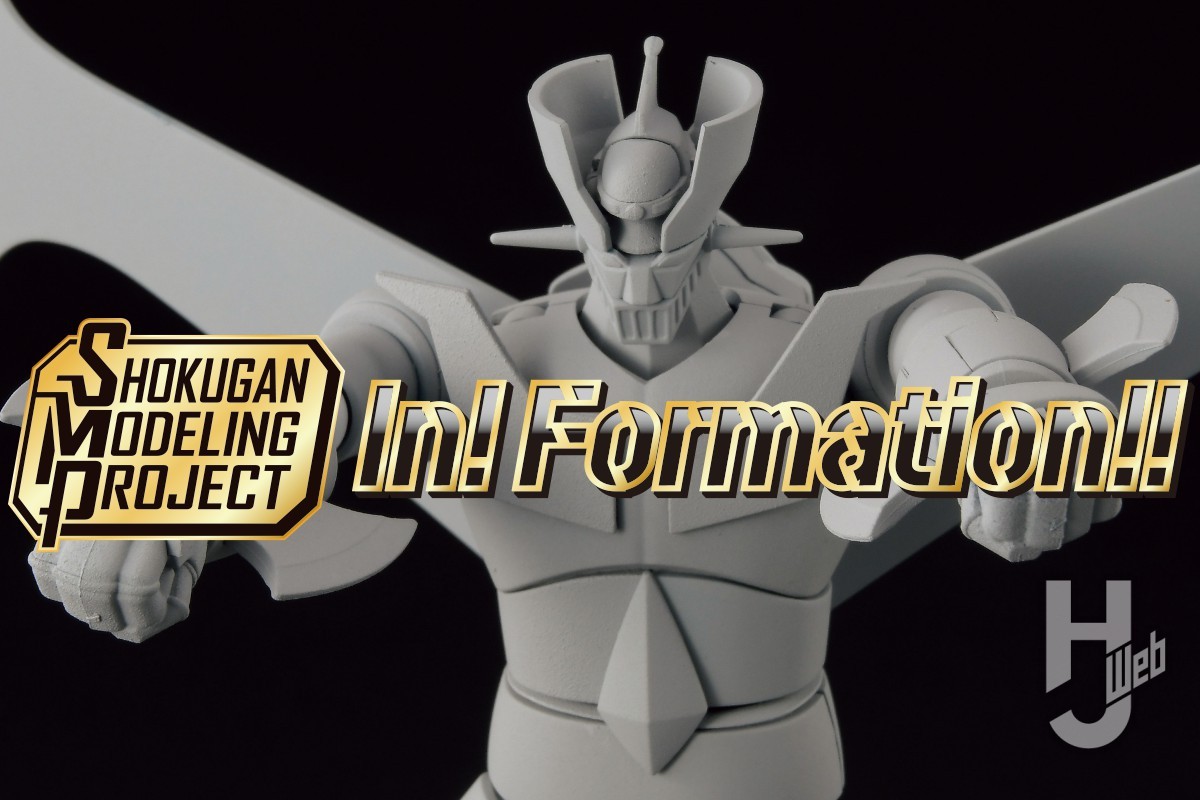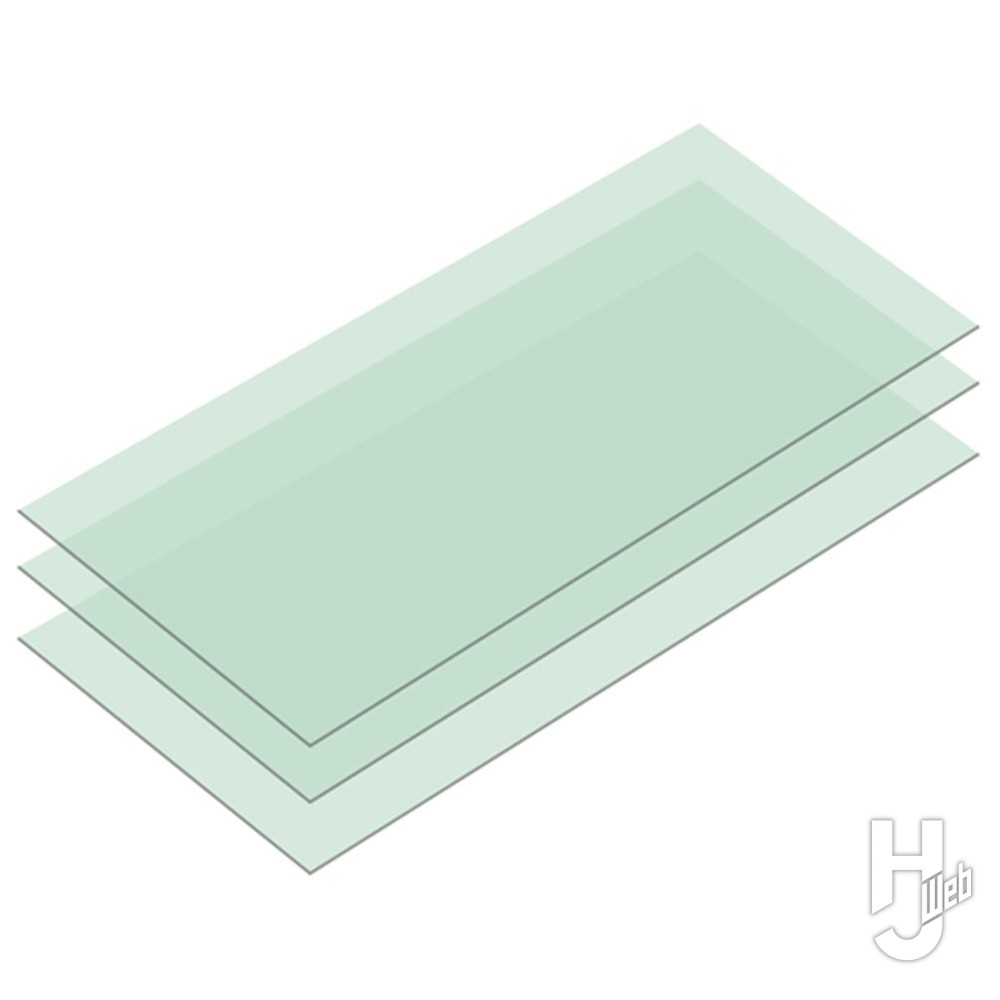【第4回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.09.15マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
第11章 美伶の忠告
人生最長と思えた一日が終わり、おれは部屋に戻るとすぐベッドにひっくり返って眠りに落ちた。
しかし寝ている間はほとんど悪夢にうなされていた気がする。細かいことは覚えていないが、人々が先に行ってしまい、自分だけ置いてけぼりにされているような夢だった。
やっと落ち着いて深い眠りに入ったと思ったら、インテリホンのアラームで起こされた。
もう朝が来ていたのだ。
大汗をかいて目覚めたおれは、最初は現実を認識できなかった。目に入ったのはいわゆる〝見知らぬ天井〟だ……。だがすぐに、異世界にいることを思い出して暗い気分になった。
それでもシャワーを浴びるといくぶん気分も回復し、借りたワイシャツとスラックスに着替えた。リクルートスタイルに見え、サラリーマンになった気がした。経験は無いが。
受付で訊くと、美伶はとっくに社員食堂でフリーの朝食を摂り、社内図書室で過ごしているという。
おれも社員食堂に立ち寄ってサンドウイッチとコーヒーを受け取ると、隣接する図書室を覗いてみた。
美伶が一人ぽつねんとテーブルに向かっていた。昨日と同じ白いパーカーを着ている。
「おはよう」
と、おれは声をかけた。
「あ、おはようございます!」
美伶は快活に答えた。おれとはだいぶ気分が違うらしい。
「よく眠れたかい?」
「はい。もうグッスリ!」
「腕の怪我の方は?」
「まだちょっと痛いです」
「そりゃそうだよね。──独りで過ごしていて寂しくないのかい?」
「はい。いつもひとりだから、全然!」
傍らに積んである本の背表紙を見てみると、科学や工学系の専門書ばかりだった。『人造人間入門』『オートマタ工学』『キベルニクス序説』エトセトラ、エトセトラ。
鈴木らしい蔵書だ。
「マンガ本は無かったのかい?」
と、おれは訊いた。
「はい。でも面白い本がいっぱい!」
と、美伶は瞳をキラキラ輝かせながら言った。
「こんなの読むのかい」
「はい。わたし、理科とかは好きなんです」
「へえ」
「理系女子か」
「なんですか、それ」
「いや、何でもない。……じゃあ、おれは仕事の話をしに行ってくるよ」
「はい。行ってらっしゃい」
美伶が手をひらひらさせて言った。
おれは図書室を後にし、社長室へ向かった。
鈴木との会話は昨日と大差なく、いくつかの指示を受けたおれは小会議室に席を借りた。
ノート型のパソコンならぬマイコンを一台あてがわれた。もちろん表示は左右反転していたが、設定でさらに反転できるようになっていたので問題は無かった。鈴木独自開発の機能だろうか。
おれは3D設計ソフトの使い方を一から学ぶ必要があったが、二日でなんとかやってのけた。記憶を総動員して、かつて描いたデザイン画に忠実な図面を描き上げた。
基本イメージはいわゆる『宇宙の戦士』のパワードスーツだが、存命遺体の伝染性を考慮して防疫を優先しており、完全密閉式の深海作業服に近い。ヘルメットは同原作のアバロンヒル社の古のボードゲームの箱絵に敬意を表して球体にしてみた。
装甲は時速七〇キロで走る自動車と衝突しても壊れない。
もちろん小説のような核バズーカやグレネードランチャーやジェットエンジン、ロケットエンジンは無い。
だが、シルエットをいかにゴリラに似せるかという点だけは忠実に守った。我ながらバカである。
「すごいじゃないか! 期待以上だ」
おれの図面を一目見て、鈴木は喜んだ。ガワだけとはいえ、試作品の製造には超特急でかかっても四日は要するとのことだった。
その間、おれは連日RICOを使ってパワードスケルトンの性能を試してみた。三日で完全に一体感を得ることができた。
一方、美伶はというと、図書室に籠りっきりでひたすら専門書を読みふけり、さらに教養番組の録画を観ていた。
おれも手持ち無沙汰になった時は、図書室を覗いてみた。といって、鏡文字で印刷された文章を読む気はおきない。頭が痛くなる。図版の多い本を探してはぼんやり眺めていた。
「鷲尾さんて、鉄人さんに〝ゴリ〟って呼ばれてるんですね」
不意に美伶が言った。
「ふふふ。昔の渾名だよ。お恥ずかしい」
「えっ。〝ゴリ〟ってゴリラのことでしょ。かっこいいじゃないですか」
「そうかな」
「わたしも鷲尾さんのこと、ゴリさんて呼んでいいですか?」
「え、別にいいけど……」
「じゃあ、ゴリさん」
「はい」
おれが片手を挙げて答えると、美伶が嬉しそうに笑った。
「──ゴリさんて、お家はどこなんですか?」
「えーと……川崎市の方なんだ」
確認はしていないが、こっちにも川崎はあるよな。
「そんなに遠くないですよね。なんでここに泊まっているんですか? わたしみたいに家に帰りたくないの?」
「いや……仕事をもらったから、集中して取り組むためだよ」
「ああそうか。〝パワードスーツ〟でしたっけ」
「そうだ」
「なんでスーツ──服っていうんですか」
「着るからだよ」
「パワードスーツって機械ですよね。機械を着るんですか」
「そうだよ」
「そんなことできるんですか。硬くないんですか」
「外は硬いけど、内側は軟らかいんだ」
「ふーん」
美伶は納得していない顔だ。やはり〝喩え〟が通じにくい。
「ゴリさんは、彼女さんっているんですか?」
いきなりな質問だった。女の子らしいといえばらしいが。
しかし何と答えればいいだろう。
「まあ、いるけど……遠い所に住んでいるんだ」
「やっぱりいるんだ……じゃあ遠距離恋愛ですね。どういう風に出会ったんですか?」
これも答えづらい質問だった。
「……インターネットの専用サイトにプロフィールを登録しておくと、知り合いたいと言う人が連絡してくるんだ。で、何回かメールでやりとりした後、いいかもと思ったら、実際に会って、本当にフィーリングが合えば付き合いを始めるという──」
「それって、〝出会い系サイト〟じゃないですか。ゴリさんはモテそうなのに、なんでそんなの利用するんですか?」
ここにも〝出会い系サイト〟という名称があり、十歳の少女でも知っていた。しかし美伶は妙なことを言った。
「いやいや、この顔でモテるわけがない」
「うそばっかり。もしかしたらゲームのつもりなんですか」
「そんなことはない、本当だよ。モテないから出会い系しかないんだ」
言っていて我ながら情けなくなった。美伶は、何か他に問題でもあるのではないかと、探るような上目使いの視線をおれに寄越した。
「……でも、そんなやり方で出会った相手なんて、信用できるんですか? その女の人は何か下心があって近付いて来たのかも」
「君もそう思うのか」
「ゼッタイ気を付けた方がいいです!」
美伶はまるでおれの保護者であるかのように、まなじりを上げてキッパリと言った。
つづく
この物語はフィクションであり、実在する人物・団体等とは一切関係がありません。
【マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした】
第4回 new ←いまココ
\オススメブック!!/