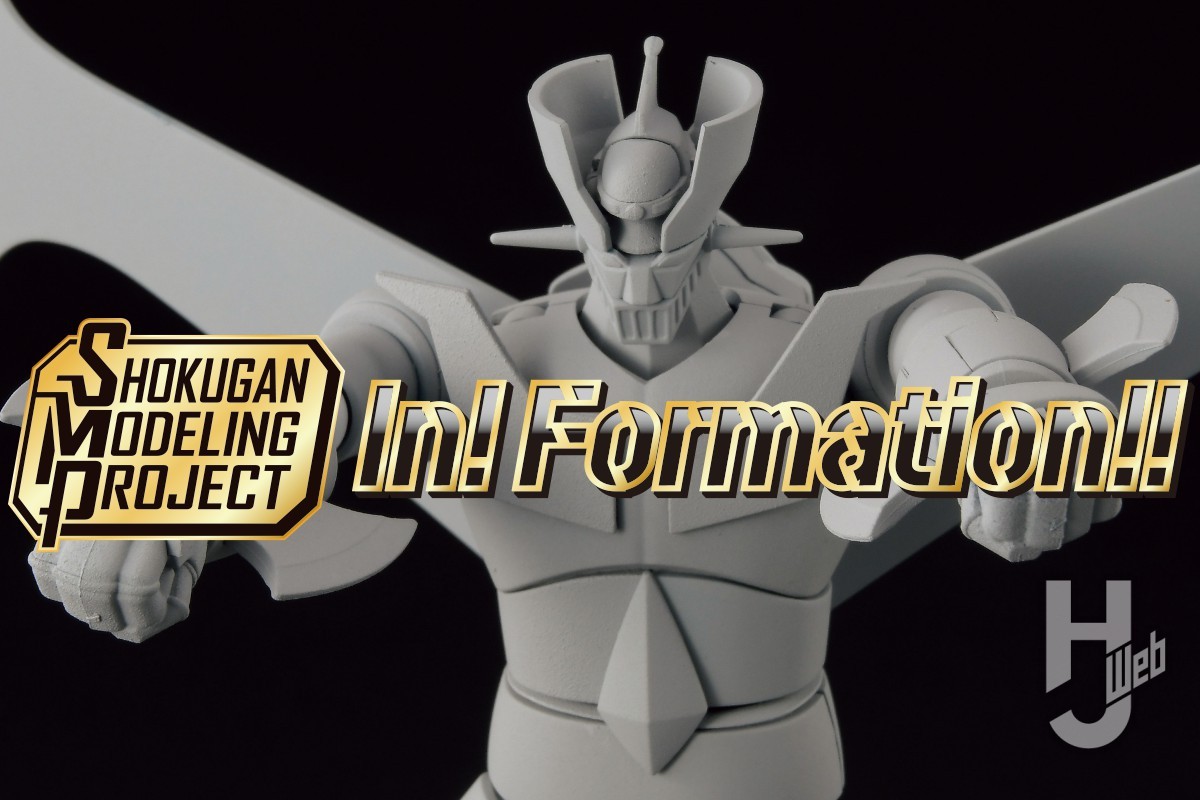【第4回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.09.15マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
第10章 鈴木の依頼
鈴木が会社の隣のビルにあるテレビ局から戻ったのは午後八時過ぎだった。
おれが──たぶん美伶も──うとうとしかけたところをインテリホンで叩き起こされ、しぶしぶ着替えて部屋を出た。
美伶は血の付いたトレーナーをクリーニングに出してもらい、今は白いパーカーを借りていた。
受付前で鈴木と待ち合わせ、ビルの外へ出た。そこからは徒歩だ。小さい身体でヒョコヒョコと先導する鈴木に着いて行く。ボディガードも二人同行した。
鈴木の行きつけという高そうな中華料理店に入る。ボディガードを部屋の隅に控えさせ、三人で丸い回転テーブルを囲む。菜食主義の鈴木に合せ、全員がベジタリアンコースとなった。
鈴木が気を利かせてメニューを読み上げた。
「季節野菜のオードブル、揚げ湯葉で作った北京ダック、蓮根餅、キノコの昆布出汁蒸しスープ、揚げ野菜、野菜カレー風味パパイヤ詰め焼き、大豆ミート炒め入り緑豆粉絲スープヌードル──」
「〝粉絲〟って何だい?」
と、おれは訊いた。
「北京語で〝春雨〟のことだ。もっとも、ここでは〝春雨〟という名の食品は無く、〝春の雨〟以外の意味は無い」
と、鈴木は言った。
やはり〝喩え〟という概念も希薄らしい。
「それにしても、見事に野菜のみを使った料理だ。スーさんは前から精進料理が好きだったよね」
鈴木は頷いた。
「粗食のことをそう呼んでただけだがね。しかしここには〝精進〟という言葉も無い。ただ、動物を大事にしようという考え方はある。精進出汁のようにかつおを使わず昆布だけの出汁がある。〝キノコの昆布出汁蒸しスープ〟はたぶん〝キノコの精進蒸しスープ〟のことだ」
「へえ……」
それからおれたちは黙々と料理を口に運んだ。肉類は一切無いが、高級店らしく素晴らしい味だった。美伶も安心したのか旺盛な食欲だった。
「お嬢ちゃんのお口に合ったかい?」
と、鈴木が訊いた。
「とっても美味しいです!」
美伶が答えた。
おれも〝転移〟以来ほっとするひと時だったが、口中の食物を咀嚼しつつ、ふとした拍子に元の世界のことが無性に気がかりになった。
あの後、新宿は核の炎に焼かれたはずだ。
×××の戦術核の威力や規模はよく知らないが、どこまでが被害に遭い、どこまでが無傷で済んだのだろうか。──母の病院はどうしたろう……。
さらに、こちらの病院とゾンビについて思いを巡らす。あの地区が封鎖されたとして、果たしてそれで安全なのだろうか。人知れず他の地区でも発生しているのではないか──。
考えがぐるぐる回るばかりで何の進展も無い。諦めて口中の物を咀嚼し、嚥下する。
「お嬢ちゃんのオヤジさんはDVなのかい?」
料理がひとしきり出終わった頃、鈴木が美伶に単刀直入に訊いた。ストレートにもほどがある。
「はい。ママの再婚相手です」
なんと、美伶も躊躇なく答えた。
「嫌いなんだろうな……」
「大っきらい!」
美伶は細く形のいい鼻梁に皺を刻んで吐き捨てた。
「本当のお父さんはアメリカ人だそうだ」
と、おれ。
「アメリゴ人です!」
美伶が訂正すると、おれの事情を知っている鈴木がクックと笑った。
「お母さんはどうしてるんだ?」
「夜のお仕事。本当はママも好きじゃない。新しいパパの味方ばっかするし」
「そうか……じゃあ、僕の所にずっといてもいいぞ」
と、鈴木はあっさり言った。
「ほんと? うれしい!」
美伶が目を輝かす。
「おい、そんなことして大丈夫なのか」
おれは焦って訊いた。
「この世界は存外、子供の自由が認められているんだ。留守電の一本も入れておけばいい。それに僕は警察にも児相にも知り合いはいる。いずれはそっちに任せる」
「そうなのか……君らがいいのなら、おれは別にいいんだが」
おれは息をついて、ジャスミン茶を啜った。
「ところで腕の傷の具合はどうだね」
と、鈴木がまた美伶に訊く。
「はい、大丈夫です」
「熱は無いか? 身体の怠さとかは? 頭痛は?」
「全然ないです」
「それはよかった。バイキンが入ったりするとよくないから」
「ありがとうございます」
やはり鈴木も感染のことを気にしているようだ。自分の社屋に入れているのだから、当然と言えば当然だろう。
「──ときに、うちの会社のホームページは見たか?」
鈴木は話題を変え、おれに言った。
「見せてもらったよ」
「軍用モデルは開発しないと書いてあっただろう」
「ああ、書いてあった」
「あれは嘘だ」
おれはアメリカ、いやアメリゴ人のように肩を竦めた。
「そんなことだろうと思った」
「実は介護用の二〇倍のパワーと三〇倍の強度のあるヤツを作っている」
「つまり本物のパワードスーツということか」
おれは腕を組んだ。
「そうだ。骨格試作まではできている。あとは外装をデザインして取り付けるだけだ。お前が昔描いたデザイン画を思い出しながら設計者に指示を出しているんだが、うまく伝わらないのでなかなか捗らない。おれに絵心が無い上に、記憶が曖昧だからだ。うっかり、あのノートにも描き写していない」
「そんなことにこだわっていたのかい」
「そりゃそうさ。スタジオぬえのデザインしたパワードスーツは、かっこ良すぎてダメだということで、お前と意気投合したじゃないか。原作には〝まるで××症にかかったゴリラのようだ〟とあった」
「正確には〝××腫〟だ」
「意味は同じだろ。だから、もっと頭でっかちでずんぐりしているべきだ。こちらでは多少不細工な方がウケるからな」
なるほど。ウケを気にしていたのか。マーケティングが苦手と言ってはいたが、やはりビジネスマンだ。
美伶が杏仁豆腐のデザートを食べるのも忘れ、おれたちの話をポカンとした顔で聴いている。子供に聴かせていいものだろうか。
「まあ落ち着いてくれよ。──なぜ今、その話なんだい?」
と、おれは言った。
「察しが悪いな、頭の打ち所でも悪かったのか?」
「元々頭はよくないよ、知っているだろう。もったいぶらずにはっきり言ってくれないか」
鈴木はまた顎に手をやった。周囲に目を配ってからおもむろに口を開く。
「恐らく早晩、政府によって〝存命遺体〟の掃討作戦が検討されるだろう。正式に存命遺体が文字通り〝遺体〟と認定されるに違いない。だから殺──いや〝無力化〟してもいいということになるはずだ。だがどうやればいいのか決定打に欠ける。なにしろ奴らは手強い。リミッターが外れていて怪力を発揮するし、痛み知らずだ。それにどんなウイルスが──まあそれはいい。とにかくそこで、まずは視察隊を送り込むことになった。しかし機動隊やHATや警予隊の通常装備では甚だ心許無い。そこでおれがフルクローズドタイプのパワードスーツの使用を提言した」
「軍用パワードスーツだと言ったのかい?」
「言うわけない。災害復興用という名目だ。もちろん〝パワードスーツ〟という名称でもない」
おれは唸った。
「さすがはいい着眼点だ」
「当然だろう。──あっちの世界のゾンビ映画ではなぜアーマーの類が出てこないのか不思議でならなかった。現代が舞台ならパワードスーツのテクノロジーだって追い着いているはずだろうに」
「そりゃあ、サスペンスにならないからな」
「これだからフィクションてやつは……」
と、鈴木が顔を顰めた。
「スーさんもすっかりここの人間だな」
おれが苦笑すると、鈴木はフンと鼻を鳴らした。
「話を戻そう。──そこでだ。せっかくなので、ゴリに設計図の修整を頼みたい」
ここでは他にやれる人間がいないのか。おれ自身も製図など高校卒業以来だ。
「何が〝せっかく〟なのかはわからないが、そらまあ、やれと言われれば……」
「そうか。思い切りゴリの好みに変えてもらってもいい。早速明日からかかってくれ」
おれは片手を挙げて頷いた。
「ここまで面倒見てくれて、さらに念押しするのは気が引けるけど、〝転移〟の件もくれぐれも頼むよ」
「うむ」
「あの……」
と、美伶が声を出した。
「ごめん、君を蚊帳の外に出してしまっていた」
おれは謝った。
「蚊帳? まだ夏じゃないけど……」
「いや、つまり、仲間外れにしてごめん」
「じゃなくて……鷲尾さんと鈴木さんて、けっこう歳の差があるのに、なんでタメ口なんですか?」
おれたちは十歳児の素朴な質問に対し、答えに窮してしまった。