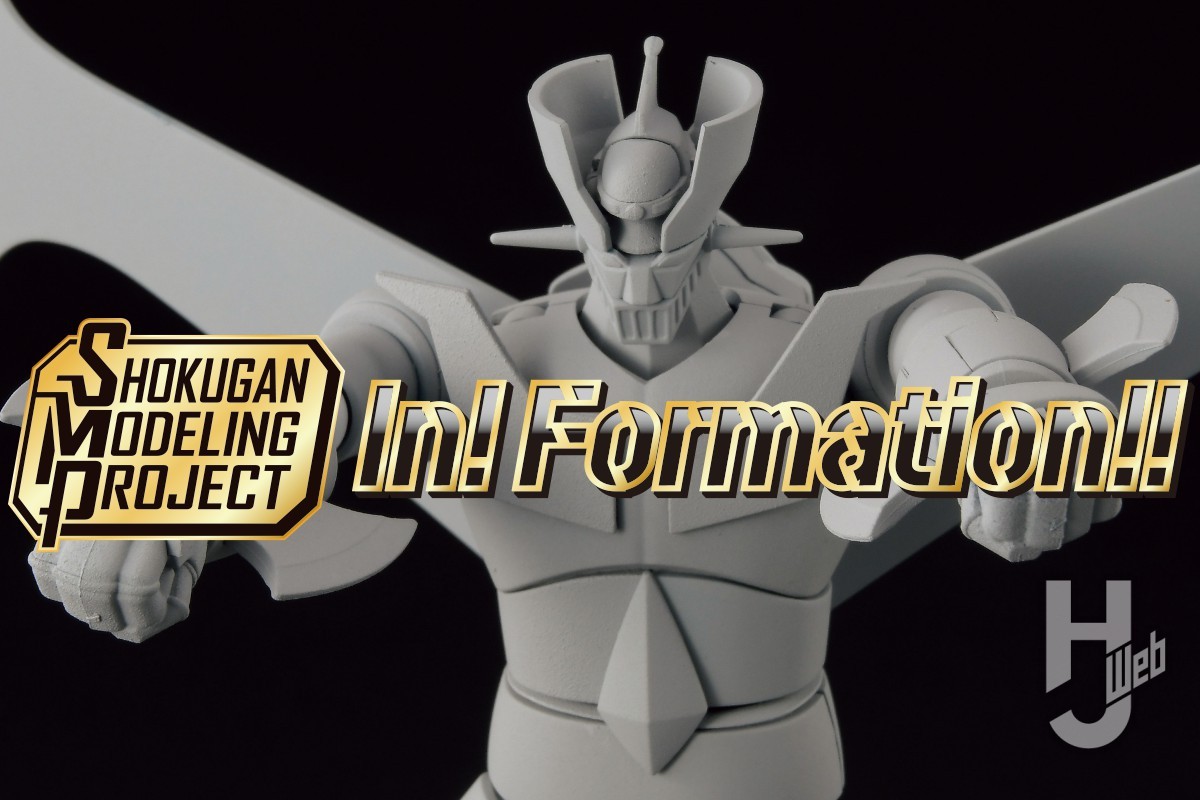【第3回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.09.08第8章 鈴木のレクチャー
鈴木は話を続けた。
「まあ、そもそも試験問題が簡単だったんだがね」
「ん?──というと」
「僕がこっちの世界に飛ばされた時、タイムラインをほぼ十年遡っていたのさ。僕は元々京大の試験問題を過去十五年分解いていて、傾向と対策もできていた。もちろん色々な固有名詞は改めて記憶し直さなければならなかったが、理科系の科目は基本、普遍的だからな」
鈴木はさらりと言ったが、十年もずれていたのか。それは反転世界に来た以上に混乱したのではないか。
「十年……相当大変だったみたいだね」
「そうでもない。テクノロジーが十年分、いやもっと古いから、僕の方が有利だった」
「するとスーさんは今、おれより十歳年上ということになるのか」
「そうだ。僕は今年三十六になる。在学中にベンチャー企業を起こして成功、もう十七年だ」
おれは感嘆の溜息をついた。
「頼る者もいないのに、たった独りでここまでやってきたとは……凄い。おれには絶対無理だ。今だって正気を保っているのがやっとだよ」
鈴木は首を振った。
「いや、僕の場合はむしろこっちの方が伸び伸びやれてよかったよ。僕に目を付けるような奴はいなかったからな」
逞しいな、とおれは思った。しかし一方で、得体のしれない不安感がもくもくと湧き上がるのを感じていた。
それが何なのかは、わからないのだが……。
「元の世界に戻る方法を探したりはしなかったのかい?」
「ああ、まったくそれはしなかったな。──考えてもみろよ。あんなクソ溜めみたいな所にわざわざ戻る気が起きると思うか? 断然こっちの方がいい」
「スーさんはそうか……でもおれは戻りたい。病気のお袋が心配だし、おれを心配してくれる女性もいる。大事な仕事もある。なあ、何か戻る方法は無いだろうか」
「女性、ねえ……」
と、鈴木は口の端を曲げた。
「なんだよ。いや、意外だろうけどさ」
「すまん。──さっき、核ミサイルが落ちたと言ったな。そんな場所に戻ってどうする。でかいクレーターと放射線しか残っていないぞ」
「そうかもしれない。……だけど、確かめないではいられないんだ」
「……未練があるんだな。そこは逆にゴリが羨ましい」
鈴木は紅茶をズズッと啜りあげた。
「そう思うなら力になってくれないか」
「そんな〝前世〟だったってことが羨ましいと言っただけだ。僕の〝前世〟はそんなことはない」
鈴木が紅茶をカップに注ぎ、おれのカップにも入れてくれた。
「なんとか……なんとか頼むよ」
おれは頭をテカテカのテーブルにこすりつけた。
「……さっきも言ったとおり、僕は戻る方法を探ったことはない。だが──たぶんやってもかなり難しいと思う」
「え……やっぱりそうなのかい?……スーさんの頭脳や資金力をもってしても?」
「考えてもみろ。次元に裂け目を作るには莫大なエネルギーが要るはずだ。お前の場合は核爆発だったろう。僕の場合は地震エネルギーだと睨んでいる。僕が転移した二日前に東日本大震災が起きた」
二〇一一年三月……両者を繋げたことはなかったが、言われてみれば確かにそうだった。やはり次元を超えるには相当な量のエネルギーが必要なのだろう。
「そうなのか……」
「いくら僕でも核や人工地震に手を出すわけにはいかないしな……しかし、方法を探る手助けくらいはしてやる。──だが、焦るなよ。今日明日というわけにはいかない」
おれは手を合わせた。
「よかった……」
「その代わり──お前にも協力してもらいたいことがある」
「……協力?」
協力はいいが、今のおれに出来ることなどあるのだろうかと思った。
「もう知ってるだろうが〝存命遺体〟のことだ」
存命遺体──ゾンビ。忘れようしていたのに、思い出させられてしまった。
「……ああ。今日この目で見たよ。あれは……まるで〝ゾンビ〟じゃないか。まさか実在するとは思わなかった。だがなぜ〝ゾンビ〟という単語を誰も使わないんだ?」
鈴木がまたニヤリと笑った。
「──それは、この世界には〝ゾンビ〟という概念が無いからだ。ブードゥー教も無い」
「概念……」
やはり。
美伶とのやりとりで薄々感じてはいたが、やはりそういうことなのか……。
「思っていたとおりだ。もしかしたらこの世界にはそもそも──〝フィクション〟という概念が無いんじゃないのか?」
おれは鈴木の表情を窺った。
「はっは!」
と、鈴木は大声を上げた。
「……?」
「もう気が付いていたか。さすがは元相棒だ、鋭いな。そのとおり〝フィクション〟が無い。SFもホラーも、神話も昔話も無い」
「一切合財無いのか!?」
「いや──厳密には、ある。ただその〝量〟が圧倒的に少ない。だから、正確を期するなら、フィクションを楽しむ文化が成熟していないと言ったところか。ごく一部の好き者たちが隠れてこっそり楽しんでいる、ということはあるらしいが……」
ここにも〝オタク〟のような人々が生息しているらしい。だが、その道の険しさは想像を絶する。
「そうだな──フィクションというか、想像の産物という概念はある。それがまったく無かったら、まず〝組織〟というものが生まれない。そして共同作業ができなければ文明は発達しない。会社も法人も無いのでは僕の事業はにっちもさっちもいかない」
「ああ……なるほど……」
おれは深く頷いた。
「また、宗教に似たようなものはあるが、聖書や仏典のような説話はくっ付いてこない。劇的なものが何も無い純粋な事実に基づいている。この世界にある〝お話〟は、基本ドキュメンタリーだ。そうだな──ルネッサンスと社会主義革命がいっぺんにやって来て、盆と正月がすっかりどこかへ行っちまったような感じだ」
最後は鈴木らしからぬギャグを混ぜてきた。
「ドキュメンタリーだけ……やっぱりそうか」
「前の世界でも〝読書〟といえば実用書しか読まず、小説を読むのは何も得られないので時間の無駄、という無粋なやつらがいたが、ここでは皆がだいたいあんな感じだ」
確かにそういう人間はいた。ウンザリと思い出す。
「読書といえば──実はおれは、元の世界ではマンガ原作をやっていたんだ。君も知っているとおり元々はマンガ家志望だったけど、編集者の勧めで原作者に転向した。もうすぐ連載が始まる……ところだった」
「そうか。原作者とはいえ一度は夢が叶ったんだな──。よかったじゃないか」
「だから……フィクションの無い世界なんておれには考えられない。だからこそ、戻りたいんだ」
鈴木は顎をゆっくりと撫でた。
「まあ気持ちはわかるが、悪いことばかりじゃないぞ。僕の会社の名前を知っているだろう。だが、この世界のハインラインは、いるにはいるがSF作家ではないし有名でもない。だからあの『宇宙の戦士』も存在しない。ということは〝パワードスーツ〟は存在しない。スペースオペラもパルプ雑誌も無い。したがってジェネラル・エレクトリック社の元祖強化外骨格〝ハーディマン〟も生まれなかった」
おれは大げさに肩を竦めた。
「……それでつまらなくないのかい? 当然『アイアンマン』だって無いわけだ」
「もちろん。だから、そこに目を付けた僕は世界で初めて強化外骨格を作ったというわけさ。特許も取得済みだからライセンス料も入る。そういう世界だ。──僕にとっては、つまらないどころか面白くて仕方が無い」
すなわち彼がアイアンマン=鉄人なんだ。
「それで金持ちなんだな」
鈴木が紅茶を注ぎ足そうとしたが、ポットは空だった。鈴木は舌打ちをした。
「実はそっちの儲けはまだ大したことはない。学生時代に開発した自律型自動掃除機〝ハイヤード・ガール〟が大当たりしたのさ」
「〝ハイヤード・ガール〟だって? 聞いたことがあるぞ。……ああ、それもハインライン原作の『夏への扉』に出て来るロボット掃除機か。──しかしそれって今でいう〝ルンバ〟のことでは?」
「そのとおり。〈アイ・ロボット社〉のあれをパクって商品化した。まだこっちには無かったからな。高校時代に中学生の家庭教師のバイトをしてた家にあったやつを分解したことがあって、構造を書き留めておいたからすぐに作れた」
鈴木は立ち上がるとデスクの方へ行き、抽斗から何やら取って戻ってきた。
その手には一冊の分厚いノートが掴まれていた。水に濡れたことを物語るかように波打っている。確かテレビ出演の時も持っていた。
そう……あの懐かしい〝アイディアノート〟だった。
鈴木が差し出したので、両手で恭しく受け取る。
壊れ物に触れるように、ゴワゴワしたページをめくってみる。以前見せてもらった時のまま、細々した文字や図がビッシリ書き込まれていた。鉛筆書きなので、水の影響はほとんどない。
「しかしお掃除ロボに〝ガール〟と名付けるって……コンプラ的にどうなんだ」
と、おれは言った。
「なんだ〝コンプラ〟って」
やはりこれも常識ではないらしい。
「いや、別に知らなくていい。──それにしても、相変わらず要領がいいな」
「こっちは文字通り裸一貫からやり直したんだから、そのくらい許されてもいいだろう。もちろん独自の発明アイディアはいくらでもあるが、あっちで既にマーケティングに成功したものから商品化した方が効率がいい。──まあ、正直いうと僕はマーケティングは苦手だしな」
「しかし『アイ・ロボット』と言えばアシモフだけど──スーさんはアシモフの方が好きだったんじゃないのか? 社名にしそうなもんだが」
「ああそうだったよ。しかしここではアシモフは実在するうえに、九十九歳でまだ存命で、小説は書かないものの、バリバリの科学評論家かつ歴史学者として世界的な有名人だ。おいそれとは名前を拝借できない。ここでは著作権よりはるかにそっちの方がうるさいんだよ。クソ!」
そう言って鈴木は頭を掻きむしった。
「そうなのか。すると、〝ロボット〟という単語そのものはどうなんだ? 君はロボットは開発していないのか」
「実は残念ながら、ロボット的な機械の開発だけは他社がとっくにやっている。チャペックの『R.U.R.』は書かれなかったから〝ロボット〟という単語は生まれなかったが、〝オートマタ〟の方で定着している。自動機械やカラクリ人形はこっちにも昔からあったからな。僕はせいぜい国内のオートマタ学会に名前を貸している程度だ」
〝ロボット〟は、もともとチェコスロバキアの作家カレル・チャペックが、〝ゴーレム〟の伝説を元にした自身のSF小説のために生み出した造語で〝労働機械人間〟を意味するが、伝説もSFも存在しないこの世界では、たまたま共通語にならなかったらしい。
「オートマタねえ……。カラクリ人形は宗教上の必要性で生まれたと聞くけど」
「宗教のことはよく知らん。──とにかく〈ソニー〉の〝アイボ〟や〈ホンダ〉の〝アシモ〟みたいな物は既に商品化されているのさ」
「やっぱり〝ロボコン〟みたいな競技もあるのかい?」
「ある。〝マタコン〟と呼ばれてこちらでも盛んだ」
オートマタ・コンテストで〝マタコン〟か。
「それはまた珍妙に聞こえるね」
「──おっと、脱線し過ぎた。そろそろ話を戻していいか?」
「ああ、ごめん」
「僕は〝存命遺体〟対策委員の一人に選ばれた。そこでお前にも知恵を貸してもらいたい。住まいも世話するし、給料も払う」
その時、窓のブラインドが自動で上がった。日が沈んだのだ。おれは瞬き始めた六本木の夜景を眺めた。確かに心惹かれる眺めではある。
「うう、気持ち的にそんなに長居はしたくないが……とりあえず、わかったよ」
ぼくは片手を挙げて同意を示した。
「では、早速本題に入らせてもらう。お前は僕よりゾンビに詳しかったよな。〝存命遺体〟をどう思う?」
話題がゾンビに戻った。
「詳しいったって、普通よりちょっと知ってるだけだよ。まあでも──あれはまさに〝ゾンビ〟だな。『地獄が満員になった時、死者が地上を歩き出す』ってやつ。もちろん元の世界ではフィクションだけど」
「それが本当に現れたわけだ。ここでは地獄も天国も概念が無いがな。発生したのはここ半年といったところだ」
「ここ半年? 最近だな。で、実際にどんな特徴があるんだい?」
「凶暴化していて人間を襲う。ダメージを受けても無反応だ。身体がボロボロになっても襲ってくる」
おれが新宿で見たとおり、ゾンビそのものだ。
「〝遺体〟というからには死んでいるのかい?」
「そこははっきりしない。見た目が死人のように見えるのと、死んだと思って霊安室に安置しておいたら動き出したということから、そう呼ばれるようになったらしい」
「一時的に仮死状態にあるんだろうか。ハイチのゾンビのように」
「こちらではハイチではなくサン・ドマングだ。ブードゥー教もゾンビも無いが、似たような言い伝えはある。例のフグ毒による仮死化は眉唾物だと言われているが、別の物質の可能性はある」
「そうか。他に特徴は? やっぱり人を食うのかい?」
「噛みつくし、肉を咀嚼しているようだが、嚥下しているかは確認されていない」
言いながら鈴木は顔をしかめた。彼は昔からグロは苦手なのだ。
「まさにゾンビの特徴が揃っているね。──しかしどうして発生したんだろう。原因は?」
「ゴリはどう思う? ゾンビ映画はいっぱい観ているだろう」
訊かれて記憶を総動員する。
「単に映画の例で言うなら──呪術というのはとりあえず外して──例えば『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』は破壊された探査衛星の放射線が原因だったかな。そのインスパイア作品の『悪魔の墓場』では害虫駆除装置が原因で、下等生物同士が殺し合うように仕向ける超音波だったはず。……それから『サンゲリア』は風土病、『28日後……』は凶暴化ウイルス──」
その他にも化学兵器や彗星の細菌、宇宙寄生虫、果ては農薬入りワインまでを列挙した。
鈴木は渋い顔で手をひらひらさせ、おれを制した。
「そうだな……リアリティがあるのはやはりウイルスか。〝存命遺体〟は実際に増えていると報告されているから、たぶん感染症の類だろうな。学者が調べているが、まだ病原体は見つかっていない」
「警察はどう対処しているんだい?」
「とりあえずは精神異常者として保護する方針らしいが、相手が凶暴過ぎてなかなか対応できないらしい。負傷者も出ている。相手は武器も持っていないから、おいそれとは発砲はできない」
おれはしかし、ゴールデン街での発砲音を思い出していた。
「撃ったとしても効き目は無いんじゃないのか? テレビで見たよ。フォルモサとかいう街の警官の映像」
「フォルモサか。××のことだよ。ここでは国だ」
あれは××だったのか。道理でアジアっぽいと思った。大国である××の実効支配下にあったはずだが、国になっていたとは。
「映像を見た限り、完全に制圧するにはやはり脳を破壊するしかないらしいね」
鈴木は首を横に傾けた。
「あれはたまたまじゃないのか? 脳を破壊するまで死なないって、映画の設定だろう。ゴリの好きなナントカって監督が作ったルールだ」
「ロメロね」
再びドアにノックの音がした。
「はい」
「社長、そろそろお時間ですが……」
と、秘書が綺麗な顔を覗かせて言った。
「もう五時か……。ゴリ、悪いが僕はそろそろ出掛けるよ。テレビの生番組に呼ばれている」
鈴木が腰を浮かせた。
「おれはどうしてればいい?」
「この会社にはゲストルームがいくつもある。それを一部屋貸そう。係の者に言っておく。僕が帰るまでそこでくつろいでいてくれ。風呂桶は無いがシャワーがある」
「助かるよ」
「備え付けのテレビもあるから、僕が出る番組を観ているといい。六時から3チャンネルだ。──じゃあ、行こう」
鈴木はスプリングコートを羽織り、おれたちは社長室を出た。
受付の前に戻ると妙な雰囲気になっていた。
美伶がベンチに座り、その隣に八重歯の受付嬢と白衣を着た初老の女が立っていた。
「あ、社長」
と、八重歯が言った。
「その子はいったい……?」
鈴木が誰にともなく言った。
「ああ、言うのを忘れてた。おれが連れて来たんだ」
と、おれは慌てて言った。
「先生、どうしました?」
と、鈴木は白衣の女に話しかけた。たぶんクリニックの医者で、互いに顔見知りのようだ。
「このお嬢ちゃんのことで、ちょっと気になることがありましてね」
と、女医は言った。美伶の傷のことで問題が発生したのか。もう発症してしまったのか。おれはびくびくしながら次の言葉を待った。
「虐待の疑いがあります」
何だって? 噛まれた傷の事ではないのか。
「本当ですか」
「これです」
と、女医が美伶のトレーナー左の袖を捲る。腕の内側に、小さな赤黒い斑点がいくつもあった。
タバコを押し付けた痕だとわかった。
「どういうことだ」
鈴木がおれの方を見ながら言った。おれは首をぶんぶん振った。そもそもタバコは吸わない。
「鷲尾さんは関係ありません」
と、美伶がか細い声で言った。
「お父さんにされたんですって。警察か児相に相談した方がいいのでは」
と、女医が言った。
「こっちもですか」
と、鈴木が右腕の包帯を指差した。
「違うとは言ってましたが、実際どうなんでしょうね」
「実は新宿で噛まれたんだ……」
と、おれは鈴木だけに聴こえるように耳打ちした。女医に伝えるかどうかは鈴木の判断に委ねた。
「わかりました……この件は僕が責任を持って預ります」
鈴木が女医に対して決然と言った。
「そうですか。では、後はお願いします」
その返事を待っていたとばかりに、女医は足早に出て行った。他の診察の途中なのだろうか。
「社長、もうお時間が……」
と、いつの間にか来ていた秘書が声をかけた。
「ゴリ、その子を黙って家に帰すわけにはいかないな」
と、鈴木は言った。
いじめや虐待には人一倍恨みのある男だ。きっと美伶に共感したに違いない。
「そうだな。先生の言うとおり児相──」
「わたしは鷲尾さんといたいです」
美伶が遮って言った。
「えっ」
おれはまた言葉に詰まった。
「そうか。じゃあゴリ、後は任せた。戻ったら飯でも行こう」
おれの返事も待たずに、鈴木は出て行った。
つづく
この物語はフィクションであり、実在する人物・団体等とは一切関係がありません。
【マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした】
第3回 ←いまココ
第4回 new
\オススメブック!!/