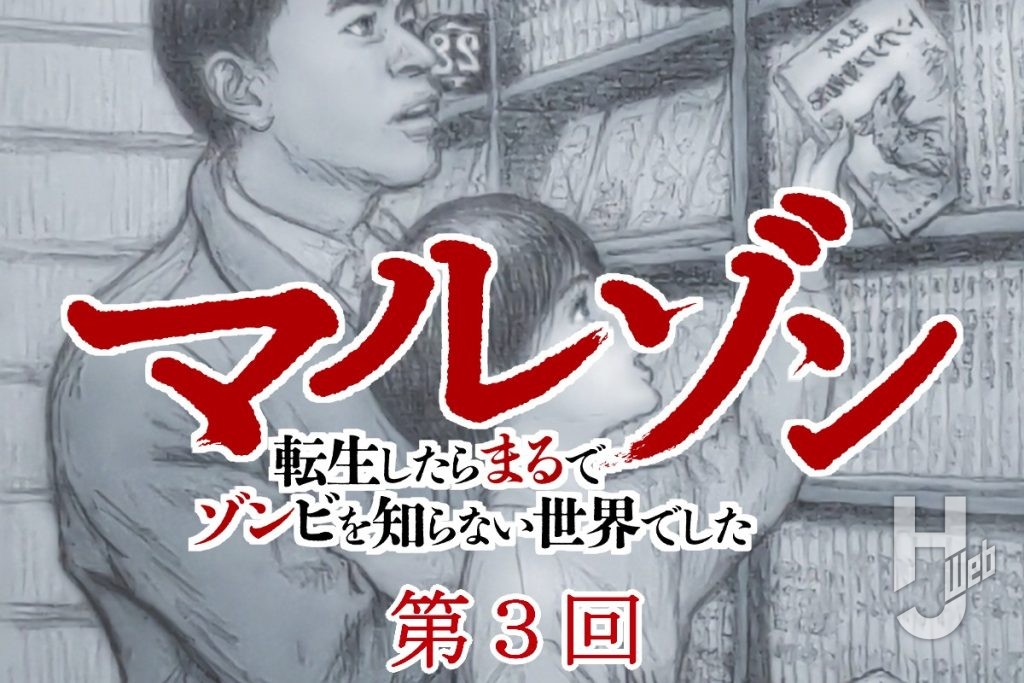【第3回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.09.08マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした
美伶とともにゾンビの侵入で混乱する病院を脱出した鷲尾は、街頭モニターで目にしたコメンテーター、鈴木鉄人に高校時代に行方不明となった親友、鈴木賢治の面影を見る。「もしかしたら鈴木も何かの影響でこの世界に?」孤立無援で頼る者のいない鷲尾は、一縷の望みをかけ、鈴木とコンタクトを取るためにネットカフェへ向かうのだった……。
原作/歌田年
イラスト/矢沢俊吾
ZIMデザイン/Niθ
第3回
第6章 フィクションの無い世界で
ズラリと並んだ背表紙はいずれもカラフルで、見慣れた感じがした。
鏡文字のタイトルを見て行く。
『マンガ世界の歴史がわかる本』『まんが日本の歴史がわかる本』『マンガで読む国際政治』『漫画で詳解! 経済学入門』……。堅いタイトルの本ばかりだった。
棚を移動してみる。
『図解・自動車の仕組み』『まんが料理教室』『マンガ版 オーディオ電気数学:基礎からわかるアンプの設計・製作入門』『マンガで学ぶ家庭の医学』……。実用書の棚だった。
物語系の棚を探す。
『マンガ版/学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて元治大学に現役合格した話』『拝啓、アスペルガー先生 マンガ版』『実録劇画・義範ちゃん誘拐事件』『コミック・実際に起きた怖い話』──。文字通り、実際に起きた話ばかりだ。しかし見たことがあるようで微妙に違和感のあるタイトルばかりだった。
美伶の所へ行く。
「君はマンガが好きなのかい?」
「だ~い好き!」
美伶が目をキラキラさせたので、『実はおれマンガ原作者なんだ、エヘン』と言おうとしたが、この世界では証明する術がないことに気付いて引っ込めた。
「君はどんなのを読むんだい?」
「これとか、これとか」
美伶が手にしていたマンガ本を見ると、『まんがトンプソン動物記』と『漫画 君たちはいかに生きるか』だった。
「難しいマンガを読むね。『ワンピース』とかは読まないの?」
おれはもしやと思い、訊いてみた。
「ワンピース? お洋服の本ですか?」
美伶は小首を傾げた。
「『ワンピース』を知らないのか。じゃあ『ドラゴンボール』は?」
「知りません」
「『ウルトラマン』とか『仮面ライダー』は?」
「ううん……」
男の子向けではダメか。おれは必死に女の子が好きそうなキャラクターを思い浮かべた。何かは引っかかるのではないか。
「じゃあ、『プリキュア』はどう?」
やっと搾り出したが、やはりこれも美伶は首を横に振った。
しかしおれはある疑念を覚え、棚を探し始めた。タイトルこそ違え、似たようなキャラクターや作品があるはずなのだが。
だが、一向にそういう本が見つからない。
どの主人公もあくまで普通の人間であり、現実の職業に合せた服装をしているだけだった。特殊な姿をしている者はいない。あとはせいぜい動物をデフォルメしたようなキャラクターだ。
仮面のヒーローも魔法少女も、ロボット兵器も宇宙戦艦も見当たらない……。
美伶はオープンスペースのソファでマンガを読み始めた。
おれは一人、ブースに戻った。慣れない手付きでキーボードを打ち込み、左手でマウスを動かした。思った以上に時間がかかる。
知っている限りのキャラクター名を片っ端から打ち込んで、検索をかけてみたものの、どれ一つとしてヒットしなかった。
たまに掠ったりもしたが、結果、まったく見当はずれだった。
例えば〝仮面ライダー〟を検索すると『もしかして仮免ライダー?』と出るし、〝進撃の巨人〟と打つとプロ野球の〝巨仁軍〟のニュースが出てくるという調子だ。ましてや〝ゾンビ〟などカケラも出てこない。
つまり、こういうことではないか。
この世界にはフィクションという概念が無い。
空想上のキャラクター、作り話、そういったものが存在しない──。
美伶が〝架空〟という言葉を知らなかったはずだ。いや、〝架空請求〟というような用語はあるかもしれないが、一般的によく使う言葉ではないのだろう。
次いで、Captoorのマップを開いた。
元々おれも東京の地理が完全に頭に入っていたわけではないが、それは見事なまでに左右反転しているように見えた。
マップの縮尺をどんどん下げていく。ついに日本列島が現れた。お馴染みのタツノオトシゴが左を向いている。右側に覆い被さるように中国大陸がある。太平洋は左側だ。
ああ、この世界は……地球は本当に左右反転していたのだ!
小一時間ほど検索をした後、何度目かのメール確認をしたら、ついにハインラインお客様サポートセンターなる送り主からのメールが届いた。
急いで開く。
鷲尾啓介様
このたびは小社お客様サポートセンターへお問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。
お客様より頂戴しましたお問い合わせにつきまして回答させていただきます。
弊社社長・鈴木鉄人へのご取材ですが、本日午後三時よりお受けできるとのことです。六本木本社まで直接お越しくださいませ。
何かご不明な点がございましたら、代表番号までお気軽にご連絡下さいませ。
やった。
鈴木鉄人があっさり会ってくれることになった。
取材という扱いだが、まったく知らない相手ではこうはならないだろう。やはりあの鈴木なのか。
約束の時間は三時だ。既に二時を回っているから、そんなに余裕はない。急いで移動を開始しなければ。
いよいよ美伶ともお別れだ。
おれはブースを出て、熱心にマンガを読んでいる美伶に声をかけた。
「それじゃあ、おれはそろそろ出掛けるよ。色々ありがとう。ここの代金は払っておくから、オープンスペースなら六時まではいても大丈夫だ。でも早めに帰るんだよ」
「えっ、どこへ行くんですか? もしかして……」
と、美伶が訊き返した。
「うん。さっき調べてもらった鈴木鉄人の所だよ。メールの返事が来たんだ」
「ほんと? 鈴木鉄人に会うんですか。いいなあ」
「そんなにいいかい」
「えーと、えーと……わたしも一緒に行っていいですか?」
美伶はすがるような目で言った。
「え……体調は大丈夫なのかい?」
「はい」
「熱は?」
「ありません」
もし感染していたとしても、まだ発症する気配は無いらしい。
しかし……。
「でも、大事を取った方がいいよ」
「……一人だと怖いんです。家に帰っても誰もいないし」
美伶は悲しげな顔になった。
「友達と遊んだりしないの?」
「友達はいません」
いないのか。何か問題を抱えていそうだ。
いじめられたとも言っていた。神経内科に通っているというのも、それと関係があるのだろうか。
気の毒になってきた。
「そうか……だったらいいよ。一緒に行こう。でも夜までに帰るんだよ。君の親父さんやお袋さんが心配するといけないから」
「はい!」
「じゃあ、行こうか」
おれたちは店を出た。
〝大江戸線〟ならぬ〝御江戸線〟という名の地下鉄に乗る。
以降の案内は美伶に見てもらったから、おれは目と頭を悩ませなくて済んだ。アナウンスされる駅名はほぼ記憶にあるとおりだったので、ずいぶん安心した。