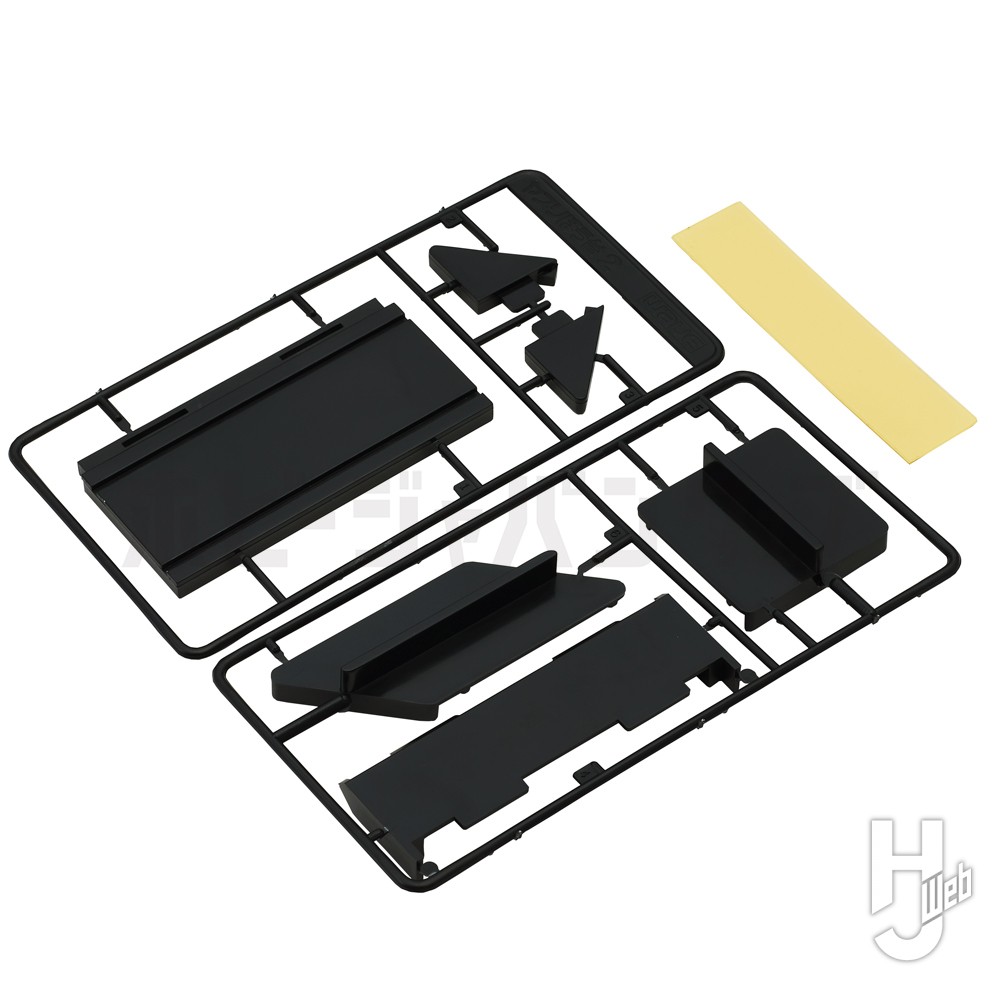【第2回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】
2025.09.01第5章 鈴木鉄人
鈴木賢治とは高校時代に一緒にSF研を作った仲だった。
二人で合作をしたことも少なくない。それは主にSFマンガだった。彼が設定やプロットを考え、おれが作画を担当した。鈴木もおれのことを皆と同じように〝ゴリ〟と呼び、おれは鈴木のことを尊敬の念を込めて〝スーさん〟と、さん付けで呼んだ。
というのも、彼は大変な読書家で、古今東西のSF小説にあまねく通じていたし、科学の知識も実に豊富だったのだ。頭の中ではいつも様々なアイディアが渦を巻いているようだった。
鈴木は、落ちこぼればかりの学校の中で常にトップの成績だった。実際、彼にはそぐわない学校だったのだ。
なぜそうなったかといえば、おれと同じような、いやそれ以上に劣悪な環境で育ったからだ。出生後すぐに捨てられた鈴木は孤児となり、養護施設に引き取られた。だが育つにつれ、巨大な頭に低い背、ひょろひょろの手足といった特異な容姿が顕著になっていき、施設内でも疎ましがられていたという。
中学校に上がる前にやっと里親が見つかったものの、その家で鈴木は単なる労働力として扱われていた。家には金銭的な余裕がまったくなく、教育にも無関心だった。いくら高い学力があっても、進学校に入ることは叶わなかったのである。
おれと同じ高校に入った鈴木は、自主的に高いレベルの受験勉強をして、難関大学を目指していた。いつかノーベル賞級の科学者になって金に不自由しない暮らしをするんだと、常々語っていたものだ。
高校でも当然のごとく容姿をからかわれた。付いた渾名は〝リトルグレイ〟。おれも他人のことを言えた義理ではないが、やはり鈴木の場合は特異過ぎたのだろう。成績がいいことも反感を買い、早くから不良たちに目を付けられ、酷いいじめに遭っていた。
おれは可能な限り鈴木を庇ったが、ある日とうとう悲劇は起きた。
それは三年次の冬。
彼は見事、京都大学工学部に現役合格したのだが、その報が校内を駆け巡った翌日、帰らぬ人となってしまった。
鈴木の合格を妬んだいじめグループに、鈴木の命と言っていい〝アイディアノート〟が奪われてしまったことが発端だった。
その分厚いアイディアノートには、鈴木が長年書き溜めた様々な機械の分解図や、発明のアイディア、研究論文の草稿、果てはおれとの合作マンガのネタまでがギッシリ詰まっていた。
『返してやる』と、いじめグループに深夜に呼び出されたが、結局、そのノートは多摩川に架かる橋の上から水の中に投げ捨てられた。鈴木は思わずそれを追って、多摩川にダイブしてしまった。
彼は真冬の川に流された。間もなく警察やボランティアによる捜索が行われたが、遺体はなかなか見つからなかった。
もちろんおれも必死になって連日鈴木を捜した。だが、やがて捜索は打ち切られた。
そして七年の歳月が流れた──。
未だに遺体が、いや髪の毛の一本でも見つかったという話は聞かない。
海まで流され、魚に食われて骨となり、深い海の底にでも沈んでいるのだろうと思っていた……。
その鈴木の面影を残す男が、今、大画面に映っている。
この世界に、おれの知っている人間がいる……。
まったくすがるものの無い今のおれには、もはや彼に会うことしか考えられなかった。似ているのではなく、もう鈴木その人にしか思えない。歳は取っていたが、たぶん何か理由があるのだ。
彼はあの時、死んだのではなく、何らかの方法でおれと同様に次元転移してきたのに違いない、そう確信した。
「鷲尾さん……どうしたんですか?」
美伶の声が回想からおれを引き戻した。
「うん? ああ、ちょっとね」
さて。
鈴木にどう接近しようか。
まずは本人について調べなければ。
おれはスマホを取り出してから、舌打ちをした。そうだった。この世界では電波が繋がらず、役に立たないのだ。
「君はスマホを持ってるかい? スマートフォンだ。おれのは壊れてて」
と、美伶に訊いた。
「スマート……ホン? もしかして〝インテリホン〟のこと? 持ってません。小学生は禁止だから」
だめか。この世界の教育もなかなかに厳しい。
どうする。おれは腕を組んだ。
一昔前に外でインターネットを使うとしたら、PCを探すしかなかった。
そうだ、ネットカフェだ。
SUICAも使える店があることは知っていたが、この世界にもあるだろうか。だが、あったとして、たぶんキーボードは使いづらいし、画面も読みづらいだろう。
そこまで考え、はっとして、おれは美伶を見た。
彼女がおれの目や手になってくれるだろうか。──依然として美伶が〝発症〟するのではないかという不安はあった。だが、この世界を知りたいという欲求──というか喫緊の課題──の方が勝っていたのだ。このままでは衣食住もままならない。
しかし……とさらに考える。これ以上、彼女を引き回してもいいものだろうか。相手は小学生だ。そして平日の昼間だ。傍からは児童誘拐犯とみなされても仕方がない状況だ。通報され、いつ警察官が飛んでくるやもしれない。そうすればすぐに新聞沙汰だ。おれはお袋や知り合いの顔を思い浮かべた。
あっ、と気が付き、おれは一人苦笑した。この世界でおれを知る人間はいない。どうとでもなれ。
とはいえ、美伶にも都合があるだろう。怪我の状態も心配だ。
訊いてみる。
「ところで今日は学校は休んだの? 早退?」
「休んでます」
「それじゃあ今日、まだ時間はあるかい」
おれは美伶に予定を訊き、また内心おかしくなった。大人の女性にはなかなか言えないのに、小さな女の子には平気で訊けるもんだ。
「はい、大丈夫です」
美伶は心なしか嬉しそうに返事をした。
「ちょっとネットカフェに付き合ってほしいんだけど。ネットカフェって、ここにもあるよね」
「あります!」
あった。よかった。
「この近所でどこか知ってる所はある?」
「うん、知ってます!」
「そこはSUICAは使えるの?」
「スイカって、食べるスイカ?」
「違う……これだ。電子マネーのSUICA」
と、おれはカードを見せた。
「うーん、よくわからないけど、たぶん……」
と言いながら、美伶が先頭を切って歩き出した。
アルタ、いやアリウの脇の細道を過ぎた。角を二度曲がる。そこは見覚えがあった。
左手に洋食屋があったので看板を見た。
AZOMIM
逆から読むと〈ミモザ〉になった。元の世界で、たまに名物のロールキャベツシチューを食べに行っていたレストラン〈アカシア〉に外観がそっくりだ。
その向かい側の地下に、マンガ喫茶兼ネットカフェはあった。
「ところで、君はコンピューターは使ったことあるかい?」
おれはまた念のため訊いてみた。
「もちろんあります! 学校のマイコンクラブに入ってるし!」
と、美伶は自信ありげに答える。
〝マイコン〟とはパソコンの昔の呼び方だったはず。ここでは定着しているらしい。
おれたちは狭い階段を降り、カウンターで手続きをした。電子マネーも使えるという。
案の定、おれたちを見た店員は不審げな視線を送ってきたが、おれは構わなかった。別に疾しいことをするわけではない。
めいめいにフリードリンクを持って、おれたちは個室に入った。
部屋は細長く、テーブルにモニターとPC・キーボード・テレビ・ヘッドフォン・マウス。合皮製の手狭なベッド兼ソファ。同じく合皮製のクッションが二つ。おれが知っているネットカフェとまったく同じだった。
この閉鎖空間でもし美伶が発症し、変転したら……いや、今は考えるまい。
キーボードを見た。やはりすべてが左右反転しており、おれの手が覚えた配列が通用しないのは間違いなかった。そしてマウスは左側にある。
「このタイプのキーボードは慣れていないんだ」
と、おれは言った。
ではどのタイプならいいのか、と訊かれたら困るのだが。
「代わりに打ってあげます!」
「腕は痛まないかい?」
「少し。でもこのくらい大丈夫です。ブラインドタッチもできます」
「それは頼もしい。じゃあ早速お願いしようかな。さっきの〝鈴木鉄人〟て人を検索してくれないか。鉄人の字は〝鉄の人〟だよ」
「はい、知ってます」
と返事をするや、美伶はデスクトップにある〝C〟というアイコンをクリックした。
〝Captoor〟という検索エンジンのポータルサイトが現れた。おれの知っている〝Google〟みたいなものらしい。
美伶はワードボックスに素早く打ち込んだ。
〝Hayapedia〟という、〝Wikipedia〟を思わせる事典サイトの一項目がヒットしたようだ。ページを出してもらう。
「これでいいですか」
おれは鏡を出すと、画面を映して左右反転させた。
「なんでいつも鏡に映すんですか?」
美伶が不思議そうに訊いた。
「ああ、こうするとブルーライトを直接見なくていいから、目が疲れないんだ」
「へえ~」
おれは咄嗟に作り話をし、美伶が感心した。『逆になって見えにくくないのか』という質問は出なかったので、ホッとした。
端からゆっくり読んでいく。
鈴木鉄人(すずきてつじん、一九八三年~ )は、日本の工学者であり、ハインライン株式会社の創業者兼CEO、元京都大学助教、元京都大学キベルニクス研究センター長。日本オートマタ学会理事。ワールドワイドCOEキベルニクス国際教育研究拠点・拠点リーダー、内閣府最先端研究開発支援プログラム「長寿と繁栄を支える最先端人支援技術研究プログラム」中心研究者、内閣府革新的研究開発推プログラムShOCKプログラムマネージャ。工学博士(京都大学、二〇一一年)。世界初の装着型パワーアシストマシンであるパワードスケルトン「RICO」を開発した。RICOの研究開発において海外から軍事利用の話があっても全て断っている。
「凄い……」
おれは感嘆の溜息をついた。
「ですよね」
と、美伶が同意する。
〝パワードスケルトン〟というか〝パワードスーツ〟は、SFの世界では古くからポピュラーなアイテムだ。ロボットのような外観を持ち、服のように人間が装着することで、その人の力を何倍にも増幅することができるというものだ。もちろん、外装を頑丈にすれば防御力も高まる。現実には介護の現場や災害時の危険な場所での活動に利用され始めている。
つまりこの鈴木鉄人は、この世界で初のパワードスーツの開発者らしい。おれのいた世界でいうと、〈サイバーダイン社〉の山海社長に相当するようだ。
サイバーダイン社の社名がハリウッド映画『ターミネーター』からの借用であるのと同様、この会社の社名が、世界で初めてパワードスーツを題材にしたSF小説『宇宙の戦士』の作者、ロバート・A・ハインラインに因んでいるのは明らかだ。確か〝リコ〟というのは同小説の主人公の名前ではなかったか。
おれの知っている鈴木もハインラインとパワードスーツが好きだった。高校の文化祭では、SF研の出し物としておれと鈴木は一緒に、本当に着られるパワードスーツを作ったものだった。アルミ板等を切り出したりして、かなり本格的だった(後で不良たちにボコボコにされたが)。
しかもこの鉄人氏も鈴木が目指した京大を出ているらしい。ますます鈴木賢治その人という確信が強まる。
やはり彼もおれと同様に次元転移してきたのではないだろうか。
リンクからハインライン社のホームページに飛ぶ。頭文字の〝H〟を図案化したカンパニーロゴが現れ、ポータルページに切り替わる。洒落たウェブデザインだ。
〝PRODUCTS〟のタグをプルダウンし、ハインライン社の製品を見てみた。強化外骨格型のRICOが並んでいた。丸みを帯びたポップな外観に、清潔感のあるオフホワイトのカラーリング。
RICOとは〝隷従・威力・着脱・応変〟という日本語の頭文字を取ったネーミングだという。英語の略称ではないのだ。おれの知っている鈴木も英語が苦手、というか興味がなかったのを思い出す。受験英語には苦労していた。
RICOにはいくつかバリエーションがあり、医療用下肢タイプ・福祉用下肢・自立支援用・腰タイプ介護支援用・同作業支援用・同自立支援用がラインナップされていた。
〝ABOUT US〟のタグをプルダウンさせると〝会社情報〟を選ぶ。最初に鉄人氏のメッセージと顔写真。テレビの容貌と同じだから最近の写真だろうか。年齢を重ねてはいるが、何度見てもあの鈴木だ。
続いて会社概要を見る。本社所在地は〈六本木ハイランド〉とある。おれの知っている〈六本木ヒルズ〉に相当するようだ。道順を確認するが、何もかもが左右反対で、なかなか頭に入ってこない。
とにかく、ここに行ってみよう。
しかし不在だったら意味がない。アポを取る必要があるだろう。〝アクセス〟を選び、電話番号を見つけ出した。が、自分のスマホは使えないし美伶も持っていない。
「ちょっと訊いてくる」
おれは番号をメモしてブースを出た。店員に固定電話を置いていないか尋ねると、あっさり「無い」との返答。
おれは呆然として出入口を眺めた。外へ出て探すのも苦労しそうだ。
肩を竦め、おれはブースに戻った。
ネットサーフィンを始めていた美伶に再び操作を頼む。
〝お問い合わせ〟というページへ飛ぶと、なにやら記入フォームが出てきた。ビッシリと書き込み欄がある。記入して返信を待つという形だ。
メールアドレス記入欄があり、ふと考え込んだ。どうする。そうだ、Gメールのアカウントを取ればいい。しかし登録先を探したが見つからない。
そうだった。〝フリーメール〟で検索してもらうと、〝Cメール〟というのが出てきた。なるほど、こちらの世界ではそう言うのか。美伶に頼んで必要事項を記入し、アカウントを取得してもらう。
再びハインライン社のフォームに戻り、頭の〝お問い合わせ項目〟をプルダウンする。〝資料ご請求〟〝RICOのレンタル・その他製品詳細について〟〝その他のビジネス・会社情報について〟等々、項目がズラリと並んでいる。
〝取材・イベント情報について〟を選択し、その下の項目から〝取材のご依頼〟を選択。あとは記入だ。美伶に再び打ち込んでもらう。
最後に肝心の〝お問い合わせ内容〟だ。
さて、何て書こう。
おれは散々考えたが、結局シンプルなものにした。美伶にタイプしてもらう。
鈴木鉄人社長の古い友人、鷲尾啓介と申します。
私もこちらに来ました。久々にお会いしたいですね。
返信お待ちしています。
「え、鈴木鉄人の友達なんですか!?」
美伶が驚く。
「かもしれないんだ」
「へええ」
送信。
一見、迷惑メールに見えなくもないが、鈴木本人に確認せずに捨てられることはないだろうとの確信があった。
とにかくメールは送った。あとは待つのみだ。
どのくらい待てばいいだろうか。
まあ、幸いここにいれば雨風は凌げるし飲み物もある。子供の好きなアイスクリームだってある。
「美伶ちゃん、少し待つことになるよ」
「わかりました。じゃあ、わたしマンガ取って来ます」
美伶はブースを飛び出して行った。
そういえば、この世界にはどんなマンガがあるのだろう。やはり『ドラゴンボール』や『ワンピース』、『進撃の巨人』のような人気作があるのだろうか。
「おれもそうしようかな」
そう呟くと立ち上がり、マンガの棚を見に行った。
つづく
この物語はフィクションであり、実在する人物・団体等とは一切関係がありません。
【マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした】
第2回 ←いまココ
第4回 new
\オススメブック!!/